カレー店の倒産増 背景に牛丼店
カレー店の倒産増 背景に牛丼店
2025/06/12 (木曜日)
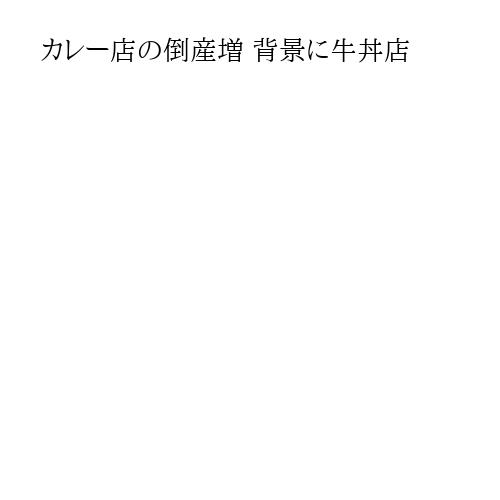
なぜ「カレー店」の倒産が続くのか 個人店を追い詰めるチェーンの戦略
はじめに
最近、日本全国で“カレーショップ”の倒産が相次いでいます。2025年3月期には負債1,000万円超の大型破綻店舗が13件を数え、過去最多を更新しました。その背景には、家庭料理の定番であった“ジャパニーズカレー”を支える主原料・米や野菜、肉の価格高騰があり、個人店や小規模チェーンが大手チェーンとの価格競争に苦戦していることが挙げられます。今回は、なぜ「カレー店」の倒産が続くのか、チェーン店の戦略も含めて多角的に分析します。
1.カレー店倒産の現状と要因
日本経済新聞などによると、2025年3月期に負債1,000万円以上で破綻したカレー店は13件に上り、これは直近の五年間で最多となりました。特に小規模個人経営店では原材料費の上昇が利益を圧迫し、客単価を上げる余地が乏しいまま赤字が膨らんだケースが散見されます。米価は過去1年でほぼ倍増し、5kgあたり4,260円に達するなど家庭用でも急激な上昇を記録(ロイター)。
2.原材料コスト高騰の背景
主要原材料の米は、2024年の悪天候による不作と消費者の備蓄買いで約60kg袋が26,400円と過去最高水準に高騰。さらに、夏場の高温で野菜(玉ねぎ・じゃがいも・にんじん)の価格も20~30%上昇。肉類やスパイスなど輸入食材は円安と世界的な物流混乱がダブルパンチとなり、飲食店の食材コスト率が従来の30%台から40%超へ跳ね上がっています。
3.大手チェーンの価格戦略と個人店への影響
ココイチ(壱番屋)やほか松屋フーズ系列の「マイカリー食堂」など大手チェーンは、仕入れ規模を生かした購買力で仕入れ価格を抑制し、自社開発の配膳ロボット導入やセルフサービス化で人件費も削減。結果として平均客単価を1,200円超に据えながら、利益率を20%前後に維持しています。一方、個人店は食材の共同仕入れや効率化投資が難しく、チェーンと同じ価格設定では利益が出ず、値上げを迫られて客足が遠のく悪循環に陥っています。
4.消費者動向と“1,000円の壁”
消費者調査では、1,000円を超える外食費に抵抗感を持つ層が半数以上とされ、昨年から平均カレーメニュー価格の1,208円への上昇で来店客5.2%減を記録したチェーン例もあります(ココイチ)。個人店がさらに1,300~1,500円台の設定を余儀なくされると、新規客の獲得はほぼ絶望的です。
5.過去の成功例と教訓
一部の個人店は、地域密着型や特色あるメニュー開発で生き残りを図っています。札幌のスープカレー店「マジックスパイス」は地元食材を活用した限定メニューとSNS販促で連日行列を維持。固定費削減のためキッチンカー展開を併用し、食材コストの高騰にも柔軟に対応しています。
6.政府・自治体の支援策
政府は2025年6月、農林水産省主導で備蓄米放出を強化し、5kg袋を2,000円台で小売店へ直販する随意契約方式を実施(36都道府県1,675店舗)。地方自治体も中小飲食店向け補助金や共同物流拠点整備を進めていますが、飲食店全体への迅速な支援にはなお課題が残ります。
7.中長期的な市場構造改革
個人店の生存率を高めるには、以下の改革が必要とされます:
- 食材の共同仕入れ・バルク購入によるコスト削減促進
- サブスク型食事サービスやテイクアウト専用メニュー導入支援
- デジタルマーケティングやEC連携を含む販路拡大支援
- 賃料補助や固定費低減のための家賃補助制度拡充
- 人手不足対策として外国人労働者受け入れ制度の活用支援
まとめ
「なぜカレー店の倒産が続くのか」は、原材料価格高騰というマクロ要因に加え、流通システムやチェーンとの競争構造という業界固有の課題が交錯した結果です。政府・自治体の緊急支援策だけでなく、個人店が自律的にコスト構造を改善し、新たなビジネスモデルを構築するための中長期的な支援体制と市場改革が急務です。


コメント:0 件
まだコメントはありません。