先住民に遺骨返還 東大は差別的
先住民に遺骨返還 東大は差別的
2025/06/12 (木曜日)
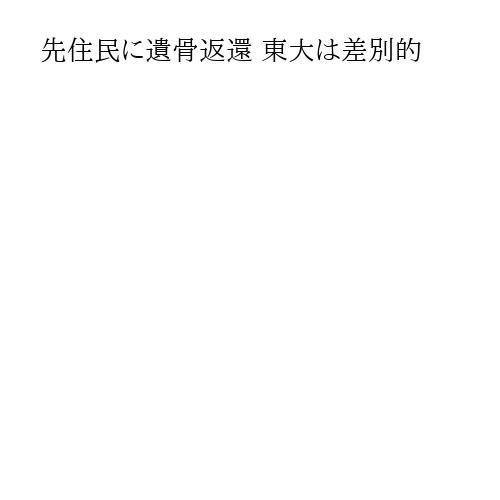
遺骨返還の東大は「最も差別的」 ハワイ先住民が耳を疑った言葉
ハワイ先住民の遺骨
2025年6月11日、毎日新聞は東京大学が昨年11月に米ハワイ先住民の遺骨10体を返還した際、先住民側が大学関係者の「返還は良いが、批判が広がると大問題になる」という発言を「最も差別的」だとして耳を疑ったと報じました。長年にわたる学術収集と保管の歴史が、返還すべき「人の骨」を単なる資料とみなす差別的認識を露呈させたとして、国内外で波紋が広がっています :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
東京大学における遺骨収集の歴史
東京大学医学部人類学教室など複数の研究機関は、明治期以降の礼拝堂改修や国内外の調査を通じて、多数の先住民族遺骨を収集・保管してきました。戦前の帝国型人類学では、人種分類を目的とする「科学主義的蒐集」が盛んであり、遺骨は「学問的対象」として扱われました。戦後も戦争捕虜や戦地調査などで収集された遺骨が学術標本室に保存され、返還運動の萌芽が生まれるまで長期にわたり所在が不明のままとなっていました。
ハワイ先住民への遺骨返還経緯
2023年、ハワイ州政府と先住民団体は、米国議会の「Native American Graves Protection and Repatriation Act(NAGPRA)」に基づき、東京大学など日本の複数大学に保管されていた遺骨の返還を求める書簡を送付。交渉の結果、2024年11月に東京大学はハワイ先住民10体の遺骨を無償で返還しましたが、その場で大学側担当者が「返還は良いことだが、日本で知られると大問題になる」と発言し、先住民らを深く傷つけました :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
「最も差別的」とされた発言の背景
先住民代表は「遺骨は先祖そのものであり、尊厳をもって扱われるべき」と訴えているにも関わらず、大学関係者の言葉は遺骨を資料・在庫管理の一環とみなす態度を象徴していました。ハワイ先住民側は「返還したという体裁を整えるための形式的行為にすぎず、日本の大学が先住民族の人権をまったく理解していない証左だ」と強く非難しています。
国際的な遺骨返還運動と法的枠組み
先住民族の遺骨返還は、国連の「先住民族の権利に関する宣言(UNDRIP)」やNAGPRAなど国際的に保護が進む分野です。特にNAGPRAは、米国内の博物館・大学に対し、遺骨や文化財の出自調査・返還義務を課しており、先住民の合意なく収集された人骨は返還対象となります。日本には同様の包括的立法はなく、各大学や文部科学省によるガイドライン任せの現状が、返還後のフォローアップ不足や倫理基準の不統一を招いています。
国内外の類似事例との比較
台湾大学と馬遠部落(台湾原住民族布農族)の遺骨返還問題では、1960年代に無断収集した64体の骨が2017年以降返還されるまで、原住民側は長年にわたり抗議活動を続けました。その過程で「学術研究の名の下に繰り返された人種差別的取り扱い」が批判され、2024年には台湾大学が公式に謝罪・補償を行いました。欧米では2015年のオーストラリア議会による「先住民遺骨返還法」が制定され、大学や博物館に返還手続きと記録公開を義務付けています。
東京大学の対応と批判
東京大学は「返還は国際的な慣例に従い行った」と説明する一方、当該担当者の発言については「個別の口頭表現であり、大学としての見解ではない」とコメント。先住民側は「言葉尻の問題ではなく、大学組織全体に根深い差別意識がある証拠」として、学長への公開質問状や国内外学会での問題提起を継続しています。
今後の課題と展望
日本の高等教育機関には、遺骨や文化財を「収集→保管→研究」という単一のフローで扱う構造的問題があります。真の和解には、返還だけでなく「共同管理」「先住民族研究者の参画」「教育カリキュラムの見直し」など、制度的・文化的な改革が必要です。また、文科省や外務省による返還ガイドラインの法制化、NGOや先住民団体とのパートナーシップ強化が急務となっています。
結論:真のリコンシリエーション(和解)に向けて
「最も差別的」と指摘された東大の発言は、返還を「儀式的パフォーマンス」にとどめないための警鐘です。学問的優位性を振りかざすのではなく、先住民の視点・価値観を尊重し、歴史的加害の認識を共有することが、真の意味でのリコンシリエーション(和解)につながります。日本の教育機関が国際的なスタンダードに追いつくためには、返還後の対応を含む包括的な「倫理的再生プログラム」が求められています。


コメント:0 件
まだコメントはありません。