2024年の児童虐待死 前年の約2倍
2024年の児童虐待死 前年の約2倍
2025/06/05 (木曜日)
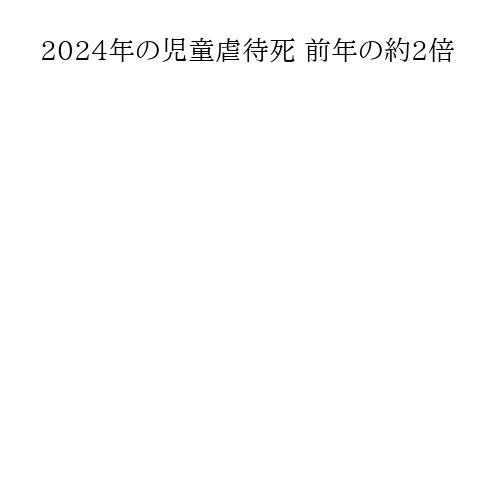
国内ニュース
【速報】2024年児童虐待で死亡した児童は前年比約2倍に 加害者の46%は「実父」 事件発覚のきっかけは児相からの通報が最多 警察庁
検挙件数が過去最多となった去年の児童虐待事件で死亡した児童が全国で52人に上り、前の年からおよそ2倍に増えたことがわかりました。児童が被害にあった傷害や不同意性交等での検挙も過去最多となっています。
警察庁によりますと、去年1年間の18歳未満に対する児童虐待の検挙は2649件に上り、前の年から264件増え過去最多となっています。
虐待の内訳では、育児怠慢や心理的虐待が減った一方で、性的虐待や身体的虐待が増えています。最も多かったのは「傷害」の1029件で、「暴行」は984件でした。「不同意性交等」は162件に上り、「不同意わいせつ」も228件でいずれも過去最多となりました。
また、虐待により死亡した児童は全国で52人に上り、そのうち無理心中は24人、出産直後に殺害されるなどし亡くなったのは9人でした。加害者での46%は「実父」で、「実母」が26%、「養父・継父」も16%を占めています。
事件が発覚したきっかけのうち、児童相談所からの通報によるものは1047件、学校や病院など児童相談所以外の関係機関からの通報によるものは264件で、いずれも増加傾向にあり過去4年で最多となりました。
警察庁は「警察と児童相談所や市区町村との連携が大切。虐待を早期発見することで、被害児童の早期保護につながる」としています。
要約
2024年の児童虐待事件において、検挙件数は2649件と過去最多を記録し、死亡した児童は52人に上りました。前年の約2倍に増加し、特に身体的虐待や性的虐待が増加傾向にあります。死亡した52人のうち、無理心中が24人、出産直後に殺害されたケースが9人を占めました。加害者の46%は実父、26%は実母、16%は養父・継父と、身近な養育者による虐待が多いことが特徴です。発覚のきっかけでは、児童相談所からの通報が1047件、学校や病院など児童相談所以外の機関からの通報が264件と、いずれも過去4年で最多を更新しています。警察庁は、警察と児童相談所など関係機関の連携が早期発見・保護に不可欠だと指摘しています。
1. 児童虐待検挙件数・死亡児童数の推移と内訳
警察庁によると、2024年中に18歳未満の児童に対する虐待で検挙された件数は2649件で、前年から264件増加しました。内訳を見ると、身体的虐待が増加し、「傷害」による検挙は1029件、「暴行」は984件でした。また、性的虐待関連では「不同意性交等」が162件、「不同意わいせつ」が228件と、いずれも過去最多を記録しています。
虐待の結果、死亡した児童は52人に上り、前年の約2倍となりました。死亡原因の内訳では、無理心中が24人、出産直後に殺害されたケースが9人、その他の直接的な暴力や放置などによる死亡が19人を占めています。加害者属性では、実父が46%、実母が26%、養父・継父が16%となっており、身近なつながりを持つ養育者による虐待が多数を占めました。
事件発覚のきっかけとしては、児童相談所からの通報が1047件、学校・病院など児童相談所以外の機関からの通報が264件で、いずれも増加傾向にあることがわかりました。これにより、通報件数の増加とともに検挙件数も過去最多を更新しましたが、死亡事案の増加は社会のセーフティネットの不備を浮き彫りにしています。
2. 児童虐待の背景:社会構造と家庭環境の変化
児童虐待増加の背景には、少子高齢化や核家族化、社会的孤立、経済的貧困などが複合的に影響しています。1990年代後半以降、バブル崩壊後の長期的な経済低迷が続く中で、生活苦からくる家庭内ストレスが増大し、虐待リスクが高まりました。特に共働き世帯の増加により保育所不足など社会的支援が追いつかず、孤立した育児環境が広がり、虐待につながるケースが多く見られます。
また、SNSやインターネットにより育児情報はあふれるものの、相談相手がいないまま精神的に追い詰められやすい状況が生じています。特に非正規雇用の増加により経済的に不安定な家庭では、育児の負担が一人の親に集中しやすく、虐待リスクが高まります。さらに、核家族化が進行する中で祖父母や地域の見守りが希薄化し、外部の目が届かない家庭内で虐待が継続される傾向があります。
3. 法整備と行政の取り組みの歴史
日本では1990年に児童虐待防止推進法が制定され、2000年に児童虐待防止法が成立しました。これにより、医師や保健師、教員などの特定職種に虐待通報義務が課され、通報からの迅速な対応が求められました。2004年の改正児童福祉法では、児童相談所が一次対応窓口と位置づけられ、速やかな家庭訪問や一時保護が可能となりました。
2008年には通報体制の強化や専門職員の育成が進み、児童相談所と警察が連携して虐待対応を行うケース会議が導入されました。2019年の改正では通報対象年齢が明確化され、通報義務者が拡大されました。しかし、これらの制度強化はあったものの、地方自治体の人員・予算が不足しているため、対応体制は十分とは言えず、通報から保護までに時間を要する事例が後を絶ちません。
4. 現在の課題:通報・保護体制の限界
通報件数は増加しているものの、虐待事案すべてに迅速かつ適切に対応できるわけではありません。専門職員の人手不足や財源不足、各自治体間の対応能力の格差が問題であり、通報後に家庭訪問や保護が必要と判断されても、十分なタイミングで手が差し伸べられないケースがあります。
また、通報後に一時保護が行われる割合は全体の約3割にとどまり、残りの約7割は「家庭での支援や見守り」とされています。家庭環境の改善が見込めない場合でも一時保護が見送られるケースや、周囲の支援が不十分で深刻化するケースもあり、死亡に至るまで虐待が継続する悲劇が発生しています。警察と児童相談所や自治体の連携は進められているものの、連携の実行力や情報共有の仕組みが不十分であるため、早期発見・保護の両面で課題が残っています。
5. 法改正のポイントと家庭でできる育児の工夫
2024年4月、児童虐待防止法および児童福祉法が改正され、「体罰禁止」が明文化されました。保護者等による子どもへの身体的な罰は一切認められず、もし行われた場合には虐待とみなされ、通報や処分対象となることがはっきり規定されました。しかし、改正後の調査では、保護者のわずか2割程度しかこの規定を認知していないことがわかっており、啓発活動不足が課題です。
家庭での虐待予防や子育ての工夫として、以下のポイントが有効です。
- 感情コントロールを習慣化する
叱る際に深呼吸をする、10秒数えてから話しかけるなど、イライラしたときに落ち着く方法を身につける。 - ポジティブな言葉がけを心がける
「ダメ!」だけでなく、「こうするともっとよくなるよ」「ありがとう」という前向きな声かけで、子どもの自己肯定感を育む。 - サポートネットワークを構築する
ママ友や地域の子育てサロン、自治体の相談窓口など、相談できる相手や場を複数持つことで孤立感を軽減する。 - 生活リズムを整える
毎日の食事、睡眠、遊びの時間を決めておくことで親子ともにストレスを減らし、安心感を育む。 - 育児情報を適切に収集する
育児書や自治体主催の講座、信頼できるウェブサイトなどを活用して最新情報を取り入れ、子育て観をアップデートする。 - 相談先を事前に把握する
児童相談所、子ども家庭支援センター、保健センター、子育て支援センターの連絡先を確認し、問題が起きたときにすぐ相談できるよう準備する。 - 夫婦・家族で協力する
育児や家事の分担を明確にし、ストレスがたまった場合には役割を交代し合う体制を整える。
これらの工夫は、虐待そのものを防ぐだけでなく、子どもが安心して成長できる家庭環境を整えることにつながります。特に一人で子育てを抱え込まないよう、周囲に早めに助けを求めることが重要です。
6. 地域社会と学校の役割
児童虐待の早期発見・防止には、地域社会や学校の協力が不可欠です。具体的な取り組みとしては以下が挙げられます。
- 子育てサロンや親子の広場の整備
地域の公民館や子育て支援センターで、乳幼児と保護者が交流できる場を提供し、育児の悩みを共有しやすいネットワークを築く。 - スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの配置
小中学校に専門スタッフを配置し、児童や保護者、教員の相談に乗りながら、家庭環境の変化を早期に察知し、必要に応じて児童相談所や医療機関と連携する。 - 見守りボランティアや民生委員の育成・研修
地域住民が子育て家庭の異変に気づけるよう、見守りボランティアや民生委員・児童委員などの研修を強化し、早期介入の体制を整備する。 - 一時預かりやファミリーホームの拡充
病気や仕事などで育児が困難になった家庭の子どもを預かる制度を整備し、里親制度の周知を進めて家庭外での養育環境を多様化する。
これらの仕組みを通じて、地域全体で子どもを見守り、虐待リスクが高い場合には速やかに関係機関と連携して支援を行うことが必要です。学校や保育所は日常的に子どもと接しているため、小さな変化を察知しやすく、「見守りの目」として重要な役割を果たします。
7. 国際比較:日本と諸外国の児童虐待対策
日本の児童虐待対策は法整備が進んできた一方で、諸外国と比較するとまだ課題が多いと言えます。欧米諸国では1980年代から家庭内虐待撲滅を目的にした法整備が行われてきました。たとえばスウェーデンは1979年に体罰禁止法を施行し、子どもの権利を積極的に保護しています。英国や米国の一部州でも、虐待リスク評価ツールを用いて早期介入を行い、専門職が家庭訪問や支援プログラムを提供する仕組みが整っています。
日本では2024年に体罰禁止が法文上明文化されましたが、欧米と比較すると遅れており、制度の実効性を高めるためには更なる取組みが求められます。特に、里親制度や社会的養護の利用促進が不十分であり、児童相談所の一時保護から後のフォローアップが十分でないという課題があります。国際的には「子どもの最善の利益」を中心に据え、多機関連携で支援を行うモデルが注目されており、日本も同様の視点を強化する必要があります。
8. まとめと今後の課題
児童虐待の検挙件数と死亡児童数の急増は、子どもを取り巻くリスクの深刻化を示しています。少子化や社会的孤立、貧困などが複合し、家庭内で虐待が見過ごされるケースが増えています。法改正により体罰禁止が明文化されたものの、保護者への周知や地域・学校との連携はまだ不足しており、制度の運用強化が急務です。
今後取り組むべき課題は以下の通りです。
- 通報・保護体制の強化
児童相談所や警察の人員・予算を増やし、通報から一時保護までのプロセスを迅速化する。特に地方自治体のリソース格差を是正し、全国的に均質な支援が行われる仕組みを構築する。 - 家庭内支援の充実
育児ストレスを軽減するための育児サポートや相談窓口の周知を徹底し、子育てに困ったときに気軽に相談できるネットワークを整備する。 - 地域社会と学校の連携強化
見守りボランティアやスクールソーシャルワーカーの配置を拡充し、日常的に子どもを見守る体制を強化。異変を察知した際には迅速に児童相談所や警察と情報を共有し、早期介入を行う。 - 社会的養護と里親制度の利用促進
里親やファミリーホームなど、家庭外の養育環境を拡充し、保護が必要な児童に適切なケアを提供できる多様な選択肢を整備する。 - 啓発活動と教育の強化
体罰禁止や児童虐待防止法の内容を保護者に広く周知するための教育プログラムやメディアキャンペーンを展開し、虐待が許されない社会的価値観を浸透させる。
児童虐待は社会全体で取り組むべき重大な問題です。子どもの命を守り、健やかな成長を支えるためには、行政だけでなく家庭・学校・地域社会が一体となり、継続的な見守りと支援を行うことが欠かせません。社会的セーフティネットを強化し、子どもを取り巻く環境全体を見直すことで、虐待を未然に防ぎ、一人ひとりの子どもが安心して暮らせる社会を築いていく必要があります。


コメント:0 件
まだコメントはありません。