都議選、政党支持率で好調の参政党 「組織は公明や共産に近い」結党時から知る渡瀬氏
都議選、政党支持率で好調の参政党 「組織は公明や共産に近い」結党時から知る渡瀬氏
2025/06/24 (火曜日)
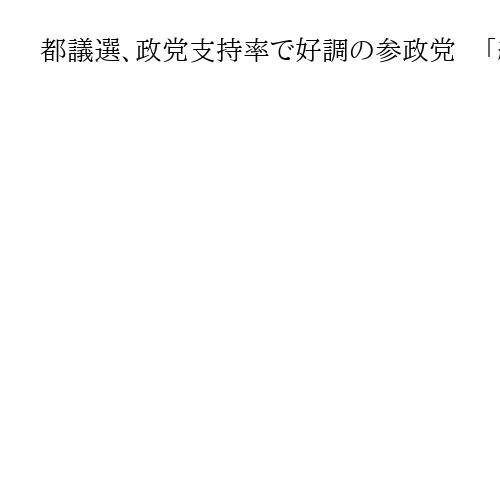
都議選のほかに、参政は今月15日に投開票された兵庫県尼崎市議選(定数42)では公認候補がトップ当選し、永田町には衝撃が走った。
インターネット上の支持の広がりが指摘されるが、渡瀬氏は「参政が議席を伸ばしているのは当然で、既存政党と全く違うからだ」と述べ、むしろ組織の在り方を特色として挙げた。既存政党について「議員中心だ。議員がいて、それを支えるための後援会組織なので『やらされている感』がある。封
背景と概要
2025年6月15日に投開票された兵庫県尼崎市議会議員選挙(定数42)で、政治団体「参政党」の公認候補がトップ当選を果たしました。これを受け、東京都議選に続いて永田町やマスメディアに大きな衝撃が走っています。これまで地方議会では大政党の“地盤・看板・カバン”が強みとされてきましたが、参政党はインターネット上の支持拡大と、従来の党組織とは全く異なる組織運営を強みとして急速に議席を獲得しています。(出典:産経新聞2025年6月24日)
参政党の台頭要因
参政党の躍進は、次のような複数の要因が重なった結果です。
- ネット世論の活用:SNSや動画配信で政策議論をライブ配信し、若年層や無党派層の支持を獲得。
- 「既存政党と違う」鮮烈なブランド:従来の党派色を極力抑え、「市民ファースト」「政治の透明化」を打ち出し、“政治を志す市民”としてのイメージを強調。
- 草の根型組織:地域ごとに自由な後援会を公認せず、ボランティア主体の支部を多数展開し、動員よりも共感を重視。
- 候補者の多様性:異業種出身や若手を積極的に擁立し、「肩書よりも政策論争」が評価された。
既存政党との比較
従来の大政党(自民、公明、立憲など)は「議員中心の後援会組織」であり、候補者と地元後援会が長年築いてきた関係性を重視します。その結果、組織を動かすには時間とコストがかかり、有権者への訴求も画一化しがちでした。一方、参政党は「党組織が候補者を支える」のではなく、「有権者が候補者を支える」という双方向のコミュニケーションを実現。これにより「やらされている感」がなく、「自分事」として選挙に参加する動機付けが強まりました。
地方議会選挙における新潮流
近年、全国の地方選挙で以下のような現象が散見されます。
- 無党派層の増加:若年層を中心に政党支持が流動化し、従来型後援会による組織票の効力が低下。
- 市民参加型プラットフォーム:「オープンリスト」「クラウドファンディング」を活用した資金調達と支持獲得。
- オンライン討論の普及:「候補者×有権者」の公開討論会がSNSで話題となり、政策判断材料が多様化。
尼崎市でも市民有志が参政党候補とのオンライン対話を主催し、政策議論を日常化した点が高く評価されました。
地域政党の歴史的背景
日本の地域政党は1990年代以降、自治体設置議会や広域行政への直接的な影響力を求めて生まれました。有名な例としては、「大阪維新の会」「都民ファーストの会」などが挙げられます。これらは当初、既成政党の政策を地方基盤で再解釈し、独自政策を掲げて急成長しました。しかし、組織運営の中央集権化が進むと失速する例も少なくありません。参政党はその反省点を踏まえ、「分権型」「双方向のネットワーク運営」を徹底しており、成長期の地域政党としては新しいモデルケースといえます。
インターネットと政治動員の融合
デジタル革命は政治にも大きな変革をもたらしました。米国大統領選ではデジタル広告が投票行動に影響を与えたと言われますが、日本の地方選挙でも同様の動きが加速。参政党は:
- 政策説明会をYouTubeで生配信
- LINE公式アカウントで有権者と双方向対話
- 投票依頼をスマートフォンアプリで送信
といった取り組みを行い、「いつでも」「どこでも」政治参加のハードルを下げています。
今後の展望と課題
参政党の躍進には期待が集まりますが、安定的な議員活動と継続的な政策実現には以下の課題があります。
- 政策の具体化:インターネット討論は盛り上がる一方、制度設計や財政調整などの「泥臭い」作業の経験蓄積が必要。
- 党内意思決定プロセス:分散型組織が意思決定の遅滞を生まないよう、明確な規約と役割分担の整備が求められる。
- 既存議会との協調:急成長の反動で孤立しないために、異なる政党議員や行政との協働スキーム構築が不可欠。
まとめ
尼崎市議選でのトップ当選を契機に、参政党は従来政党とは一線を画す新たな政治モデルを示しました。ネット世論の力と、市民ボランティアによる草の根組織の融合が生み出す“参画する政治”の可能性は、今後の地方政治に大きなインパクトを与えるでしょう。永田町をはじめ全国の既成勢力にとっては、参政党の挑戦が“改革の好機”とも映ります。政策立案と実行力をいかに両立させるかが、これからの成長の鍵となるはずです。


コメント:0 件
まだコメントはありません。