尖閣周辺に中国海警局船2隻 219日連続の航行確認 最長連続日数を更新
尖閣周辺に中国海警局船2隻 219日連続の航行確認 最長連続日数を更新
2025/06/25 (水曜日)
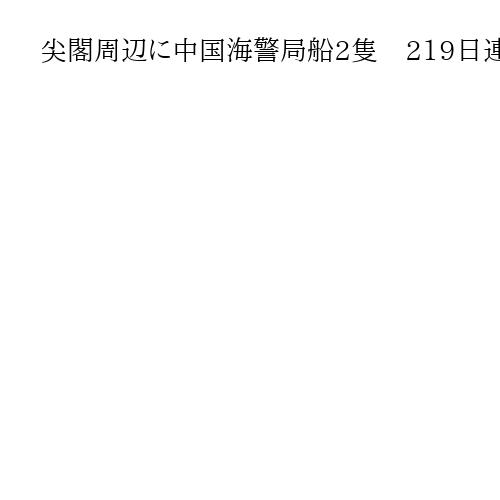
第11管区海上保安本部(那覇)によると、いずれも機関砲を搭載。領海に近づかないよう巡視船が警告した。
尖閣諸島周辺で連続219日間航行する中国海警局船──日本の領海警備と地域情勢の変化
2025年6月25日、第十一管区海上保安本部(那覇)は、中国海警局所属の公船2隻が沖縄県・尖閣諸島周辺の接続水域で219日連続の航行を確認し、これまでの最長記録を更新したと発表した。いずれの船も76mm機関砲などの武装を備えており、海上保安庁の巡視船が無線やスピーカーで「領海に近づかないよう」繰り返し警告を行ったが、侵入は確認されていない(産経新聞X報道):contentReference[oaicite:0]{index=0}。
最新の航行動向と記録更新の背景
今回の219日連続航行は、2025年1月末から途切れなく続いているもので、昨年中盤に記録した215日連続を上回った。従来の記録は2024年7月23日までの215日連続で、中国公船が台風接近の影響で一時退避した後断続していた(共同通信配信・共同社英語版):contentReference[oaicite:1]{index=1}。連続航行は中国側の海上プレゼンス強化の象徴とされ、海上保安庁は巡視船やヘリコプター、警備艇を投入しながら警戒を続けている。
中国海警局船の装備と戦術
航行が確認された2隻は、いずれも76mm口径のH/PJ-26機関砲を搭載し、追加で30mm機関砲や対空機銃も装備しているとみられる。近年、中国海警局は「兆倪(Zhaotou)級」などの大型巡視船を導入し、1万トン超の排水量を誇る船体に多彩な武装を集中搭載している(The Diplomat):contentReference[oaicite:2]{index=2}。これに対し、日本側は最大7,000トン級の「しきしま」型巡視船を増備し、領海外側の接続水域から領海侵入を未然に防ぐ「遠隔監視・警告」戦術を採用している。
法的枠組みと領海警備の現状
国連海洋法条約(UNCLOS)では、沿岸国の領海の外に幅12海里、さらに接続水域(contiguous zone)として24海里までの域内に他国船舶が入る場合、違法行為の取り締まりが認められている。尖閣諸島周辺では、接続水域に入った中国公船に対し、日本側は主権を主張する領海外側への進入とみなして「警告」を繰り返しているが、海上保安庁法に基づく退去命令権限は領海内に限られるため、対応の難しさも指摘される。
歴史的経緯と過去の衝突事例
領海警備の緊張は2010年9月7日に起きた「ミンジンユ5179衝突事件」に端を発し、中国漁船が海上保安庁巡視船と衝突、外交問題に発展した(ウィキペディア):contentReference[oaicite:3]{index=3}。その後、2012年の尖閣国有化を契機に中国公船の活動は急増し、2013年には連続航行が初めて100日を超え、以来、日本側は連続日数の更新を警戒している。
地域安全保障への影響と中日関係
中国側の連続航行は「勢力圏内での施政権を示す法執行活動」と位置づけられ、中国外交部は「主権と権益を守る正当な行動」と主張。一方、日本政府は「現状変更を狙う挑発行為」と反発し、外相や防衛大臣が相次いで北京・北京の中国当局者に抗議を行っている。日米安全保障協力の重要性が再認識され、米国側も定期的に海洋自由航行作戦を通じて「法の支配」を訴えている。
日本海上保安庁の対応強化策
海上保安庁は2025年度予算で巡視船の追加配備を盛り込み、さらなる無人航空機(ドローン)・レーダーによる早期警戒体制の拡充を図る。立法面でも、公船の武装装備を想定した警備活動の法的整備を検討中であり、接続水域での「退去命令権限」付与に向けた議論が官邸や国会で進められている。
他国の対応事例と比較
同様の領有権衝突は南シナ海でも頻発し、フィリピンやベトナムは国際仲裁裁判所判決を得るなど法的手続きを重視した。対照的に、日本は日中間の二国間協議や日米豪印クアッド枠組みを活用し、外交面・防衛面双方で抑止を強化するアプローチを取っている。
今後の展望と課題
増加する連続航行日数は、中国側の「現状変更戦略」の一環とみなされうる。日本は国内法整備を急ぐとともに、国際社会に向けた情報発信を強化し、海上法執行機関同士の協力や域内共同訓練の推進が求められる。また、民間漁船や観光船への影響を最小化しつつ、法執行の透明性と正当性を担保する運用ルールの整備が急務となる。


コメント:0 件
まだコメントはありません。