「骨太方針」実質賃金1%上げ目標
「骨太方針」実質賃金1%上げ目標
2025/06/07 (土曜日)
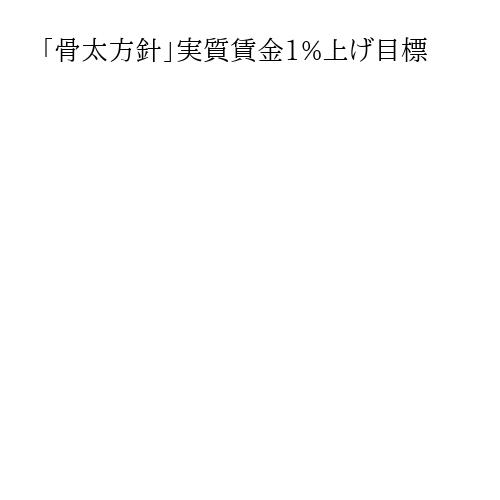
国内ニュース
石破内閣初の「骨太の方針」、実質賃金1%上げ目標…水田政策の見直しや米関税政策対策も
政府は6日、今後の重要政策の方向性を示す「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」の原案を経済財政諮問会議(議長・石破首相)に示した。「賃上げを起点とした成長型経済」の実現や、米国の関税措置で不透明感が漂う国内景気対策に取り組むほか、米価の高騰対策も盛り込んだ。
石破内閣による骨太の方針の策定は初めて。「国民所得と経済全体の生産性向上」を掲げ、持続的、安定的な物価上昇の下で年1%程度の実質賃金の上昇を目指すと打ち出した。米国の関税措置に伴い輸出の減少や消費、投資が下押しされる懸念があると指摘する一方、中国が貿易などを通じ、相手国に「経済的な威圧」を加えているとの懸念に言及した。
政府が2026年度の設置を目指す防災庁では、専任閣僚を置く方針を明記した。農業政策では「水田政策の見直しの具体化」を掲げて、事実上の減反政策となっている生産調整の見直しを示唆した。
この日は、新しい資本主義実現会議(議長・石破首相)も開かれ、成長戦略「新しい資本主義の実行計画」の改定案が示された。骨太の方針の原案とともに、与党との調整を経て13日にも閣議決定する。
要約
2025年6月6日、石破内閣は今後の重要政策の指針となる「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」原案を経済財政諮問会議に示した。成長の起点に賃上げを据え、実質賃金を年1%上昇させる「賃上げを起点とした成長型経済」を掲げるとともに、米国の新たな関税措置など海外リスクに備えた国内景気対策、2026年度設置を目指す防災庁の専任閣僚配置、生産調整見直しによる水田政策改革や米価高騰対策などを盛り込んだ。また同日開かれた「新しい資本主義実現会議」では、成長戦略「新しい資本主義の実行計画」の改定案も併せて示され、13日の閣議決定を目指す。
1. 「骨太の方針」の歴史的意義と位置付け
「骨太の方針」は、2001年の小泉改革期に創設された「経済財政諮問会議」で毎年取りまとめられる国家運営の基本方針で、財政健全化と経済成長の両立を目指す政策パッケージとして定着してきた。菅政権下の2020年度にはコロナ対策を重視し、岸田政権では「新しい資本主義」を重層化した策定が行われた。本年は石破首相体制下で初の策定となり、従来の財政構造改革に加え、賃上げ・分配政策に重点を置いた点で特徴的である。
2. 賃上げを起点に据えた「成長型経済」モデル
原案では「実質賃金を年1%上昇させる」目標を明記し、企業の賃上げを促すための税制優遇や補助金を拡充する方針を示した。具体的には、賃上げを実施した中小企業への法人税減税や交付金交付を強化し、賃上げと生産性向上を同時に実現する「人的投資拡大プログラム」の創設を検討する。また公務員などの待遇改善や最低賃金引き上げの加速度的推進を打ち出し、個人消費拡大と内需主導の成長循環を目指す。
3. 米国関税措置への対応と国内景気対策
米国が一律10%の相互関税を再適用する可能性が高まる中、原案は「輸出の下押し」「国内投資・消費の減速リスク」を指摘。鉄鋼・自動車など重点産業への緊急支援策として、輸出保険の補強や国内調達拡大支援、関税分相当の上乗せ補助金を検討する。また、需要家支援として「エネルギー価格変動調整基金」を創設し、電力・ガス料金高騰を一時的に抑制しつつ、再生可能エネルギーへの転換補助も強化する方針を示した。
4. 米価高騰対策と農政改革
食料品の中でも米価は全国的な高騰が鮮明化しており、原案では「政府備蓄米の段階的放出」を再確認。併せて米価安定のため、水田政策の見直しを明示し、事実上の減反政策である生産調整を段階的廃止し、生産者の需給調整を市場メカニズムに委ねる方向を示唆した。また、スマート農業・IoT農機導入支援や、JA改革を通じた流通の効率化によりコスト低減を図り、消費者価格抑制と農家所得安定を両立させる方針が盛り込まれている。
5. 防災庁設置と専任閣僚の配置
原案では2026年度中の防災庁設置に向けて専任閣僚を置く「防災大臣」ポストを明記。従来の内閣府・気象庁・消防庁の縦割りを解消し、気候変動対応や災害リスク管理の司令塔機能を強化する。国内外を問わず激甚化・頻発化する自然災害に迅速対応するため、平時の防災投資拡大だけでなく、AI・衛星データを活用した次世代監視・予兆システム構築も掲げる。
6. 「新しい資本主義の実行計画」改定案のポイント
同日開催の新しい資本主義実現会議では、2021年策定の実行計画を改定し、脱炭素投資やデジタル化投資に対する国家投資枠を拡大。2050年カーボンニュートラル達成に向け、グリーンイノベーション基金を倍増し、民間投資の呼び水とする。スタートアップ支援策では、大学発ベンチャーの資金調達環境整備や、特許使用料負担軽減制度を導入し、知財立国戦略を強化する。さらにSociety5.0実現に向け、分散型AI・量子コンピューティング研究に対する国家プロジェクトを創設する。
7. 政策決定のプロセスと今後のスケジュール
原案は与党・関係省庁の調整を経て、6月13日の閣議決定を目指す。その後、国会提出資料としてまとめられ、衆参両院での論戦材料となる。各省は原案に基づく詳細な実施計画を夏までに策定し、2026年度予算編成に反映させる。与党内では、特に賃上げ税制優遇措置の恒久化や新規歳出の財源確保策が焦点となり、議論が活発化する見込みである。
8. 背景要因と国内外の環境変化
世界経済は米中対立や金融引き締め、コロナ後のサプライチェーン再編などで不確実性が高まっている。日本経済も長期的なデフレ脱却が道半ばで、賃金上昇と生産性向上の好循環確立が喫緊の課題である。また、少子高齢化による労働力不足や地域格差の拡大も深刻化し、従来の投資誘導策だけでは対応困難な局面を迎えている。こうした内外環境を踏まえ、「賃上げ起点」「脱炭素」「デジタル化」「防災強化」を柱に据えた原案は、日本経済の耐性・成長力を同時に高める狙いがある。
9. 主な評価と課題
賃上げと分配重視の方針は企業・労働界から一定の理解を得る一方、財源確保策や規制改革の具体性が薄いとの指摘もある。農政改革では生産者団体から戸別所得補償制度の継続要望が強く、水田政策見直しの合意形成が課題となる。また、防災庁設置には予算拡大と既存組織との権限調整が必要で、実務立ち上げに時間を要する見込みである。与党は今後、これらの調整を進めつつ、地方自治体や産業界との連携を強化し、現場に即した実効性ある制度設計を急ぐ必要がある。
10. まとめと今後の展望
石破内閣の初となる「骨太の方針」原案は、「賃上げ起点の成長」「脱炭素・デジタル化投資」「防災体制強化」「農政改革」を横断的に組み合わせた全体像を示した。国内外の不確実性が増す中、年1%の実質賃上げを達成し、好循環を定着させるかが最大のカギである。今後の与党・省庁間調整を経て、13日の閣議決定後、2026年度予算・立法に反映される予定だ。実効性をいかに担保し、国民生活実感につなげるかが政策遂行の成否を左右するだろう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。