「このままでは日本が壊れてしまう」北村晴男弁護士が日本保守党からの参院選出馬を表明
「このままでは日本が壊れてしまう」北村晴男弁護士が日本保守党からの参院選出馬を表明
2025/06/30 (月曜日)
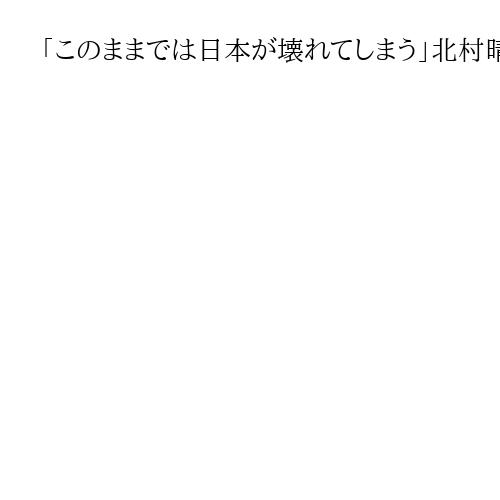
「ありがたいことに選挙に出ないかと誘ってもらったことは少なからずあったが、これまでは一度も出ようと思ったことはなかった」とも語り、詳しい立候補の理由については、7月1日の日本保守党の記者会見などで説明するとした。
北村氏は昭和31年生まれ。早大卒。日本テレビ系の人気番組「行列のできる相談所」などテレビでも活躍した。選択的夫婦別姓制度の導入に反対するなど、保守的な論客としても知られる。
「このままでは日本が壊れてしまう」北村晴男弁護士、日本保守党から参院選比例代表に出馬表明
弁護士の北村晴男氏(69)は6月30日、自身のYouTubeチャンネルで、7月3日公示・20日投開票の参議院選挙に日本保守党(百田尚樹代表)の比例代表候補として立候補することを明らかにした。急きょ決断した理由について「このままでは日本が壊れてしまうという思いが最大の理由」と述べた。
北村晴男氏の歩みと政治参画の動機
北村氏は大学卒業後に司法試験に合格し、30年以上にわたって憲法・人権問題を専門に活動。重い人権侵害事件を数多く手がけ、弁護士会内では「公正な法運用と市民の権利擁護」を掲げてきた。2023年には弁護士団体の政治的中立性に疑問を呈し、日弁連の偏った動きを批判。これまで複数の政党から立候補の誘いは受けていたが、「政治の世界に足を踏み入れる覚悟がつかなかった」と振り返る。だが昨今の社会・経済・安全保障をめぐる危機感から「専門家として政策論争に加わる必要性を痛感した」と語った。
日本保守党とは何か
日本保守党(保守新党改称後のConservative Party of Japan)は2023年に作家・百田尚樹氏らによって設立された右派政党。保守主義を標榜し、「少子高齢化対策」「自国文化の擁護」「外交・安全保障の強化」を掲げる。移民規制や伝統文化重視、憲法改正を訴え、インターネットやSNSを通じた若年層への情報発信に強みを持つ。党勢拡大のカギとして、著名人を比例代表に擁立し、既成政党に対する「受け皿」を目指している。
参院選における少数政党の躍進潮流
近年の参議院選では、与野党の二大政党に対抗する“第三極”が支持を伸ばしている。都民ファーストの会や参政党、日本保守党などが比例代表で議席を獲得し、国政の構図を複雑化させた。特に参政党は2022年に比例で初議席を獲得し、今回も注目を集める。北村氏の擁立は、日本保守党が保守層の分断票を結集し、自民党の「岩盤保守」を揺さぶる戦略の一環とみられる。
北村氏の政策提言の方向性
- 憲法改正と国防強化:自衛隊の役割明確化と抑止力強化を訴え、憲法9条見直しに理解を示す。
- 少子化対策と家族支援:子育て支援の拡充、女性就労環境の整備、産休・育休制度の実効改善。
- 地方創生と農林水産業振興:地方自治体への権限移譲や地場産品ブランド化支援を提唱。
- 規制改革と行政透明化:行政手続きの簡素化、公務員制度改革、情報公開の拡充。
- 司法制度の見直し:裁判員制度や刑事司法への国民参加拡大、公選法改正による選挙制度改革。
競合政党との比較
比較のため、同じく比例代表に注力する参政党(神谷宗幣代表)は、教育改革や反グローバリズムを掲げ、ワクチン政策批判などで保守層の不満票を取り込む。日本保守党は歴史認識問題や移民政策の是正に重きを置き、思想的にはやや排他的傾向が強い。北村氏はこれまで法律顧問として両党の政策策定に関わってきたが、今回の出馬により、より実践的な政策実行力を訴える狙いがある。
政治参加の新たなステージとして
北村氏は「専門家として法の番人だけでなく、政策立案者としての役割を果たしたい」と表明。弁護士経験を生かし、法令整備の観点から立法府での提言を目指す。高齢化や安全保障の危機が深刻化する中、専門知識を持つ市民が政治参画する流れは今後も加速しそうだ。
まとめ
北村晴男氏の日本保守党からの参院選比例代表出馬表明は、既成政党への不満や保守層の分断を背景に、専門家が政治の最前線に立つひとつの象徴と言える。氏が掲げる「日本が壊れる」という強い危機感は、少子高齢化、国防不安、地方衰退など現代日本が直面する課題と直結する。今後の選挙戦では、ネット戦略に加え、地方の有権者への直接訴求が鍵となるだろう。政治経験に乏しい北村氏が、法律家としての信頼性をどう票に結び付けるかが注目される。比例代表での獲得議席は、日本保守党の政策訴求力のバロメーターともなりうる。いずれにせよ、国政に専門家の声をより反映させる試みとして、次代の政治参加モデルを示す可能性がある。


コメント:0 件
まだコメントはありません。