生活保護減額3千億円規模か 試算
生活保護減額3千億円規模か 試算
2025/06/02 (月曜日)
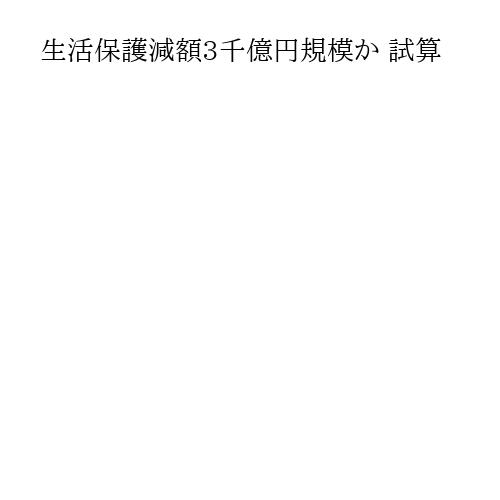
生活保護減額、3千億円規模か 13~18年、時事通信試算 違法訴訟、27日最高裁判決
国が2013~15年に3回実施した生活保護基準額の引き下げによる減額の総額が、18年までの約5年間で計3000億円規模になることが1日、時事通信の試算で分かった。
各地の受給者が減額処分取り消しなどを求めた訴訟では、判断が分かれた大阪、名古屋各高裁の2件について最高裁が27日に判決を言い渡す。原告が勝訴すれば、国は減額分の返還を求められる可能性がある。
厚生労働省によると、引き下げの影響期間は13年8月~18年9月。この間、受給者数は約209万~約216万人で推移した。
同省の資料では、最初の引き下げによる13年度の財政効果は約150億円、2回目の14年度はさらに260億円、15年度も260億円と見積もった。これにより13~15年度の各減額幅は予算ベースで150億円、410億円、670億円となった。
厚労省は16年度以降の見積もりを作成していないが、受給者数に大きな変化も見られないことなどから、15年度と同規模の減額が続いたとみられる。18年度は10月に新たな基準額改定が実施されたため、同年度の減額幅を670億円の半額に当たる335億円として試算したところ、減額は総額計2900億円余りとなった。
試算について、厚労省の担当者は「厚労省の出した数字ではないが、間違いだとも言えない」と話している。
大阪訴訟の原告側代理人を務める小久保哲郎弁護士は最高裁で勝訴した場合について、「国は全ての受給者に謝罪し、引き下げ前の基準に基づき未払い分を支給するべきだ」としている。
生活保護基準引き下げによる減額規模と法的問題
2025年6月1日に時事通信が試算を発表したところによると、国が2013~2015年にかけて3度実施した生活保護基準額の引き下げによる減額総額は、2018年までの約5年間で約3,000億円に達する見込みです。各年度ごとの減額効果を厚生労働省の資料から整理すると、以下のようになります。
- 2013年度(第1回引き下げ):減額財政効果約150億円
- 2014年度(第2回引き下げ):累計減額約410億円(前年度150億円+新たな引き下げ260億円)
- 2015年度(第3回引き下げ):累計減額約670億円(前年度410億円+新たな引き下げ260億円)
- 2016~2017年度:受給者数に大きな変動がないことから、2015年度と同規模の減額が継続したと推測される
- 2018年度:10月に新基準額改定が行われたため、減額幅は2015年度の半額相当と仮定し約335億円と試算
これらを合計すると、2013年8月から2018年9月までの減額効果はおよそ2,900億円余りに上り、四捨五入して約3,000億円規模になると報じられました。厚労省担当者は「厚労省が公表した数字ではないが、大きく外れた試算とも言えない」と述べています。
訴訟の経緯:減額処分取り消しを求める裁判
生活保護基準の一方的な引き下げに対し、各地の受給者らは減額処分の取消しや未払い分の返還を求めて裁判を提起しました。特に注目を集めているのは大阪高裁・名古屋高裁で争われた2件の訴訟で、いずれも原告側が「引き下げ前の生活保護基準に戻すべきだ」と主張しています。
両高裁の判断は分かれており、大阪高裁では「国の裁量に合理性があった」として請求を退けた一方、名古屋高裁では「受給者の生活保障権が侵害された余地がある」として一部棄却・一部認容の判断を下しました。最高裁は2025年6月27日に両件について判決を言い渡す予定であり、原告側が勝訴すれば国は減額分の返還を求められる可能性があります。
減額の背景と政府の説明
2013年から2015年にかけて、国は「生活保護基準を社会保障費の抑制と自立支援の観点から見直す」ことを理由に3回にわたって基準額を引き下げました。これにより受給者の収入保障額が削減され、たとえば単身世帯で月1万円前後、家族世帯で数万円の減額となりました。
厚生労働省は「雇用情勢の改善や物価変動に応じて、基準を適切に見直す必要があった」と説明してきましたが、受給者側や支援団体からは「生活費や医療費が増加している中での引き下げは、最低限度の生活保障を損なう」と強く反発されました。特に、地方自治体ごとに物価や地価の違いが大きいにもかかわらず一律の引き下げを行ったため、住居費や光熱費の負担が相対的に重い地域の受給者ほど深刻な影響を受けたと指摘されます。
裁判での論点:違憲性と裁量権の範囲
訴訟では主に以下の論点が争われています。
- 憲法上の生存権(第25条)の侵害:
引き下げによって受給者が「最低限度の生活」を営む権利が奪われたかどうか。 - 裁量権の逸脱・濫用:
政府が基準改定の判断過程で必要な調査や議論を十分に行ったか、裁量権を逸脱していないか。 - 生活保護法の解釈:
同法に定められた「最低生活費」の算定方法や、改定時の手続き要件を遵守したか。
大阪高裁は「国の裁量範囲内」と判断しましたが、名古屋高裁は「受給者の立証責任が不十分」としながらも一部で違憲性を認める趣旨の判決を示しました。最高裁の判断によっては、国の一律的引き下げ政策が違憲と位置づけられ、減額分の返還や新たな支援策が必要になる可能性があります。
3,000億円問題が示す社会保障政策の課題
生活保護基準の引き下げによって生じた3,000億円規模の節約効果は一見すると財政負担軽減に寄与したように見えます。しかし、長期的には以下のような課題も浮上しています。
- 受給者の生活困窮化:
支出削減を余儀なくされた受給者の中には、医療受診を控えたり、 子どもの教育費を節約したりするケースが散見されます。これが健康悪化や子どもの学習機会の喪失を招き、結果的に社会保障費の増大を招く恐れがあります。 - 地方自治体財政への影響:
国の基準引き下げに伴い、自治体が補足的に生活扶助を行うケースも増えました。地方交付税の財源配分や自治体予算の圧迫が生じ、自治体独自の支援策が打ちにくくなる副次的な問題が指摘されています。 - 社会保障制度全体の信頼低下:
一方的な給付削減が相次ぐことで、受給対象者のみならず、将来の受益を見込む国民からも不安の声が上がります。制度の「安心感」や「公平性」を損ない、社会保障全体への信頼低下を招く懸念があります。
過去の類似事例と教訓
日本ではバブル崩壊後の1990年代、経済停滞を背景に社会福祉費抑制策が断続的に行われました。とくに高齢者向け年金や医療給付、生活扶助の給付水準引き下げがたびたび検討され、そのたびに現場や支援団体から反発が生じました。最終的に年金給付維持や医療費助成の再拡充に至った例もあり、「短期的な財政効果だけを追求すると、将来的にもっと大きなコストや社会的歪みを招く」という教訓が得られています。
私見:バランスの取れた政策運営の必要性
現状、経済状況の厳しさを理由に「やむを得ず生活保護基準を見直す」という判断は理解できます。しかし、その一方で「弱者にさらなる負担を押し付ける形」では、社会全体の持続可能性は担保されません。私の考えとしては、以下のようなポイントを重視すべきです。
- 影響分析と段階的実施:
基準引き下げの前後で受給者の生活実態を詳細に分析し、インパクトが大きい世帯や地域に対してはきめ細かい救済措置を講じる。段階的かつ柔軟な実施時期を設定し、急激な生活悪化を防ぐ。 - 雇用・自立支援策の強化:
生活保護受給者の自立支援を目的に、職業訓練や就労支援を強化する。引き下げによって浮いた財源を、自立促進に活用し、受給者が再就職しやすい環境を整える。 - 自治体・地域福祉との連携:
地方自治体やNPOとの連携を強化し、生活に困窮した家庭への緊急支援や、子どもの学習支援、医療費助成など、地域に応じた支援メニューを整備する。 - 制度への信頼回復:
引き下げ政策の目的や根拠をわかりやすく国民に説明するとともに、受給者の生の声を政策立案に反映させる仕組みを構築する。透明性を高めることで、制度全体への信頼を回復する。
最高裁判決がもたらす今後の展望
2025年6月27日、最高裁が大阪・名古屋両高裁の判断をどう評価するかは今後の大きなポイントです。もし原告が勝訴した場合、国は減額分の返還を余儀なくされるだけでなく、今後の生活保護基準改定において「受給者の同意」や「十分な調査・審議」が求められる可能性が高まります。
一方、国が勝訴した場合でも「減額幅を超えた不当な負担がなかったか」「受給者の生活実態を十分に考慮したか」といった問題が引き続き議論されるでしょう。いずれにしても、社会保障費が膨張する中、「弱者を切り捨てず、持続可能な制度設計をいかに実現するか」が喫緊の課題です。
まとめ
2013~2015年の生活保護基準引き下げによる約3,000億円の減額は、短期的な財政効果として一定の成果を上げたものの、受給者の生活困窮や自治体財政への影響、社会保障制度全体の信頼低下といった深刻な課題も浮き彫りにしました。最高裁判決の結果如何によっては、国は過去の減額分を返還し、今後の制度運営において根本的な見直しを迫られる可能性があります。
今後は「財政効率と受給者の最低限度の生活保障」という二律背反に対し、いかにバランスを取るかが最も重要です。政府・自治体が協力し、受給者が安心して暮らせる生活保障と、国民負担を抑制する財政運営の両立を目指すことが求められます。


コメント:0 件
まだコメントはありません。