回転ずし大手の中国進出・くら寿司全店撤退の背景 はま寿司96店、スシロー91店が先行
回転ずし大手の中国進出・くら寿司全店撤退の背景 はま寿司96店、スシロー91店が先行
2025/07/02 (水曜日)
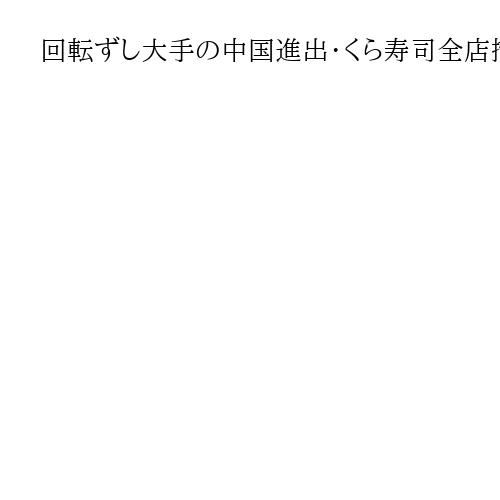
「スタートがうまく切れなかった」。くら寿司の取締役は閉店の要因について、進出直後の23年8月に中国が日本産水産物の輸入を停止したことなどを挙げた。
中国本土の店舗では当初から食材の8割は中国産を使い、現在はすべて中国産だが、風評被害もあり知名度を上げる販促が打てなかった。出ばなをくじかれたことに加え、中国の不動産不況による不景気が追い打ちかけ、思うように客足が伸びなかったという。
くら寿司は当
くら寿司中国全店撤退──進出から2年、なぜ「スタートダッシュ」に失敗したのか
回転寿司大手のくら寿司は2025年7月2日、中国本土の全3店舗を年内をめどに閉店・撤退すると発表した。2023年6月の上海1号店開業からわずか2年での撤退決定は、当初掲げた「10年間で100店舗」という目標から大きく後退する結果となった。
1. 中国進出の背景と経緯
- 海外展開の先駆:くら寿司は2009年に米国に、2014年に台湾に進出し、2025年5月時点で米国76店・台湾59店を運営する国際戦略を展開してきた。
- ゼロコロナ政策終了後の挑戦:2023年6月、約3年ぶりに再開された中国市場で上海に1号店をオープン。同年中に3店舗体制を整えた。
- 野心的な成長プラン:「10年で100店舗」を掲げ、広域展開を目指したが、実際は出店数の横ばいで推移。
2. 撤退の直接要因
くら寿司取締役は閉店決定の理由を大きく三点挙げた:
- 日本産水産物の輸入停止:23年8月、中国が福島処理水放出を理由に日本産水産物を一律禁輸。くら寿司は当初から食材の8割を中国産に切り替えたが、風評被害で「日本ブランド」の訴求が難航し、認知度向上策が打てなかった :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
- 価格競争力の限界:中国店舗では一皿約200~250円(日本の約2倍)に設定。周辺に急増する地元チェーンと比べても高価格が敬遠され、集客が伸び悩んだ。
- 中国不動産不況と消費低迷:23年後半から深刻化した不動産市場の冷え込みで消費者心理が悪化。外食支出を抑える動きが鮮明となり、高コストのくら寿司は影響を受けた :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
3. 競合他社との明暗対比
- スシロー:2021年広州1号店以降、累計30店以上を開設。低価格とSNS映えメニューで現地客を掴み、待ち時間数時間の人気を博す。
- はま寿司:2014年北京進出以来、25店を追加出店し、2025年に100店体制を達成。地元食材との融合メニュー開発と大衆価格帯戦略が奏功。
- 元気寿司:2010年深圳1号店から継続的に出店を重ね、リサイクル樹脂皿導入などコスト削減策を徹底。
4. 中国市場の特異性とリスク管理
中国は人口14億人を擁する世界最大の小売市場だが、以下の要因が日本企業の挑戦を阻む:
- 消費者嗜好の多様化と地元ブランドの強さ
- 規制・検査の厳格化と突発的な輸入禁止リスク
- 急速なデジタル化に伴うO2O戦略の重要性
- 地域ごとの景況感格差と不均一な成長ポテンシャル
5. 今後のくら寿司の海外戦略
くら寿司は中国撤退後、米国市場への再集中を明言。北米では76店体制をさらに拡大し、持ち前の「ビッくらポン!」等の卓上ゲームでファミリー客層を掴む計画だ。また、東南アジアや中東の成熟市場への新規進出も検討するとされる。
まとめ
くら寿司の中国撤退は「出ばなをくじかれた」不運だけではなく、戦略の根幹にある価格・商品・リスク管理のミスマッチが浮き彫りになった結果と言える。日本ブランドの高品質と独自コンテンツは海外でも競争力を持つ一方、現地市場の細分化したニーズや規制リスクを克服するためには、より綿密なローカライズ戦略とリスクヘッジが不可欠だ。中国市場から一時撤退する判断は合理的とも受け止められるが、得られた教訓を活かし、次なる海外戦略を練り直すことが求められている。


コメント:0 件
まだコメントはありません。