万博中国ナショナルデー、何立峰副首相来日へ 自民・森山幹事長、パンダ貸与要請
万博中国ナショナルデー、何立峰副首相来日へ 自民・森山幹事長、パンダ貸与要請
2025/07/06 (日曜日)
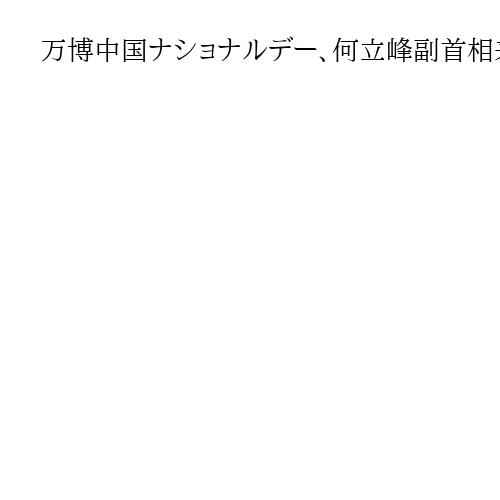
会談で森山氏は、日本で2001年に牛海綿状脳症(BSE)が発生したのを受けて中国が規制する日本産牛肉の輸入再開も働きかける見通し。
関係者によると、日中両政府は日本からの輸出の前提となる関連協定の発効を調整しており、日本の外務省局長が4日、中国側と日本産牛肉を巡り協議した。
国内で飼育するパンダは、和歌山県の4頭が6月下旬、中国に返還され、東京・上野の2頭だけとなった。
中国副首相・何立峰氏来日で浮上する日中牛肉貿易再開とパンダ外交の行方
2025年7月6日、中国の何立峰(かりっぽう)副首相が大阪・関西万博の中国ナショナルデーに合わせ来日する方向で調整されている。日中友好議員連盟会長の森山裕自民党幹事長は、同日大阪で何氏と会談し、①2001年の牛海綿状脳症(BSE)発生以降中国が禁止してきた日本産牛肉の輸入再開の働きかけ②ジャイアントパンダの新規貸与要請──の2点を重ねて要請したと複数の外交筋が明らかにした:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
牛海綿状脳症(BSE)発生から再開交渉へ
2001年9月、日本国内で初のBSE確認が報じられると、米欧をはじめ中国・韓国など多くの国が日本産牛肉に対し輸入規制を実施した。中国は同年末から全面的に禁止し、その後も追加要件として飼養管理証明や検査体制の強化を要求し続けてきた。以降、中国向け輸出はゼロ。日本政府は外務省を中心に二国間協定の策定を急ぎ、2005年のGATT(WTO前身)協議でも議題としたが、合意には至らなかった。
今回、日中両政府は「輸出の前提となる関連協定」の発効を調整しており、外務省局長が7月4日に中国側と協議した。議論の焦点は、衛生植物検疫法に基づく審査項目の見直しと、現地検疫所の認定制度、飼養管理記録の相互承認にある。中国側は「安全性を最優先する」としつつ、国産牛肉のブランド価値を高める好機とも捉えており、秋以降の輸入再開見通しが浮上している:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
パンダ外交の歴史と現状
ジャイアントパンダは20世紀以来、中国が外交カードとして世界各国に貸与してきたシンボル的存在だ。1972年の日中共同声明以降、北京動物園と東京・上野動物園での「シャンシャン」親子公開など、日本でも長年にわたり国民の愛情を集めてきた。しかし、和歌山県・白浜アドベンチャーワールドで飼育されていた4頭は今年6月下旬に中国へ返還され、上野のリーリーとシンシンの2頭だけとなった。貸与期限は2026年2月までであり、タイミングによっては再び「パンダ不在状態」が起こる可能性がある。
森山氏は「大阪万博の舞台で新たに2頭程度のパンダ貸与をお願いしたい」と直接要請するとされる。茨城県や仙台市などが誘致を表明しており、中国側は「地方都市での繁殖プログラム拡大」を掲げる一方、「国際イベントにおけるパンダ展示は両国友好の証」と位置づけている:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
過去の開国交渉と類似事例
これまで日本産食品で輸出禁止から再開に至った例として、2011年の東日本大震災後に発生した福島第一原発事故に伴う水産物輸入規制がある。欧米やアジア各国との二国間合意を経て、2019年までに大多数の規制が解除された。今回の牛肉交渉も同様に「合意形成の段階的進捗」と「相互検査体制の構築」が鍵を握る。
日中経済関係と国内農業への影響
中国は世界最大の牛肉輸入国であり、日本企業にとって巨大市場だ。農林水産省の試算によれば、再開初年度の輸出額は約3千億円規模に達する可能性がある。一方で、国内畜産業界からは「国内需要と価格の安定化」「輸出依存リスクの分散」を求める声が上がり、政府は生産体制の強化支援やトレーサビリティ制度の確立に取り組む方針だ。
展望と今後のステップ
- 二国間協定の条項最終調整:衛生検査・証明書発行プロセスの明文化
- 地方自治体との協力枠組み:誘致希望都市でのパンダ飼育環境整備支援
- 農家向け研修・設備投資助成:輸出品質基準対応のための技術指導
- 国際的なブランド戦略:和牛PRキャンペーンの共同実施
- 友好交流行事:万博後の文化交流イベントでの現地試食・パンダ公開企画
まとめ
2001年のBSE発生以来、24年間停止してきた日本産牛肉の中国向け輸出再開交渉は、関係協定の最終調整段階に入りつつある。再開が実現すれば、農水産業界にとって経済的チャンスとなる一方、品質管理や生産体制の整備が不可欠だ。また、ジャイアントパンダ貸与を通じた「動物外交」は、日中関係のシンボルとして引き続き大きな注目を集める。大阪・関西万博での会談を契機に、両国が「食品安全」と「文化交流」の両輪で新たな協力モデルを築けるかが、今後の焦点と言える。


コメント:0 件
まだコメントはありません。