1121人散った戦艦 元乗員の102歳
1121人散った戦艦 元乗員の102歳
2025/06/09 (月曜日)
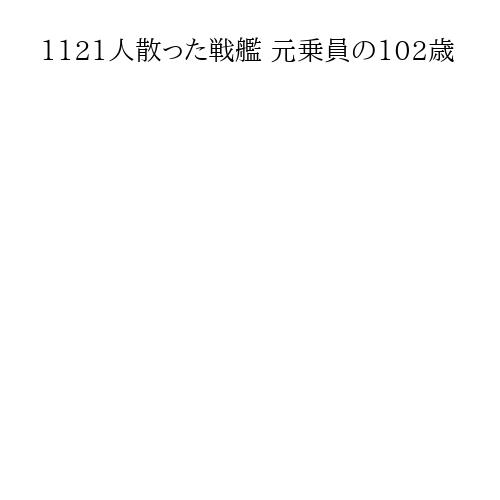
国内ニュース
1121人散った戦艦 元乗員の102歳6/9(月) 9:39
山口沖で謎の爆沈、1121人が散った戦艦陸奥 元乗組員の102歳、海底に横たわる写真見て生存者は「誰もいねえ」 あの日から82年
記事概要
1943年6月8日未明、山口県沖の柱島南方海域で謎の爆沈事故により1121名の乗員が犠牲となった日本海軍戦艦「陸奥」。事故から82年目となる2025年6月8日、元乗組員で現在102歳の篠原喜一さん(長野県在住)が、海底に横たわる「陸奥」の写真を前に「誰もいねえ」と当時の光景を振り返り、その悲劇を語り継いでいます。
戦艦「陸奥」の概要
戦艦「陸奥」は大正11(1922)年に竣工した長門型戦艦2番艦で、全長約215m、基準排水量約38,000トンを誇りました。主砲41cm連装砲を四基装備し、日本海軍の主力艦として位置付けられましたが、昭和18(1943)年の太平洋戦争中期に太平洋艦隊の旗艦を務めていました。
爆沈事故の経緯
昭和18年6月8日未明、同艦は柱島泊地を出航し、訓練を終えて岩国方面へ移動中に前部主砲塔甲板付近で巨大な爆発が発生。瞬時に前部艦橋と主砲塔が吹き飛び、艦体は航行不能となりそのまま南側の海底へ沈没しました。生存者わずか約353名、1121名が帰らぬ人となりました。
原因調査と謎の多さ
日本海軍は当初「魚雷攻撃によるもの」と公表したものの、当該海域に敵潜水艦の存在記録は皆無でした。その後、機密扱いで原因究明は不徹底に終わり、現在も原因として「内部火薬庫の自然発火」「雷撃の誤爆」「機雷触雷」など複数の仮説が残されています。
元乗組員・篠原喜一さんの証言
当時曳航艇の水兵として「陸奥」を支援した篠原さんは、事故直後に漂流した重油と鉄片の海面を目の当たりにし、「見渡す限りに仲間の姿はなく、海面を埋め尽くす残骸だけが広がっていた」と証言します。海底の写真を見て「艦の表面は錆に覆われ、かつての威容はなく、乗員のいない静寂だけが戻ってきた」と語ります。
慰霊と継承活動
陸奥の慰霊は艦ゆかりの山口県光市や広島県大竹市、群馬県高崎市の寺院などで毎年行われています。篠原さんは近年、群馬県の寺院を訪れ、戦没者名簿の奉納や鎮魂法要に参加。「戦艦とともに散った英霊を忘れてはならない」と後世への継承を訴えています 。
海底調査と記録映像
近年の海底調査ではROV(遠隔操作無人潜水機)により艦首から艦尾まで詳細な撮影に成功。写真には折れ曲がった主砲塔や兵員室入口の丸穴が残り、爆心地の凄まじい威力を物語っています。調査チームは「当時の惨状を伝える貴重な資料」と評価し、記録映画やVR展示を通じて一般公開も進んでいます。
陸奥事故が教える教訓
- 大量の火薬を搭載する軍艦の安全管理の重要性
- 戦時下における情報隠蔽と正確な事故報告の必要性
- 人命軽視の指揮・運用判断への反省
これらは現代の危機管理や軍備運用にも通じる普遍的な課題として指摘されています。
まとめ
戦艦「陸奥」爆沈事故から82年、元乗組員・篠原さんの102歳という高齢の肉声は、戦争の悲惨さと平和の尊さを後世に伝える重要な証言です。未解明の謎を含むこの事故は、個々の尊い命が海底に眠る史実として、究明と慰霊、そして平和教訓の継承が今なお求められています。


コメント:0 件
まだコメントはありません。