「親子別姓だ」「戸籍に旧姓なじまぬ」夫婦別姓3案に反対 衆院委での八木秀次氏陳述全文
「親子別姓だ」「戸籍に旧姓なじまぬ」夫婦別姓3案に反対 衆院委での八木秀次氏陳述全文
2025/06/17 (火曜日)
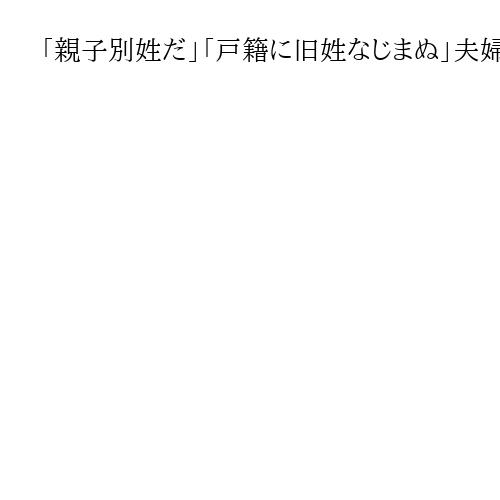
国内ニュース
まず、こうして国会で議員立法という手法によって民法や戸籍法の改正が審議されているが、果たしてここに合理的根拠があるのか、立法手続きについて疑念がある。
民法や戸籍法のような重要かつ基本的な法律を改正する場合、内閣提出法案とするのがこれまでの慣例となっている。
議員立法での民法改正は民法860条の3の新設の1例のみで、成年後見人が被後見人宛に届いた郵便物開封の権限を付与するという、いわば付随的な
はじめに:議員立法での民法・戸籍法改正手続きに合理的根拠はあるか
2025年6月現在、民法や戸籍法といった国民生活の基盤を規定する法律の改正が、議員立法という手法で審議されています。しかし「重要法案は内閣提出法案とするのが慣例」という指摘もあり、議員立法による改正手続きの合理性や妥当性に疑問が呈されています。本稿では、議員立法の立法手続き上の位置づけや歴史的経緯、内閣立法との違い、議員立法の事例、そして今後の課題を整理します。
議員立法と内閣立法の違い
議員立法(議員提出法案)は、国会議員が自ら法案を発議する方式です。発議要件は衆議院で議員20人以上、参議院で議員10人以上の賛成を要します。一方、内閣立法(内閣提出法案)は、内閣が閣議決定を経て国会に提出するもので、議員立法に比べ発議要件は緩やかです。内閣立法は与党・政府の優先政策を反映しやすく、議員立法は所属政党や利益団体との整合性を図る「根回し」が必要とされます:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
内閣提出法案が慣例となった背景
行政作用として政府が法案を策定し、国会の審議日程を確保できる内閣提出法案は、議院内閣制の下で優先的に成立を目指す手段です。年金改革やTPP関連法案、刑事訴訟法改正など、国家の重要政策変更は一貫して内閣提出で行われてきました。これに対し、議員立法は政府の審議日程への影響を極力抑えつつ、全会一致による合意形成を要するとされ、立法手続き上のハードルが高いとされています:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
議員立法の成立実績と無理難題
実際に議員立法として成立する法案は全法案の一割未満にとどまり、多くは廃案または継続審議となります。国会の慣行として、内閣提出法案が優先審議される傾向が強いためです。成立例としては国会法や議員の歳費に関する法律改正、いわゆる附則的・技術的改正が中心で、民法や戸籍法のような「基本法」の改正は極めて稀です:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
議員立法による民法改正の例:第860条の3新設
議員立法で民法改正が実現した例として、2024年3月に施行された民法860条の3の新設があります。これは成年後見人に、被後見人宛の郵便物開封権限を付与する付随的規定で、成年後見制度の円滑化を目的としたものです。本条は、成年後見人の事務遂行に必要な範囲で郵便物を開封・閲覧できると定めていますが、基本的な民法の大枠変更ではありません:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
「選択的夫婦別姓」議員立法案の挫折
2019年、第160回国会に「選択的夫婦別姓」を可能とする民法改正案が議員立法で提出されましたが、本会議での審議入り前に会期切れで廃案となりました。内閣提出法案と比較すると、政策的重みと政府調整の有無が明暗を分けた格好です。この失敗例は、「基本法の改正は政府提出によるべき」との慣例を再確認させました:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
戸籍法改正の議員立法審議事情
戸籍法も身分関係を定める基本法であり、従来の改正は政府提出が原則でした。近年、戸籍に「同性パートナー」の登録を認める議員立法案が提案されましたが、政府提出の内閣法案ではないため、与野党の調整が難航し、審議入りが大幅に先送りされています。基本的生活権に関わる改正であるため、内閣提出の体制を求める声が強まっています。
立法手続き上の合理的根拠とは何か
不文の慣例として、基本法の改正は政府提出法案とするのは、①政策整合性の確保、②予算・財政負担の一元管理、③政府与野党間の調整容易化──などが挙げられます。議員立法でこれらを担保するには、政党の機関承認や事前協議が欠かせず、合理的遂行のための手続きコストが高くなる点が課題です:contentReference[oaicite:5]{index=5}。
今後の課題と展望
今国会で再び議員立法による民法・戸籍法改正が検討されていますが、「重要基本法の改正手続きは政府提出に一本化すべき」という慣例を再確認し、立法手続きの透明性と合意形成手順の明確化が求められます。立法府と行政府が連携し、国民の信頼を担保する合理的な枠組みづくりが急務です。


コメント:0 件
まだコメントはありません。