米関税差し止め訴訟どうなる 解説
米関税差し止め訴訟どうなる 解説
2025/06/06 (金曜日)
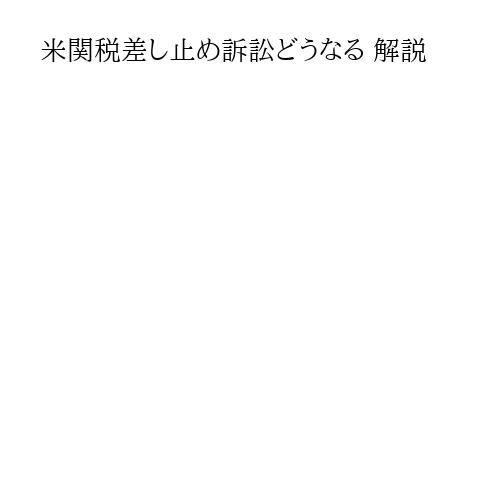
飯塚真紀子在米ジャーナリスト6/6(金) 8:37(写真:ロイター/アフロ)米国際貿易裁判所は、先月28日、国際緊急経済権限法貿易に基づいて貿易相手国に相互関税を課すことは大統領権限を逸脱しているという理由で違法として関税を差し止める判決を下した。トランプ政権は直ちに控訴、翌29日には、米連邦巡回控訴裁判所が米国際貿易裁判所の判断を一時停止し、関税措置を復活させる判断を下した。両当事者の主張陳述後
要約
2025年5月28日、米国際貿易裁判所(CIT)は、ドナルド・トランプ大統領が国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づいて課した相互関税が、「大統領権限の逸脱」に当たるとして違法と判断し、関税の差し止めを命じました。その翌29日には連邦巡回控訴裁判所がCITの判断を一時停止し、関税措置を維持する判断を下しました。ホワイトハウス関係者や識者は、本件が米連邦最高裁まで争われる可能性が高いと見ており、トランプ政権が最終的に勝利する可能性が注目されています。本稿では、IEEPAの概要と歴史的経緯、CIT判決の法的論点、控訴裁判所の判断、過去の類似判例、行政府と議会間の権限対立、さらにトランプ政権が最終的に勝訴するシナリオについて詳しく解説します。
1. IEEPA(国際緊急経済権限法)の概要と歴史
国際緊急経済権限法(IEEPA)は1977年に制定された連邦法であり、大統領に対して「国家安全保障や外交政策を脅かす緊急事態が発生した場合に、貿易制裁や金融資産の凍結など広範な経済措置を講じる権限」を与えるものです。IEEPAの初期の主な活用例としては1979年のイラン革命後のイラン資産凍結や、1980年代のニカラグア政権への制裁が挙げられます。その後、1990年代から2000年代にかけて、北朝鮮・イラク・リビアなどに対し、テロ支援や大量破壊兵器拡散の懸念を理由に同法を適用した制裁措置が実行されました。
2001年の対テロ戦争以降、IEEPAはアメリカ合衆国の対テロリズム戦略と連動してさらに重要性を増しました。たとえば、アフガニスタンやイラクに対する経済制裁、テロ組織への資金流入阻止措置など、さまざまな国際危機においてIEEPAは主要な法律根拠となりました。同時に、IEEPAはあくまで「国家安全保障や外交政策に関連する制裁措置」を想定しており、その適用範囲が適正に運用されるかどうかが過去の裁判でたびたび争われてきました。
2. トランプ政権によるIEEPA相互関税導入の経緯
2025年4月2日、トランプ大統領は大統領令14257号を発行し、IEEPAを根拠として「全輸入品に対する一律10%の相互関税」を課すと同時に、中国やインドなど57カ国には追加で11%から50%の上乗せ関税を課す措置を宣布しました。この「Liberation Day Tariffs」と呼ばれる措置は、長年の対中貿易不均衡や国内雇用保護を目的として掲げられ、これによって年間数千億ドル規模の輸入品に新たな関税をかけるという大規模な通商介入でした。
トランプ政権はこの措置を、「国家安全保障に重大な脅威をもたらす経済的不均衡をただちに是正するための緊急措置」と位置づけ、大統領一存で実行できるIEEPAの「広範な裁量権」を行使したと説明しました。しかし、野党やビジネス界、そして一部の司法専門家からは、「IEEPAが想定する緊急事態の対象範囲を逸脱しており、本来は議会の立法権限に委ねられる関税措置を大統領が行うことは憲法違反ではないか」と強い批判が寄せられました。
3. 米国際貿易裁判所(CIT)の判決概要
2025年5月28日、ニューヨーク州ブルックリンにある米国際貿易裁判所(CIT)は、トランプ政権がIEEPAを根拠とした相互関税のうち、中国等に対する追加関税部分について「IEEPAの立法目的を逸脱している」として違法と判断しました。裁判所は、IEEPAが許容する制裁措置はあくまで「特定の国や地域に限定されるべきものであり、包括的に全輸入品に関税を課すことは、議会が定めた貿易立法権限を侵害する」と結論づけました。その結果、当該関税措置は差し止められ、4月9日に予定されていた高率関税の適用および既存の関税徴収も無効とされました。
CIT判決は、主に次の2点を理由としています。第一に、IEEPAが定める「緊急事態」に該当するのは、テロ支援や核兵器拡散などの国家安全保障リスクであり、「通商不均衡」はIEEPAの適用範囲外と解釈される点。第二に、関税の引き上げは憲法上、議会の立法権限に属するとされており、大統領令のみで実行できる法律ではないと判断された点です。これにより、CITは相互関税の差し止めを命じ、トランプ政権に対して「IEEPAに基づいて包括的関税を実行する権限はない」と明確に警告しました。
4. 連邦巡回控訴裁判所による一時停止判断
CIT判決直後、トランプ政権は即日5月29日に連邦巡回控訴裁判所(Federal Circuit)に控訴を行いました。これに対し巡回控訴裁判所は「CIT判決の効力を暫定的に停止する」判断を下し、相互関税の徴収をそのまま維持することを認めました。一時停止の判断理由としては、「差し止めが直ちに実行された場合、米国内の市場混乱や企業への影響が大きくなる」「最終判決を得るまで現状を維持する方が望ましい」といった点が挙げられています。
この一時停止命令により、米税関・関税局は即日、相互関税の徴収を再開し、企業や輸入業者は以前と同様の高い関税率を支払い続けることになりました。ただし、最終判決までの暫定措置であるため、今後のブリーフィング(口頭弁論)を経て一時停止を延長するかどうかが審理される見込みです。CIT判決の取り消しを求めるトランプ政権側と、差し止めを維持させたい原告側は、順次書面を提出し、巡回裁判所内で激しい法廷論争が繰り広げられています。
5. 過去の類似判例と今回の違い
アメリカでは行政府による通商制裁権限を巡る争いは過去にも複数ありました。特に2018年にトランプ政権が「通商拡大法201条」を根拠に中国や欧州からの鋼・アルミ輸入に高率関税を課した際、複数の訴訟が提起されました。そのうち「Federal Shipping Co. v. United States(2020年)」では、最高裁判所の一部判事が「201条は大統領に貿易安全保障措置を講じる広範な権限を与えており、大統領の判断を尊重すべき」と述べたことで「大統領権限を広く認める」という結論に至りました。このため201条による関税は最終的に維持され、行政府権限の強さを示す先例となりました。
ただし、IEEPAと201条では適用対象と立法構造が異なります。IEEPAは「国家安全保障や外交政策上の緊急事態」を根拠に制裁を課すものであり、その緊急事態の範囲が限定的であるため、経済的な通商不均衡を含むかどうかが大きな争点となりました。一方、201条は「国家安全保障に対する脅威」がより広く解釈され、最高裁がその裁量を広く認めた経緯があります。今回のCIT判決は、IEEPAが想定する「緊急事態」として「通商不均衡」が認められないとした点で画期的であり、最高裁がどのように判断を下すかは、今後の行政権限の範囲を決定するうえで極めて重要です。
6. 行政府と議会の権限対立
アメリカ合衆国憲法では、関税は議会が制定する法律によって定めるとされています。しかし、1950年代以降、議会は大統領に対して通商交渉権や緊急事態における制裁権限を付与する法律を次々と成立させ、行政府の裁量を拡大してきました。IEEPAもその一つであり、大統領が「国家安全保障上の緊急事態」を宣言すれば、議会の個別承認なしに広範囲な経済制裁を発動できる仕組みを提供しています。
しかし、IEEPAが想定する「緊急事態」の範囲や、「議会の立法権限」との整合性が曖昧であるため、憲法的にどこまで大統領が関税を含む制裁措置を自ら決定できるのかが常に問題となってきました。今回のCIT判決は、「議会が定める連邦関税法を迂回して、大統領令のみで包括的な関税を課すのは憲法に照らして許されない」という立場を示した点で、行政府の裁量を抑制する意義があります。一方、トランプ政権側は「IEEPAは議会が与えた権限であり、事実上議会が通商権限の一部を大統領に委譲したものだ」と主張し、行政府権限の正当性を訴えています。
7. トランプ政権が勝訴するシナリオ
現時点で想定されるトランプ政権の勝訴シナリオは主に以下の3つです:
- IEEPAの緊急事態定義を広く解釈させる:連邦巡回控訴裁判所もしくは最高裁で「通商不均衡」は国家安全保障や外交政策に深刻な影響を及ぼす緊急事態とみなされるべきだと判断させる。そうなれば、大統領権限による包括関税は合法と認められる可能性がある。
- 最高裁における行政優越論の採用:過去の201条訴訟と同様に、最高裁の保守派判事が「行政府には緊急性のある経済制裁を迅速に実行する裁量がある」という判断を示すことで、行政府権限が認められ、IEEPAによる関税措置が維持される。
- 議会との妥協による法改正:裁判が長期化する中、議会がIEEPAを改正し、特定条件を満たせば大統領に包括的な関税権限を明示的に付与する法案を可決する。これにより、裁判所の判断にかかわらず行政府権限が法律によって裏付けられ、トランプ政権の政策が正当化される。
ただし、IEEPAの緊急事態定義は本来、国家安全保障上の明確な危機を前提としており、「通商不均衡」をこれに含めるかどうかは法文解釈の焦点です。また、最高裁が行政優越論を採用するかは判事構成や具体的事案の提示によって左右されるため、第1項の解釈がどの程度広がるか慎重に見極める必要があります。さらに、議会が法改正に動く場合は上下院双方の承認を得る必要があり、党派対立が深刻化する中で成立するかどうかは不透明です。
8. 関税差し止めが国際経済にもたらす影響
今回のCIT判決と巡回控訴裁判所の一時停止判断は、アメリカと主要貿易相手国を巻き込む広範な影響を与えています。EUやカナダ、メキシコなどの盟友国は、CIT判決を「法治主義の勝利」と捉える一方で、「米国の貿易政策の不安定性が投資やサプライチェーンに悪影響を及ぼす」と懸念を示しました。特に中国は、本件を「米国の一方的な保護貿易主義が再燃した例」として非難し、WTO(世界貿易機関)への提訴を検討するとしています。
日本政府も、自動車や鉄鋼製品などへの関税引き上げによる輸出への悪影響を懸念し、WTO協定に基づいて紛争解決手続きを進める準備を進めています。さらに、アジア太平洋地域での他国との二国間協定強化を通じて米国依存度を減らす動きが加速しています。これにより、米国のIEEPA関税戦略に対抗して各国が連携し、新たな通商秩序を見据えた動きが活発化すると予想されます。
9. まとめと今後の展望
米国際貿易裁判所がIEEPA相互関税を違法とした判決は、大統領と議会間の権限分立を巡る司法判断の分水嶺となりました。連邦巡回控訴裁判所が一時停止を命じたものの、本件は最高裁まで争われる可能性が高く、最終的に行政権限を拡大するか抑制するかが問われます。過去の201条訴訟では行政府優位の判断が下されましたが、今回はIEEPAの緊急事態定義が焦点となり、最高裁がどちらの立場を支持するかは予断を許しません。
トランプ政権が勝利するには、IEEPA解釈の拡大や法改正を通じて大統領権限を明確化する道が考えられますが、その実現には議会の合意や最高裁判断が不可欠です。一方、今回の判決を受け、各国はWTO紛争解決や代替的通商協定を模索する動きを強めており、米国の貿易政策が国際経済に与える影響は今後も大きな議論材料となるでしょう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。