金融・個人の対中制裁は効果薄の可能性 大西洋評議会「台湾危機で中国に制裁する」(上)
金融・個人の対中制裁は効果薄の可能性 大西洋評議会「台湾危機で中国に制裁する」(上)
2025/07/01 (火曜日)
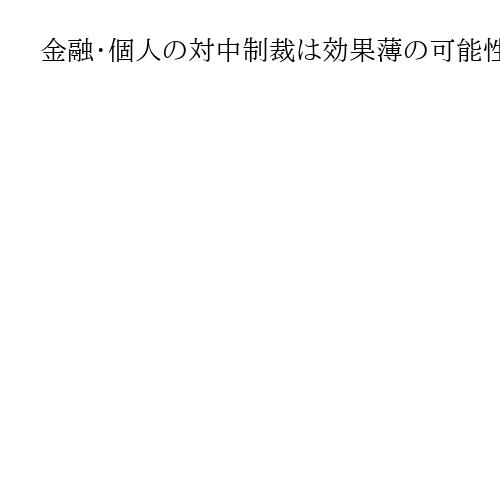
経済成長を重視する中国は台湾への武力侵攻zには踏み切らない-。そんな楽観論の根拠の一つが、中国は侵攻への懲罰として各国が発動する経済制裁に耐えられないという見方だ。だが、侵攻に至る前のグレーゾーン事態で行う制裁の効果を検証した米シンクタンク「大西洋評議会」の報告書は異なる結論に至った。世界第2位の経済規模で各国との相互依存度が高い中国への制裁は、制裁を科す側のコストが大きすぎ、政治的に困難だと分析し
中国への制裁は「痛み分け」──大西洋評議会報告が示す現実と中国の耐性
台湾有事に備えた中国への経済制裁は、有力な抑止手段とみなされてきた。中国経済の世界第2位という規模ゆえ、あらゆる制裁を科せば深刻なダメージを与えられる──。だが、米シンクタンク「大西洋評議会」の報告書は、この楽観論を覆す。制裁を科す側のG7諸国にとっても巨大な経済コストが伴い、さらに中国は回避・代替手段を拡大しており、政治的に実行困難だと結論付けている(出典:産経新聞2025年7月1日)。
「制裁を科す側」のコスト過大
報告書は、金融制裁や輸出管理など3つの主要チャネル──中国の金融機関、指導者や軍関連企業、戦略的産業──を標的にできると整理するが、実際に①米国・欧州の大手銀行が中国ビジネスを縮小すると自国の市場にも混乱が及ぶ、②半導体やレアアースなど相互依存が深い分野での禁輸は同盟国経済にも打撃を与える──と分析。制裁を科す側の国内産業や消費者にも大きな負担が及び、政治的に踏み切れない現実を浮き彫りにしている(大西洋評議会報告書)。
中国の「耐性」と回避能力の向上
さらに報告書は、中国が以下の施策で西側制裁への耐性を高めていると指摘する:
- 自国金融圏拡大:人民元建ての国際決済インフラを強化し、ドル決済への依存を削減。
- 代替貿易ネットワーク:「影の船団」を活用した船舶間移送やダークシップによる密輸が増加。国営企業同士の取引を優先し、制裁対象外ルートを開拓。
- 技術的自立:半導体や希少金属の国内生産拡大と渋太いサプライチェーン再編を推進し、先端技術分野での脆弱性を軽減。
- 外交的牽制:一帯一路参加国との経済協力を深化させ、制裁効果を相殺する多国間圏内での「スワップ協定」やインフラ投資を積極活用。
こうした回避力は、ロシア侵攻後の西側制裁対応で磨かれた経験に基づくもので、報告書は「ロシアの事例は中国にとって“最良の教科書”」と指摘している 。
過去事例との比較:ロシア制裁の教訓
ウクライナ侵攻に対するG7の包括的制裁は、ロシア経済を大きく縮小させつつも、欧米のエネルギー価格高騰や金融市場の混乱を招いた。中国はこの教訓を反面教師とし、自らのエネルギー・資源調達先を分散させたほか、国営企業間の貿易で制裁回避ルートを構築している(WSJ 2024年12月)。
抑止力としての制裁の限界と補完手段
報告書は「制裁は兵器ではない。軍事的抑止や外交努力と組み合わせて初めて効果を発揮する」と結論づける。経済的プレッシャーは局地的・短期的な効果にとどまり、制裁回避策が拡充する中長期的な抑止力には限界がある。従って、日米同盟や地域安全保障協力、サイバー防衛能力強化など多層的アプローチの重要性を強調している(大西洋評議会報告書)。
まとめ
中国への経済制裁は、表面的には強力な抑止手段に見えるが、実際にはG7に重いコストと中国の回避能力を与えるだけにとどまる可能性が高い。中国はロシア事例を学び、金融決済システムの脱ドル化、代替貿易ルートの構築、技術自立の加速を進めており、西側制裁の効果は限定的になりつつある。このため、抑止戦略としては制裁単独に依存せず、同盟・多国間の安全保障協力、軍事的抑止力、サイバー防衛、地域経済連携の強化を組み合わせることが不可欠だろう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。