日本、ブラジルからの鶏肉輸入停止が拡大 鳥インフルエンザウイルスの検出で
日本、ブラジルからの鶏肉輸入停止が拡大 鳥インフルエンザウイルスの検出で
2025/06/18 (水曜日)
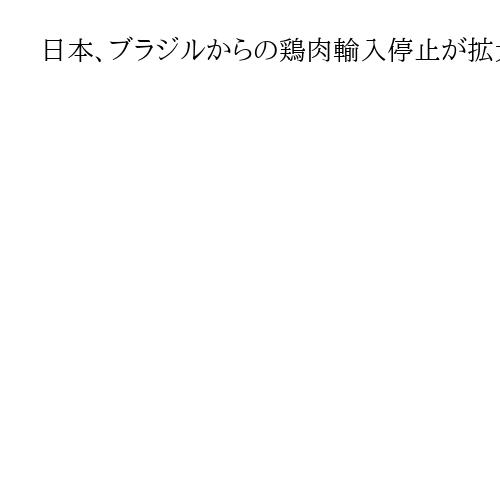
日本の農林水産省によると、中西部マトグロッソ州のカンピナポリス市産は今月9日に、中部ゴイアス州のサントアントニオ・ダバハ市産は14日に停止した。両市では今月に入り自給用の鶏からウイルスが検出された。
5月に南部リオグランデドスル州モンテネグロ市の商業用の養鶏場で検出され、日本はこれまで同市産に限り鶏肉の輸入を止めていた。ブラジル農業省は感染拡大の防止を急いでいるが、拡大が続けば鶏肉輸入量の7割を
はじめに:日本がブラジル産鶏肉輸入を次々停止――鳥インフルエンザ拡大への危機感
2025年6月9日付で日本の農林水産省は、ブラジル中西部マトグロッソ州カンピナポリス市産、同月14日付で中部ゴイアス州サントアントニオ・ダバハ市産の鶏肉および関連品の輸入停止を発表しました。両市では今月、市民自家消費用の鶏から高病原性鳥インフルエンザウイルス(HPAI)が検出されたためです。これに先立つ5月には、南部リオグランデドスル州モンテネグロ市の商業用養鶏場での発生を受け、当該市産に限定して輸入停止を実施していました。本稿では、今回の措置の経緯、ブラジル国内の感染状況と対策、日本側規制の国際的背景、経済的影響、今後の輸入再開プロセスなどを詳しく解説します。
1.ブラジル国内の鳥インフルエンザ発生状況
ブラジル農業省は2025年5月末から6月にかけ、野外飼育の自給用鶏を中心に複数州でHPAI陽性を確認しました。最初の商業用発生は5月9日、リオグランデドスル州モンテネグロ市の大規模養鶏場で報告されました。続いて6月9日にはマトグロッソ州カンピナポリス市、14日にはゴイアス州サントアントニオ・ダバハ市の自家飼育鶏で陽性が検出されています。感染経路は渡り鳥や野鳥由来とみられ、養鶏場では即時の殺処分と防疫措置が講じられています。防疫区域の設定や移動制限、ワクチン接種の検討など、州政府と農業省が連携して感染拡大防止に取り組んでいます。
2.日本の輸入規制措置と根拠
日本はこれまで、OIE(国際獣疫事務局)のガイドラインおよび農林水産省の動物検疫規程に基づき、鳥インフルエンザの発生状況に応じて地域別・施設別に輸入停止措置を実施しています。商業用発生に伴うモンテネグロ市産の輸入停止は5月10日から適用され、今回の自給用発生に伴い、カンピナポリス市とサントアントニオ・ダバハ市についても同様の措置を発動しました。これにより同市産の鶏肉・加工品・卵が日本へ到着した場合、検疫所で強制廃棄されます。
3.中国・EUなど主要輸入国の対応比較
ブラジルは世界最大の鶏肉輸出国であり、年間約600万トンを供給します。主要輸入先の中国は5月16日、リオグランデドスル州全域の商業用発生を受けて60日間の全面輸入停止を決定し、輸出額の約14%を占める市場を一時閉鎖しました。EUはこれまで発生国に対し、発生地域への限定的な封鎖措置を実施し、周辺地域の輸入は許可。日本は発生市ごとの「区域化」措置を2024年から導入し、感染確認市のみ対象とする柔軟な対応を特徴としています。
4.経済的影響と農業部門の懸念
鳥インフルエンザによる輸入停止が長期化すると、日本国内の鶏肉需給には一時的なひっ迫感が生じる恐れがあります。ブラジル産は国内シェア約70%を占め、価格抑制に貢献してきたため、代替輸入先の増加や国内生産拡大によるコスト上昇が懸念されます。ブラジル側も早期終息を目指し、対象地域での野生鳥類監視強化や家きん飼養衛生管理基準(GMP)の徹底指導を急いでいます。
5.感染再発防止と輸入再開の要件
日本が当該市産の輸入再開を認めるには、発生から28日経過後、周辺地域含め新規発生が確認されないことが条件です。さらにOIE認定のサーベイランス実施による清浄性証明書の提出が必要とされます。ブラジル農業省は地域別のモニタリング報告を強化し、各市の衛生状況を逐次公表する方針です。再開判断は現地報告と検疫所の検査結果を踏まえ、専門家会議で慎重に検討されます。
6.家きん衛生管理の国際基準と国内対応
HPAI対策として世界的に整備が進む「家きん衛生管理プログラム(GMP+)」では、飼育環境の生物学的安全性確保、従業員動線管理、野鳥侵入防止設備の義務化などが求められます。ブラジルでは一部大規模養鶏場が導入を進めていますが、自給用小規模農家では実施が遅れており、今回の発生はその脆弱性を浮き彫りにしました。日本側は輸入検疫強化に加え、国内養鶏農家への衛生管理講習会やワクチン臨床試験支援を拡充しています。
結論:鳥インフル長期化リスクへの備えと国際協調の重要性
今回の輸入停止措置は、発生市ごとの限定的対応と地域衛生体制の強化を両立させる日本独自の「区域化」モデルを改めて示しました。事態の長期化に備え、ブラジル側は野鳥監視ネットワークの強化や小規模農家支援を急ぎ、日本側は輸入再開要件の透明化と国内代替供給ルートの整備を進める必要があります。国際獣疫事務局(OIE)を通じた情報共有や、主要輸入国との協調措置が、グローバルな食料安全保障と家きん衛生管理の向上につながるでしょう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。