ラーメン店倒産 過去2番目の水準
ラーメン店倒産 過去2番目の水準
2025/07/05 (土曜日)
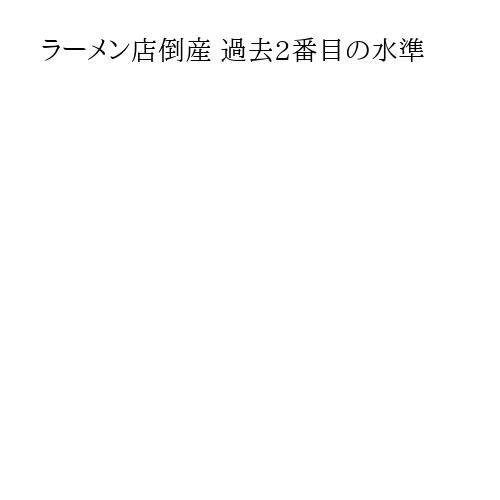
2025年上半期「ラーメン店」倒産 過去2番目の高水準 コロナ禍の重しを抱えながら、価格転嫁と効率化が急務に
2025年上半期「ラーメン店」倒産、過去2番目の高水準に──コロナ禍支援後の逆風と価格転嫁の難しさ
2025年上半期(1~6月)のラーメン店倒産件数は25件(前年同期比24.2%減)で、集計開始以来最多だった2024年上半期の33件に次ぐ過去2番目の高水準となりました。負債総額は16億5,700万円と前年同期比23.8%増加し、金額規模でも過去2番目の大きさを記録。小・零細規模の店舗に加え、大口負債事例も散見されるなど、業界全体で生存競争が激化しています。
背景
ラーメン店は比較的低資本で開業できることから新規参入が多く、全国で多様な業態が競い合う激戦区です。コロナ禍の間は、無利子・無担保のいわゆる「ゼロゼロ融資」や営業時間短縮に伴う休業支援など、政府・自治体による手厚い資金繰り支援に支えられ、倒産件数は2021年上半期14件、2022年上半期5件と低水準で推移しました。しかし支援縮小後、原材料費や人件費、光熱費の一斉高騰、円安による仕入れコスト増が各店舗を直撃し、再び淘汰の波が押し寄せています。
倒産動向の推移
まず上半期の推移を振り返ると:
- 2021年上半期:14件(ゼロゼロ融資など支援下で低水準)
- 2022年上半期:5件(支援残存期で過去最少)
- 2023年上半期:33件(支援終了後の急激な増加)
- 2025年上半期:25件(3年ぶりに減少も過去2番目の高水準)
また、2024年度(4月~翌3月)の年間倒産件数は47件(前年度比25.3%減)で、63件の23年度をピークにやや落ち着きを見せたものの、依然高水準でした(出典:Foodrink 安田正明, 2025年4月7日)。
要因分析
主因は「販売不振」で、2025年上半期倒産の88.0%を占めています。主な要因は以下の通りです:
- 原材料費高騰:小麦粉やチャーシュー用肉の輸入価格上昇
- 人件費増加:人手不足対策による賃金引き上げ
- 光熱費の急騰:電力・ガス料金の上昇
- 円安:輸入食材コストへの直撃
- 価格転嫁の困難さ:値上げによる客離れリスク
これらの開店・運営コスト増に見合うだけの売価転嫁が難しく、利益率の低い小・零細店舗を中心に経営が立ち行かなくなっています。
歴史的視点
同調査は2009年以降のラーメン店倒産を集計していますが、過去15年で上半期の倒産件数が20件を超えたのは以下の3回のみです:
- 2023年上半期:33件
- 2025年上半期:25件
- 2024年度年間:47件(23年度:63件)
パンデミック前の2019年頃は上半期で20件以下、年間でも30~40件程度で推移しており、コロナ禍とその後の物価・人件費高騰がいかに影響を与えたかが浮き彫りです。
似ている事例
他の飲食業態でも同様の淘汰が進んでいます。2024年上半期の飲食業全体の倒産件数は493件と過去最多を更新し、特にバー・キャバレーやすし店の倒産が前年同期比で2倍以上に急増しました(出典:東京商工リサーチ )。こうしたナイトライフ系や高級業態と比べ、ラーメン店は小資本・低価格路線が特徴ですが、基本的なコスト構造悪化の影響は共通しており、業界を問わず生き残り策の急務が叫ばれています。
対策と展望
今後、ラーメン店が継続的に生き残るためには:
- オペレーション効率化:自動化・省力化による人件費削減
- 差別化戦略:地域特性や独自メニューによるブランディング強化
- 適正な価格転嫁:顧客心理を考慮した段階的値上げ
- 直販・EC展開:冷凍ラーメンなど通販ビジネスの併用
- 店舗統合・フランチャイズ化:資本力強化と規模メリットの享受
これらの手法を組み合わせ、小規模店舗でも生き残れるビジネスモデル構築が求められます。
まとめ
2025年上半期のラーメン店倒産は、25件の件数と16億5,700万円の負債総額という数値が示す通り、コロナ禍支援終了後のコスト高騰と価格転嫁難による厳しい経営環境下で、過去2番目の高水準を維持しました。2021年・2022年の低水準から一転、2023年上半期の33件をピークに、2025年上半期はやや減速したものの依然高止まりしており、生存競争の厳しさが続いています。
さらに、同時期の飲食業全体では493件もの倒産が発生し、バー・すし店といった他業態でも淘汰が加速。ラーメン店特有の低価格・小資本モデルは参入障壁を下げた一方で、コスト上昇への耐性が弱く、一度客離れが起これば立て直しが困難です。
今後は効率化や差別化、段階的な価格転嫁などを通じて、店舗ごとの競争力を高める必要があります。併せて、通販や業務提携といった新たな収益柱の確立、さらには複数店舗展開によるスケールメリット追求など、経営の多角化が生死を分ける要因となるでしょう。
結論として、ラーメン店は「手軽な一杯」という魅力を保ちつつも、背後で進むコスト構造の変化に対応するための経営改革を急ぎ、新たな時代の消費者ニーズと市場環境に適応していかなければなりません。今こそ業界全体で知見とノウハウを共有し、持続可能なビジネスモデルを構築することが、倒産件数を減らし、次の成長を生む鍵となるでしょう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。