外国人増え賃金上がらず 主張検証
外国人増え賃金上がらず 主張検証
2025/07/19 (土曜日)
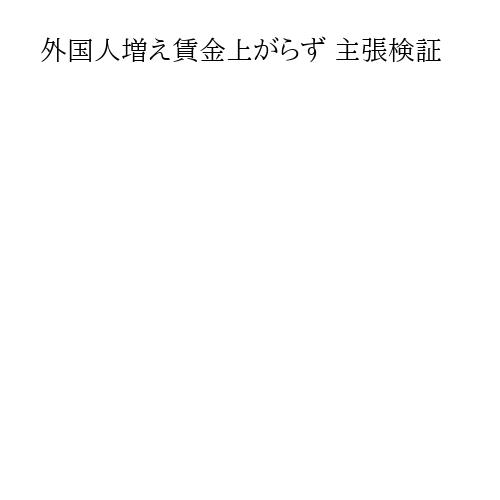
<ファクトチェック>「外国人増えると日本人の賃金が上がらない」は事実? 識者に聞く
外国人労働者と賃金問題:真実と誤解を検証
2025年7月19日、Yahoo!ニュースに掲載された毎日新聞の記事「<ファクトチェック>『外国人増えると日本人の賃金が上がらない』は事実? 識者に聞く」は、外国人労働者の増加が日本人の賃金停滞の原因とする言説を検証している。この主張は、2025年参議院選挙を前に政治的な議論で浮上しており、賛否両論を呼んでいる。以下、この問題の背景、歴史的文脈、類似事例、そして今後の影響について詳しく解説する。
[](https://news.yahoo.co.jp/pickup/6546123)主張の概要と検証結果
毎日新聞の記事によると、「外国人労働者が増えると日本人の賃金が上がらない」との言説は、特にSNSや一部政治勢力で拡散されている。参政党などがこの主張を掲げ、外国人労働者の受け入れ拡大が日本人の低賃金を招いていると訴えている。しかし、専門家の分析では、この主張を裏付ける明確な証拠は乏しい。龍谷大学の脇田滋名誉教授(労働法)は、「日本の賃金が低いのは、非正規雇用の拡大や政府・経営者の賃金抑制策が主因」と指摘し、外国人労働者の影響は限定的だとしている。ニッセイ基礎研究所の鈴木智也准主任研究員も、「外国人流入による賃金への影響は明確に確認されていない」と述べる。
[](https://news.yahoo.co.jp/pickup/6546123)X上では、この記事に対する反応が多様だ。ある投稿では、「外国人労働者が低賃金の原因でないなら、なぜ30年間賃金が上がらないのか」と疑問を呈し、別の投稿では「企業が賃金を抑える構造こそ問題」と脇田教授の見解を支持する声が見られる。これらの意見は、外国人労働者をめぐる議論が感情的かつ政治的な対立に発展している現状を反映している。
歴史的背景:日本の労働市場と外国人労働者
日本の労働市場は、1990年代のバブル崩壊以降、「失われた30年」と呼ばれる経済停滞期を経験した。この期間、企業はコスト削減のため非正規雇用を拡大し、正規雇用の賃金上昇を抑制。厚生労働省によると、1997年から2020年までの実質賃金指数はほぼ横ばいで、主要先進国の中で日本のみが賃金停滞を続けた。一方、外国人労働者は1990年の約100万人から2024年には200万人を超え、労働力不足を補う役割を担ってきた。特に、製造業、建設業、介護、サービス業で外国人労働者の需要が高まっている。
外国人労働者の受け入れは、1980年代後半の日系南米人や1990年の入管法改正による技能実習制度の導入で本格化した。2019年には「特定技能」制度が創設され、労働力不足解消を目的に受け入れが拡大。政府は外国人労働者を「労働力の補充」と位置づけるが、賃金への影響は複雑だ。外国人労働者の賃金は、日本人の約7割程度と低く、産経新聞は「安価な労働力の活用が全体の賃金を抑制する可能性」を指摘するが、因果関係は明確でない。
歴史的に、外国人労働者の増加は経済成長と労働市場の構造変化に伴う。バブル期には労働力不足から外国人労働者が増加したが、賃金は高水準だった。対照的に、2000年代以降の低成長期では、非正規雇用の増加や企業の内部留保拡大が賃金停滞の主因とされる。X上では、「1990年以降のGDP停滞と外国人労働者の増加は関連がある」との意見もあるが、専門家は「賃金停滞は労働市場全体の構造問題」と分析する。
類似事例:海外の外国人労働者と賃金
外国人労働者の増加と賃金の関係は、海外でも議論されてきた。米国では、1980年代以降のメキシコ系移民の増加が低賃金労働市場に影響を与えたとする研究がある。しかし、経済学者トーマス・ピケティは、賃金格差の拡大は移民よりも資本集中や労働組合の弱体化が主因と指摘。カナダやオーストラリアでも、外国人労働者の受け入れが進むが、賃金停滞の主因は国内の労働政策や経済構造にあるとされる。カナダのトロント大学による研究では、移民労働者が低賃金セクターに集中する一方、高スキル労働者の賃金にはほとんど影響がないと結論づけられた。
欧州では、難民危機後のドイツで外国人労働者が急増したが、賃金への影響は限定的だった。ドイツ労働研究所の調査によると、外国人労働者は低賃金職に集中するが、全体の賃金停滞は企業の賃金抑制策やグローバル競争の影響が大きい。日本と同様、外国人労働者を「賃金停滞のスケープゴート」とする政治的言説が問題視されている。X上では、「外国人労働者が賃金を下げるという主張は、欧米でも証拠が薄い」との投稿があり、国際的な視点での議論が広がっている。
社会的影響:排外主義と政治的議論
「外国人増えると賃金が上がらない」との言説は、排外主義やポピュリズムを助長するリスクがある。毎日新聞の記事では、こうした主張がSNSで拡散され、外国人労働者への偏見を煽ると指摘。参政党の「日本人ファースト」政策は、外国人労働者の受け入れ制限を訴え、2025年参院選で注目を集めている。X上では、「外国人労働者が日本の文化や治安を脅かす」との感情的な意見が散見される一方、「外国人労働者がいなければ介護や建設業が成り立たない」との現実的な声もある。
政治的には、立憲民主党の野田佳彦代表が参政党の主張を「排外主義的」と批判し、共生社会の重要性を強調。対照的に、参政党支持者は「日本の労働者を守るべき」と反論し、議論が二極化している。著名人のインスタグラム投稿では、参政党への支持を表明し、「一人の投票は民主主義の根幹」と主張。批判に対し、選挙結果を尊重すべきと訴えた。この発言は、外国人労働者をめぐる議論が政治的信条や国民感情に深く根ざしていることを示している。
経済的影響と今後の課題
外国人労働者の増加は、日本の労働力不足を補う一方、賃金構造や労働条件の改善が課題だ。厚生労働省のデータでは、外国人労働者の平均賃金は日本人の約70%で、特に技能実習生は低賃金で働くケースが多い。新制度「育成就労」が2025年に導入予定だが、不況時の雇用の調整弁として外国人労働者が解雇されるリスクが指摘されている。
[](https://news.yahoo.co.jp/pickup/6546089)賃金停滞の解決には、外国人労働者の処遇改善や非正規雇用の是正、最低賃金の引き上げが必要だ。政府は2024年に最低賃金を全国平均で時給1004円に引き上げたが、国際比較では依然低い。X上では、「外国人労働者を低賃金で使う企業体質が問題」との意見があり、企業の賃金政策見直しを求める声が強い。日本経済団体連合会も、賃上げと生産性向上を同時に進める必要性を強調している。
今後の展望:共生と経済成長のバランス
外国人労働者の受け入れは、少子高齢化が進む日本で不可避だ。総務省によると、2025年の労働力人口は約6000万人に減少し、外国人労働者の役割はさらに重要になる。しかし、賃金停滞や社会統合の課題を放置すれば、排外主義や社会分断が悪化する恐れがある。政府は、外国人労働者の権利保護や日本語教育の拡充、公正な労働環境の整備を進める必要がある。また、企業には賃上げや正規雇用の拡大を求める圧力が高まるだろう。
X上では、「外国人労働者を受け入れつつ、日本人の賃金も上げる政策が必要」との提案が散見される。欧米の事例を参考に、外国人労働者の賃金基準を明確化し、差別的な処遇を防ぐ法整備が求められる。参院選を機に、外国人労働者と共生する社会のあり方が議論の焦点となるだろう。
結論:事実に基づく議論の必要性
「外国人労働者が賃金を下げる」との主張は、証拠が乏しく、非正規雇用の拡大や企業の賃金抑制が主因とされる。日本の労働市場は、少子高齢化による人手不足から外国人労働者に依存する一方、賃金停滞の構造的問題が続く。欧米の事例でも、外国人労働者の影響は限定的で、労働政策の改善が鍵だ。参院選での議論やX上の多様な意見は、社会の関心の高さを示す。外国人との共生と賃上げを両立させる政策が、日本経済の持続的成長に不可欠だ。


コメント:0 件
まだコメントはありません。