沖縄戦後80年 遠のく「平和の島」
沖縄戦後80年 遠のく「平和の島」
2025/06/19 (木曜日)
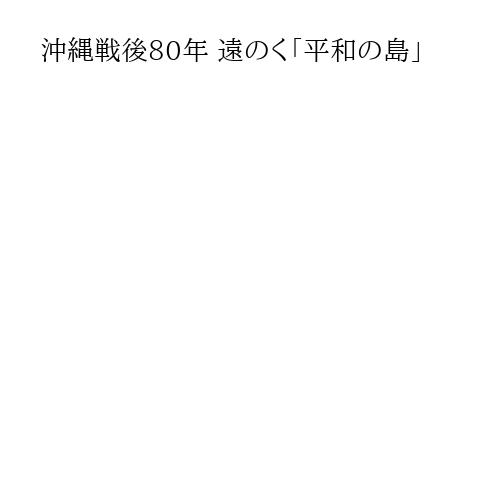
国内ニュース
沖縄、苦難の戦後80年 地上戦、米軍統治、基地強化 遠のく「平和の島」
はじめに:戦後80年を迎えた沖縄──苦難の歴史と遠のく“平和の島”の夢
2025年6月、太平洋戦争末期の地上戦から80年を迎えた沖縄は、戦没者の慰霊や平和への誓いの一方で、いまなお重くのしかかる米軍基地問題を抱え続けています。約20万人の犠牲を出した戦場の島は、1945年から1972年まで米軍統治下に置かれ、その後も日本政府の施策や基地強化によって「平和の島」のイメージは遠くなりつつあります。本稿では、戦後の苦難から現代の基地負担までをたどり、沖縄が見据えるべき未来を考えます。
1.血と泥にまみれた地上戦の記憶
1945年4月1日、米第10軍による上陸作戦「アイスバーグ作戦」が始まり、82日間にわたる沖縄戦で多くの米兵と沖縄県民が命を落としました。日本軍守備隊の自決命令による集団自決や、大規模な砲撃・空襲のなか、住民の犠牲は計り知れず、いまだに多くの遺骨が洞窟に残されたままです。
2.米軍統治下の苦悩と復帰運動
戦後、沖縄は米国の施政権下に置かれ、言論や集会の自由が制限される一方、米軍基地建設のための土地収用が強行されました。住民たちは基地反対運動や「沖縄返還」を求めるデモを繰り返し、1971年の日米協定で「沖縄返還協定」が成立。1972年に本土復帰を果たしましたが、基地の多くは返還されず、現在も県内各地に集中しています。
3.復帰後の基地強化と地域経済
復帰後の沖縄は、日本全国のわずかな面積でありながら在日米軍施設の大半を抱えています。現在も多数の施設が稼働し、政府からは毎年多額の交付金が支払われますが、騒音や事故、環境汚染など、住民生活への影響は深刻です。基地関連の雇用が地域経済の一部を支える一方で、観光や農業の発展を阻む要因ともなっています。
4.過去の民衆蜂起と現在の抗議活動
1970年に起きたコザ暴動は、米軍軍警との衝突で多くの負傷者を出し、基地への不満が爆発した象徴的事件です。現在も辺野古での新基地建設に対する座り込み抗議が10年以上続き、国内外の注目を集めています。住民や自治体は基地負担の軽減と県外移設を強く求めています。
5.慰霊と平和への取り組み
毎年6月23日の「慰霊の日」には、沖縄全戦没者追悼式が営まれ、多くの参列者が平和祈念公園を訪れます。戦没者遺骨の発掘や身元確認に市民が参加し、慰霊碑の整備や平和教育を通じて、次世代への継承が進められています。
結論:平和への“再発見”と未来への選択
戦後80年を迎えた沖縄は、過去の痛ましい記憶と現在の基地負担のはざまで揺れています。真の「平和の島」を取り戻すには、基地を含む社会構造の見直しと地域主体の経済振興、国際的な理解と連帯の深化が不可欠です。沖縄の人々が自ら描く未来を尊重し、歴史の教訓を次代に生かす取り組みこそが、平和への確かな一歩となるでしょう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。