30年ひきこもる子 気遣う70代の父
30年ひきこもる子 気遣う70代の父
2025/06/23 (月曜日)
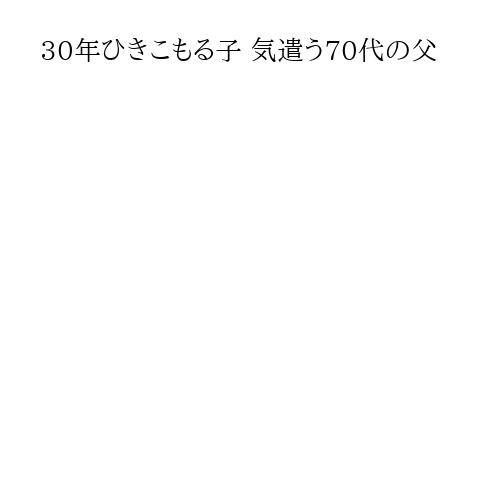
総合ニュース
長男が不登校、「教師の子なのに」「学校というレールに戻さねば」…誰にも相談できず悩んだ父
教師家庭に訪れた“不登校”の現実
2025年6月23日9時30分配信の読売新聞オンラインは、現役小学校教諭の父親が自身の長男(中学生)の不登校問題に深く悩み、誰にも相談できずに苦しんだ体験を伝えています。父親は「教師の子なのに」「学校というレールに戻さねば」というプレッシャーに囚われ、家族や同僚にも打ち明けられず、孤立していったといいます。(出典:読売新聞オンライン 2025年6月23日)
不登校の発覚と初動対応
長男は入学当初から登校を嫌がり、最初は体調不良を訴えて欠席を繰り返しました。父親は「授業についていけないのでは」と学習面を心配し、家庭学習のサポートに注力しましたが、状況は改善しませんでした。「学校の先生の息子なら大丈夫」という周囲の目が、かえって息子を追い詰めたといいます。
医療機関の受診と医師の助言
学校カウンセラーの勧めで精神科を受診したところ、医師から「病気ではなく、親子関係を見直す時間が必要」と指摘されました。「診断名はつかない」との言葉に父親は戸惑い、「レールに戻す」ことしか考えてこなかった自分を反省しました。
「戻さねば」という強迫観念
父親は、教育現場で「登校指導」の先鋒を務める立場。自身が家庭で不登校を解決できないことへの罪悪感は大きく、「学校というレールから外れたら再起不能になるのでは」と焦燥を募らせました。
相談できないジレンマ
同僚教諭に相談すれば噂が広がる不安、家族に打ち明ければ「家庭の恥」となる恐れから、父親は誰にも口を開けずに一人で抱え込みました。電話相談窓口への連絡も迷い、支援制度の利用は後回しに。
支援機関との出会い
半年後、地域の教育相談センターに匿名で足を運び、ようやく専門家と面談。息子の気持ちを優先する支援プランを提案され、「戻す」ではなく「選択肢を増やす」視点に切り替わりました。
フリースクールや居場所づくり
相談センターの紹介で、息子は週2回のフリースクールに参加。自宅と学校の中間的な居場所で、友人を作り、少しずつ校舎への足取りが軽くなりました。父親も家での声かけを変え、「行きたいところへ行っていい」と見守る姿勢へとシフトしました。
不登校支援の歴史的変遷
かつて日本では「皆が同じ教室に集まること」が教育の前提とされ、不登校は個人の問題ととらえられてきました。しかし1990年代以降、法改正とともにフリースクールや通信制高校、スクールカウンセラー配置が進み、多様な学びの場が認められるようになりました。
教師家庭の支援ネットワーク
- 校内スクールカウンセラーとの連携で、匿名相談を可能にする仕組み
- 同僚教師向けメンタルヘルス研修で「家庭の課題を話せる場」を設置
- 教育委員会による教職員子育て支援プログラムの整備
欧米の教育現場との比較
北欧諸国では「教育システムのミスマッチ」ととらえ、学校外プログラムを公費で保障。英国では「代替カリキュラム」を地域ごとに定め、子どもの興味・関心に沿った学びを提供しています。日本でも「チーム学校」構想を活かし、家庭・学校・地域が協働するモデルが注目されています。
多様性を尊重する教育へ
「学校に戻す」だけがゴールではありません。子どもの個性やペースを尊重し、学びと居場所を多様化することが、次世代の教育の鍵です。教師自身が子育ての苦悩を共有し、支援ネットワークを活用することが、持続的な解決への道となるでしょう。
結び:子どもの声に耳を傾けて
「教師だからこそ相談できない」という父親の告白は、教育現場全体に向けた痛烈なメッセージです。子どもの小さなSOSを見逃さず、多様な支援策を組み合わせることで、新しい学びの形を社会で育んでいきたいものです。


コメント:0 件
まだコメントはありません。