「反自衛隊」沖縄県民の意識変化
「反自衛隊」沖縄県民の意識変化
2025/06/23 (月曜日)
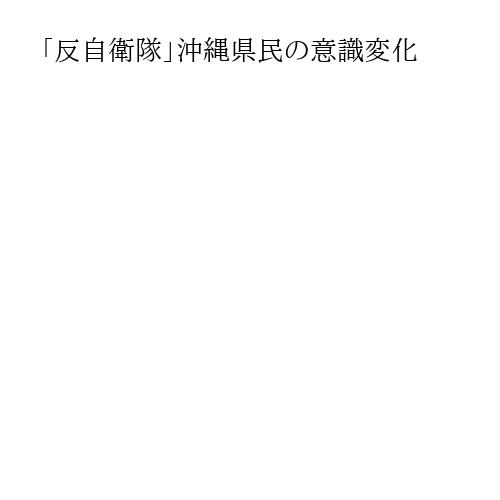
総合ニュース
地上戦から80年 「反自衛隊感情」強かった沖縄で見える意識変化
反自衛隊感情の背景
1945年の沖縄地上戦から80年を迎えた今も、「反自衛隊感情」は沖縄県民の間に根強く残ってきました。1972年の本土復帰後、県内に陸上自衛隊が配備されると、住民は“再び戦場になるのでは”という不安から抗議集会を開き、自衛隊員の住民登録を拒否する動きも起きました。こうした抵抗は当初、「沖縄を軍事拠点にしたくない」という強い思いの表れでした。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
復帰直後の抵抗と集会
復帰後まもない1970年代前半、辺野古やうるま市など各地で「自衛隊配備反対」の旗を掲げた集会が頻発。地元紙報道によれば、自衛隊の入域式典には数百人規模の抗議行動があり、県民の7割近くが“自衛隊不要”と考えていました。基地への怨嗟(えんさ)が、自衛隊全体への拒否感情につながっていったのです。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
住民登録拒否と具体的事例
配備当初、自衛隊員の住民票登録を巡っては、複数の自治体で役場が手続きを拒否。市町村の窓口職員が「戦争を呼び込む」との声を上げ、隊員は県外に転出せざるを得ないケースも見られました。このような事例は、県民感情の深刻さを象徴しています。
調査に見る意識の変化
明星大学などの研究グループが2022年に実施した沖縄県在住者への世論調査では、自衛隊の強化に「賛成」が約40%、「反対」が30%弱、「どちらともいえない」が3割強を占めました。若年層ほど賛成が多く、かつての一辺倒な反対感情から、複雑な県民感情へと移行していることがうかがえます。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
若い世代の支持傾向
別の調査では、18~34歳の約5割が「自衛隊強化に賛同」と回答。戦後世代よりも高い支持率を示し、情報化時代の大学生・若手社会人が「災害派遣や地域防衛で役立つ」と評価していることがわかります。
災害派遣での評価の高まり
近年の台風被害や新型コロナ対応で、自衛隊は給水支援や検査拠点設営などを迅速に実施。被災地での働きぶりに対し、沖縄県民の間でも「頼りになる存在」との声が増え、かつての反発感情を和らげる要因となっています。
地元紙報道と住民の声
沖縄タイムスや琉球新報の特集では、自衛隊員が地域交流や清掃活動に取り組む姿を紹介し、「人柄を知ることで抵抗感が薄れた」との声を複数掲載。メディアによる積極的な情報発信も、意識変化に一役買っています。
比較:本土とのギャップ
本土では自衛隊配備にあまり抵抗感が見られないのに対し、沖縄では依然として基地負担への敏感さが顕著。だが、全国的に若年層の国防意識が高まる中、沖縄でも若者が自衛隊を“地域の安全を守る存在”と捉え始めており、かつての一律反対とは一線を画しています。
自衛官出身県民の視点
うるま市出身の元自衛官は「派遣時に地元の理解を得られず苦労したが、今は近所の祭りで子どもたちに武器や装備を見せると喜ばれる」と語ります。直接触れ合うことで生まれる信頼感が、かつての忌避感を解消する鍵となりつつあります。
基地負担軽減策との連携
沖縄振興交付金の増額や、返還基地跡地の民間活用など、振興策とのセットで自衛隊への理解を深める取り組みも進行中。自治体と防衛省が協働し、住民利便施設の整備や見学会を実施することで、「基地が息苦しいだけの場所ではない」というイメージ刷新を図っています。
まとめ:過去から未来へ
地上戦の記憶と基地負担の重さから生まれた「反自衛隊感情」は、復帰50年余りで徐々に彩りを変えています。災害支援や対中国抑止など、安全保障の必要性を感じる県民が増え、特に若い世代で好意的な意見が目立ちます。今後は、地域振興との連携を深めながら、沖縄が「防衛と共存するモデル地域」として全国に示す役割が期待されます。:contentReference[oaicite:3]{index=3}


コメント:0 件
まだコメントはありません。