政府 コメの「生産調整」見直しへ
政府 コメの「生産調整」見直しへ
2025/06/06 (金曜日)
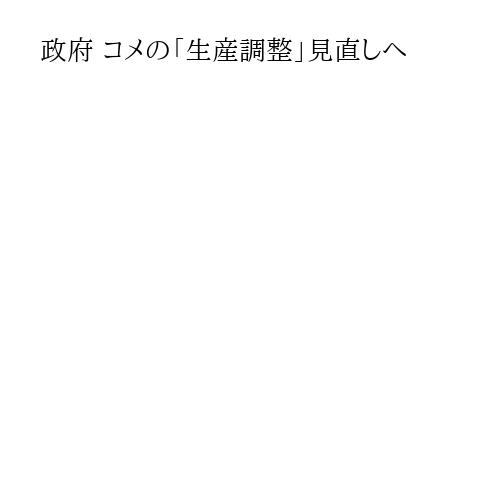
総合ニュース
コメの「生産調整」、政府が見直しへ…農家の経営難防ぐため「所得補償」新設も検討
政府はコメの価格高騰を受け、必要な生産量確保のため、事実上の減反にあたる生産調整を見直す方針を固めた。米価下落で農家が経営難に陥る事態を防ぐ観点から、新たな所得補償の実施も検討する。政府は5日、「米の安定供給等実現関係閣僚会議」の初会合を首相官邸で開き、価格高騰の原因究明や今後の農政改革に向けた議論に着手した。
はじめに
2025年6月5日、政府はコメの生産調整政策(通称「減反政策」)を見直す方向で議論を開始しました。需要が伸び悩む一方、米価の急騰や品薄状態が顕在化し、消費者や流通業者からの不安の声が高まっています。これまでの「必要以上に生産を抑える」仕組みから転換し、「状況に応じて生産を増減できる」柔軟な制度設計を目指す動きが本格化しており、農政の大きな転換点となる可能性があります。
減反政策の誕生と役割
日本における減反政策は、戦後の食料不足を背景に1960年代後半から導入されました。当時は、国の統制下で作付面積を制限し、余剰米が市場に溢れないように調整する仕組みが構築されました。農家は「田んぼの一部を休ませてコメ以外の作物」を栽培し、その見返りとして政府から補助金を受け取る運用が行われ、需要・供給のバランスを保つ役割を担ってきました。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
しかし、1990年代以降、補助金の多くが転作作物に偏るようになると、農家は「コメを作るよりも大豆や小麦などの転作作物で収入を得た方が有利」と判断し、コメ作付面積の縮小が進みました。その結果、農村の集落や生産基盤は脆弱化し、担い手不足と高齢化が加速しました。さらに2000年代以降は自由化の流れもあり、国が強力に介入して需給をコントロールする仕組みは徐々に形骸化しました。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
近年の米価高騰とコメ不足
2025年に入ってから全国的にコメの供給不足が深刻化し、米価は一気に高騰しました。農林水産省は備蓄米を複数回にわたり市場に放出しましたが、いずれも需要を満たせず、スーパーや小売店で品薄が続きました。消費者からは「米の値段が高すぎる」「近所の店で売り切れが続いている」といった声が噴出し、食卓への影響が広がっています。
現行の生産調整では「前年の実績をベースに翌年の作付面積を決定する」ため、需要増加や異常気象の影響に柔軟に対応できません。たとえば、2025年春の寒波や梅雨入りの遅れが一部産地で生産見通しを狂わせ、生産量の低下を招いたことも指摘されました。気候変動に伴う収量の不安定化が続く中、硬直的な作付ルールでは需給バランスを取り損ねるリスクが顕在化しやすくなっています。
政府・閣僚会議の設置と議論の焦点
政府は6月5日夕方、石破茂首相を議長とする「米の安定供給等実現関係閣僚会議」の初会合を開催しました。出席した小泉進次郎農林水産大臣は記者会見で、「なぜ今コメが不足し、価格が高騰しているのか、まずは詳細な原因を分析する」と述べ、流通の適正化や生産増加策に取り組む考えを示しました。具体的には、①減反対象品目の見直し、②備蓄米の計画的放出と売り先の多様化、③生産段階でのリスク分散策(スマート農業の普及支援等)などが検討課題に挙がっています。
特に注目されるのが、「所得補償制度」の新設です。従来、減反の代わりに支払われる補助金は「転作補助金」として転作先の作物に手厚いものでしたが、生産を増やす局面では「生産量を確保した農家に対する最低限の所得補償」が必要になります。この案は、増産が進んだ場合に市場価格が急落するリスクを回避するセーフティーネットとして機能することが期待されています。2026年6月末までに具体的な制度設計をまとめる方針が示されています。
農家・JAの反応と懸念
一方、農家からは「生産調整がなくなるとコメを作ってきた基盤が一気に崩れる」という声が聞かれます。山形県の大規模水田を営むある農家は、「減反を前提に設備投資を抑えてきたため、突然生産量を増やすとなると苗代や肥料、機械の整備費用が膨れ上がり、経営が立ち行かなくなる」と訴えています。
また、JA(農業協同組合)関係者からは、「生産調整を廃止して増産に踏み切ると、JAの流通量が急増し、流通コストや貯蔵・品質管理の負担が増大する」「価格が暴落した場合、JAや農家の経営基盤が揺らぐ」との懸念が示されています。生産調整がなくなれば、JAがこれまで管理してきた在庫コントロール機能が後退し、流通網を再編成する必要が生じるため、現場レベルでの混乱も予想されます。
ただし、秋田県大潟村で「減反」反対を訴え続けてきた農業法人会長の涌井徹さんは、「異常気象やグローバルな需給変動に対応するには、サーカスの綱渡りのような微調整では限界がある。議論が動き出したこと自体は嬉しい」と歓迎しています。涌井さんによれば、「米価が高騰しているのは、需給調整に失敗し、結果的にコメの供給が追いつかなかったためだ」と指摘しており、「将来を見据えた安定供給モデルの構築が必要だ」と語っています。
歴史的視点:過去の生産調整見直しの経緯
実は、今回のような生産調整見直しの議論は、これまでにも何度か持ち上がってきました。1980年代後半、米余りが問題化した際には、国が国際協定(GATT/UR交渉)との関係で減反面積を削減しながらも、国内需給を維持する微調整が行われました。しかし、当時も「コメ農家の収入補償と需給安定の両立」は難しく、最終的に「生産調整+円滑な輸入枠管理」という形で折り合いをつけた経緯があります。
1995年以降、WTO体制下で農業交渉が本格化すると、日本は「生産調整に伴う補助金」がWTO協定で制限対象となり、徐々に減反政策に依存しづらくなる状況が生まれました。そのため、転作支援策や食味向上のための品種改良支援に移行し、コメ以外の作物やブランド化戦略が推進されました。しかし、2020年代に入り米価が再び上昇し始めたことで、「減反とブランド化の両立」が難しくなり、今回の見直しにつながっています。
社会経済的影響と今後の課題
生産調整見直しは、農家だけでなく流通業者、消費者、そして海外輸出市場にも影響を与えます。まず、流通業者側は「安定した供給量を確保できないと仕入計画が立てづらい」「急激な増産による一時的な供給過多は、市場価格の下落を招き、在庫評価損を生むリスクがある」といった懸念を抱えています。消費者側も「コメが供給不足で高値が続く」のと「価格が急落して農家疲弊」の二つのリスクに晒される可能性があり、政策決定には慎重さが求められます。
また、海外輸出を拡大する方針が示されていますが、日本産米のブランド価値を維持しつつ、海外消費者の嗜好に合った銘柄をどう開発・供給するかは大きな課題です。特に東アジア市場や北米市場では「和食ブーム」が続いているものの、現地のコストや物流網との競合が激化しており、日本産米が割高になりすぎると売れ行きに影響が出るリスクがあります。
さらに、中長期的には「人口減少」「家計の米離れ」「食の多様化」というマクロ的要因を無視できません。日本の年間コメ消費量はピーク時の2000年代初頭から減少傾向にあり、今後も数十年かけて縮小が続く見込みです。その中で「生産量を増やせば国内価格を下げられる」という単純な解決策だけでは、構造問題を根本的に解消できない可能性があります。若年層や都市部ではパンや麺類をはじめとする他の主食へのシフトが進んでおり、コメの需要低迷が今後も続くと予測されています。
地域別の影響と対応策
地域別に見ると、新潟・秋田・山形・北海道といった東日本や北日本の大規模産地は生産調整撤廃による「一気に増産した際のインフラ整備」が急務になります。これら地域では、大規模な農地や農業機械を持つ農家が多く、条件が整えば短期間で収穫量を増やすことが可能です。しかし、その一方で「急激な増産が流通を圧迫し、一時的に余剰在庫を抱えるリスク」や「品質管理コストが増大するリスク」もあります。
一方、西日本の中小規模産地では、「小規模の田んぼで多品種栽培を行い、地産地消や6次産業化を進める」動きが活発化しています。たとえば、岡山県や香川県では「ブランド米+加工品(米粉、和菓子等)の開発」で付加価値を高める取り組みが続いており、生産調整見直し後も「高品質・高付加価値路線」を維持することで生産継続を図ろうとしています。
北海道では、2025年産の生産目安が当初の計画から約1.7万トン増やされました。政府は備蓄米を買い戻す制度を強化し、米価下落リスクに備えるとともに、道内産米のブランド価値維持を図る方針です。ただし、北海道の夏季は寒暖差が大きく、米の品質維持にコストがかかることから、小規模農家の中には「増産しても取り組むインセンティブが乏しい」といった声も出ています。
今後の展望と政策提言
今回の生産調整見直しでは、短期的な米価安定策と中長期的な需要創出策を同時並行で進める必要があります。具体的には、①生産調整の撤廃に伴う所得補償制度の明確化、②備蓄米放出ルールの柔軟化、③農業インフラ(貯蔵施設・低温倉庫の整備)への投資拡充、④消費者向けの需要喚起キャンペーン(学校給食や外食産業との連携強化)などが考えられます。
また、気候変動に対応するためのスマート農業技術導入支援や、省力化・効率化を図るICT利活用が不可欠です。ドローンを使った農薬散布、自動走行コンバインによる収穫といった取り組みに対し、自治体やJAが補助金を手厚く提供することで、農家の負担軽減と品質向上を同時に実現できます。さらに、種子改良や耐病性品種の開発支援を強化し、突発的な天候リスクを軽減する体制構築も急務です。
食の多様化に対応するため、海外市場での販路開拓は喫緊の課題ですが、「日本食ブーム」に乗じて高付加価値米(ブランド米)の輸出拡大を狙う一方、大量消費国向けには「コメ粉」や「米由来の加工品」など加工食品の開発・供給を進めることが求められます。国内外の需要バランスを見極め、安定的かつ持続可能なコメ流通モデルを構築することで、将来的な価格の乱高下を抑えることが期待されます。
まとめ
今回の生産調整見直し議論は、「国内需要の低迷」「急激な米価高騰」「異常気象リスク」という三重苦に対する農政の対応として不可欠なものです。しかし、増産推進と価格安定、農家の経営維持という三者のバランスをどう取るかが最大の課題です。政府は2026年6月末までに具体的な制度設計を公表する予定ですが、その過程では「農家側の声」「流通業者の実情」「消費者ニーズ」とを丁寧にすり合わせる必要があります。
将来的には「単に生産量を調整する」のではなく、「気候変動に耐えうる生産基盤の強化」や「国内外需要の多様化に対応した付加価値創出」「スマート農業の普及」といった中長期視点での改革が求められます。コメ消費は徐々に減少しているものの、「日本の食文化の根幹」を支える作物である以上、その持続可能性維持は国策として死活的課題です。今後の農政改革が「日本のコメ作りを未来に繋ぐ」ものとなるよう、国民的な議論と理解が不可欠です。


コメント:0 件
まだコメントはありません。