筑波大 人文3学科を統合・再編へ
筑波大 人文3学科を統合・再編へ
2025/06/06 (金曜日)
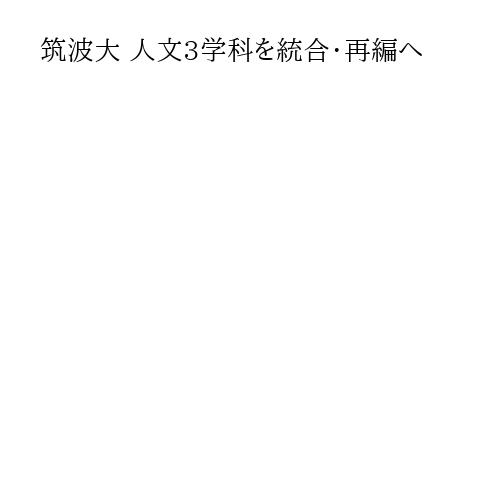
総合ニュース
筑波大、人文系組織を統合・再編へ 教員「縮小、質の低下」を懸念
筑波大が、三つある人文系の学類(学科)を2029年度に統合し、その上部組織である学群(学部)も改組する方針であることが、関係者への取材で判明した。中央教育審議会(文部科学相の諮問機関)は、少子化を理由に大学など高等教育機関の再編・統合が必要とする答申を2月にまとめており、国立大における先駆けになる可能性がある。一方で教員らからは「人文教育の縮小や質の低下につながりかねない」と反発する声も出ている。
はじめに
2025年6月、毎日新聞が入手した筑波大学の内部文書によると、人文・文化学群に属する「人文学類」「比較文化学類」「日本語・日本文化学類」の3学類を、2029年4月に統合し「人文学専門学群」として再編成する方針が示されました。この方針は、少子化の進行や大学再編・統合の国の方針を背景に打ち出されたものであり、学群・学類の再編を巡る議論は大学側と教員・学生の間で賛否が分かれています。この記事では、内部文書の内容を整理するとともに、日本の高等教育における人文学再編の背景・歴史的経緯、今回の再編案が抱える問題点や論点を解説します。
1. 内部文書の概要と再編案の内容
内部文書によれば、筑波大学は現行の人文・文化学群内にある以下3学類を統合し、2029年4月から「人文学専門学群」として一本化する計画を進めています。
- 人文学類
- 比較文化学類
- 日本語・日本文化学類
再編理由として文書はまず「少子化に伴う18歳人口減少」を挙げ、加えて「人文学を取り巻く課題」として以下の点を指摘しています。
- 専門分野の細分化が進み、学問領域同士の連携が困難になっている
- 学生や教員の理数・工学リテラシーが不足し、総合的な思考を養いづらい
- 社会や産業界と学術研究・教育の間に距離が生じており、実社会に即した学びが提供しづらい
その上で、「教養知(リベラル・アーツ)と専門知を両翼とする総合的人文学を学修する」カリキュラム構築を掲げ、「人文学専門学群」がすべての人文系科目を一元的に編成・提供することで、学内リソースを最適化し、社会との接続を強化するとしています。しかし、この方針は24年2月頃から検討が始まり、25年3月には教員の審議を経ずに上層部から「報告事項」として通達されたため、一部教員や学生の間で強い反発が起きています。
2. 少子化と大学再編の国の方針
日本は1990年代後半から少子化が顕著となり、18歳人口(大学進学年齢)が減少し続けています。文部科学省の統計によれば、18歳人口は2000年の約2,000,000人をピークに減少し、2025年以降は年間約1,100,000人前後にまで落ち込むと予測されています。この人口構造の変化を踏まえ、中央教育審議会(中教審)は2025年2月に「高等教育機関の適正規模化・再編統合を促進すべき」との答申をまとめました。その中で、中教審は以下の点を指摘しています。
- 18歳人口の減少に対応し、大学の過剰供給を是正する必要がある
- 大学間の横断的連携や統合を支援し、地域ごと・学術分野ごとの最適規模を確立すべき
- 特に少子化で入学者数が激減する文系人文学系の特異な課題に配慮し、再編・統合を促進する必要がある
こうした国の方針を受けて、全国の国公私立大学で学部・学科の再編が相次いで検討されるようになりました。とりわけ人文・社会系学部は入学者減少の影響を受けやすく、学科や専攻が統廃合される例が増えてきました。筑波大学の今回の再編案も、この国の再編方針と不可分の関係にあります。
3. 国内の人文学教育における再編の歴史的経緯
日本の大学における人文学系学部は戦後すぐから整備が進み、1950年代~60年代にかけて「文学部」「教育学部」「法学部」「経済学部」などが各地の国公立・私立大学に新設されました。特に文学部は、哲学・史学・文学・言語学・芸術学など人文諸分野を総合的に学ぶ場として位置づけられました。
1970年代以降、学問分野は細分化が進み、「史学」「哲学」「文学」「民俗学」「比較文化学」など専攻が多岐に分化しました。加えて1980~90年代にかけて国際化が進展すると、「比較文学」「比較文化」「国際日本学」などの領域が誕生し、多くの学部でカリキュラムが増設されました。
21世紀に入るとグローバル化と情報化が加速し、従来型の学問が社会や産業界と乖離しやすくなる問題が浮上します。そのため、2000年代末から「リベラル・アーツ教育」や「学際融合プログラム」が提唱され、人文学系学部も従来の「細分化した学問分野」を超えて横断的に学ぶ取り組みが始まりました。しかし、少子化の影響で入学定員を満たせず、多様な専攻を維持し続ける経営的難しさが顕在化し、2010年代後半から大学再編・統合の議論が活発化しました。
4. 筑波大学における人文・文化学群の沿革
筑波大学は1973年に「東京教育大学」から改組されて開学し、従来の教育学部に加え、学際的な教育・研究を進める「学群制」を採用したことで知られています。1975年には人文・文化学群が設置され、以下の3学類で教育を行ってきました。
- 人文学類:哲学・歴史学・美学・文学・考古学など、伝統的な人文学分野を網羅
- 比較文化学類:複数の文化圏を横断的に比較し、国際理解やグローバルな視点を養う
- 日本語・日本文化学類:日本語学・日本文学・日本文化史・民俗学など、日本固有の言語・文化研究に特化
これらの学類は、共通基盤として教養科目を横断的に学ぶ「共通教育センター」と連携しつつ、人文学系の専門科目を提供してきました。学群制の特徴として、「幅広い教養教育を通じて多様な学問領域を横断的に学ぶ」「専門分野に特化した教育も同時に行う」があり、文理融合や学際的研究を推進する拠点となっていました。しかし、2010年代後半以降は入学者数が減少し、各学類の定員割れが顕在化してきました。
2024年2月頃から始まった再編検討では、学内アンケートや試算を含むデータを基に、「入学志願者数の減少」「教員数の減少予測」「学類ごとの教育・研究テーマの重複」などが分析されました。これを受けて再編案では、3学類を統合しリソースを一元化することで、教育プログラムの再構築や教員配置の効率化を図る意図があります。
5. 再編に対する教員・学生の反発と懸念
今回の再編案に対し、複数の人文学系教員からは以下のような強い反発が報告されています。
- 「専門分野が細分化されてきた歴史を無視し、一括統合することで教育の質が低下する」
- 「数百人規模の一律講義ばかりになり、少人数ゼミやハンズオンの指導が困難になる」
- 「人文学は独自の教育手法を持つが、それが失われる恐れがある」
- 「学生や現場教員の意見を無視し、上層部の一方的な決定である」
- 「学際的な教育を推進するという名目だが、実際には学類を減らすだけの経費削減策に過ぎない」
ある教員は「人文学には独自のカリキュラム構築や実地研究、フィールドワークなどの特有の授業スタイルがある。これを維持せずにマスプロダクションのような大規模講義に変えてしまえば、学生が深く学べる機会が失われる」と懸念しています。さらに、2025年3月に「報告事項」として再編計画が提示された際には、教員組合・学生自治会の一部が抗議の声を上げ、学内集会や署名活動を行いました。
学生からも「専門分野を深めたいのに、複数分野を統合したコースでは学びの軸がぶれてしまう」「教員との距離が遠くなり、就職支援やキャリア形成の相談がしづらくなる」との不安の声が上がっています。こうした反発が広がり、大学側は「正式決定前に学内説明会をさらに実施し、懸念に答える」と表明していますが、学生・教員の信頼回復には時間がかかると見られます。
6. 文部科学省・中教審の大学再編支援策
中教審の答申を受けて、文部科学省は2024年度から以下のような再編支援策を打ち出しています。
- 大学再編・統合支援交付金:複数大学の統合や学部再編を行う際に、設置法人に対する交付金や補助金を拡充
- 定員調整・定員管理の緩和:少子化で志願者が減少する学部・学科に対し、定員割れであっても一定期間は減収ペナルティを回避できる特例措置
- 地域貢献連携拠点の指定:人口減少地域や過疎地域において、大学・専門学校・企業・自治体が連携して教育プログラムを提供するための連携拠点設置を支援
これにより、大学は一定の再編・統合コストを軽減できるメリットがありますが、一方で、支援策に頼りすぎると「再編ありきの計画」に偏る危険性も指摘されています。特に人文・社会系学部では「支援金目当てで安易に統合を進めると、研究基盤が損なわれる」との危惧が根強く残っています。
7. 大学再編と地域社会への影響
大学再編は単に教育機関の内部構造を変えるだけでなく、地域社会や地方経済にも大きな影響を及ぼします。筑波大学の場合、茨城県つくば市や周辺地域においては、学生や教職員の消費活動が地域経済を支えています。学類・学群が統合されて学生数が減少すると、以下のような影響が考えられます。
- 学生街の衰退:同キャンパス周辺の飲食店・アパート・書店などの売上減少が懸念され、雇用や地元商店の経営が苦境に立たされる可能性。
- 地域文化活動の縮小:人文学系の研究者が地域の文化イベントやシンポジウム、公開講座を企画・運営してきた実績が、学類統合で教員数が減ることで減少し、地域住民が学べる機会が失われる。
- 自治体との連携機会減少:筑波大学は「茨城県つくば市との連携」の拠点的役割を担っており、地域活性化プロジェクトや産官学連携事業が活発に行われてきた。しかし、人文学系学群の規模縮小によって協働可能なリソースが減少し、地域振興への貢献度が低下する恐れがある。
このため、地域住民や自治体の一部からも「大学の存在は地域の文化的拠点でもある。再編で人文学教育が弱体化すれば、地域の文化振興にも深刻な影響が及ぶ」との声が上がっています。大学側は地域連携を重視する姿勢を打ち出していますが、再編後の具体的な取り組みについては未だ詳細が示されておらず、地域との協議も急務とされています。
8. 海外の事例に見る学際再編の成功例と課題
日本だけでなく、欧米やアジアの先進大学でも学部・学科の再編は進んでいます。例えば、アメリカの一部大学では従来の「リベラル・アーツカレッジ」や「文理両学部」を統合し、「College of Arts and Sciences(文理融合カレッジ)」として一元化するケースが増えています。こうした再編のねらいは以下の通りです。
- 学際的プログラムの強化:文系・理系の枠を超えたプログラム設計により、学生が多角的な視点で問題解決能力を養う。
- 教育・研究リソースの効率化:図書館やラボ、教員人件費などを包括的に管理することで、コスト削減やシステム化を図る。
- グローバル競争力の向上:世界大学ランキングなどで評価されやすい「学際研究」「インターナショナルリサーチセンター」を再編後の学部横断的に展開する。
一方で、欧米の再編事例にも課題はあります。学部間のカリキュラム整合性が不十分で学生が混乱するケースや、特定分野の研究が地位を失い、若手研究者の進路選択を狭める事例が指摘されています。また、教員の所属意識が低下し、研究活動や教育活動に影響が出ることも報告されています。これらの経験から、日本の筑波大学でも「学際融合」という理想を掲げるだけでなく、具体的な教育・研究プログラムの設計や教員配置、人員育成の仕組みを慎重に検討しなければ同様の課題を抱えかねません。
9. 教育の質と学問の自由をめぐる懸念
今回の再編案に対して、教員や学生から特に強い懸念が寄せられているのが「教育の質」と「学問の自由」の問題です。以下のポイントがしばしば挙げられます。
- 少人数ゼミ・個別指導の減少
人文学系では伝統的に「少人数ゼミ」「演習授業」「個別指導」が教育の要であり、学生と教員が直接対話しながら批判的思考を磨くことが重視されてきました。しかし、統合によって大規模講義中心のカリキュラムに変更されると、学生が主体的に議論に参加する機会が減少し、学びの深度が低下する懸念があります。 - 学際研究・専門分野の消失
細分化された人文領域(哲学、史学、文学、言語学、民俗学など)が一元化されることで、専門研究者が所属学類を失い、地域研究やフィールドワーク、人文情報学など個別テーマごとの研究環境が危機に晒される可能性があります。学問の自由を尊重し、多様な研究プロジェクトを支援する仕組みが維持されなければ、日本の人文学研究全体が後退しかねません。 - 学費負担の増加リスク
統合後のカリキュラム刷新に伴い、実習費用や図書購入費用などが増える場合、学生の経済負担が増すことが予想されます。とくに文系学生はアルバイト収入に頼る傾向が強く、学費外の負担が重くのしかかると、ドロップアウトや就学継続の意思決定に影響を及ぼす可能性があります。 - 学生・教員の声の反映不足
筑波大学では伝統的に「学内自治」を尊重し、学科運営委員会や大学評議会に学生・教員が参加し、カリキュラムや規程変更を協議してきました。しかし今回の再編案は、「報告事項」として一方的に伝えられた背景があり、学内ガバナンスを軽視しているとの批判が上がっています。大学運営における透明性や説明責任を果たすためには、再編案の詳細を公表し、教職員・学生からのフィードバックを十分に取り入れるプロセスが不可欠です。
これらの懸念を放置したまま再編を強行すれば、「学生が人文学を学ぶ意義を見失う」「人文学系教員が育成されず、研究者・教育者の道を閉ざされる」といった深刻な学術的後退を招く恐れがあります。
10. 今後のスケジュールと予測される議論の行方
筑波大学側は、2025年中に文部科学省に再編計画書を正式提出し、文科省と協議しながら認可を得るプロセスを踏む見込みです。一般的に大学学部・学科改組には以下のステップが必要となります。
- 学内ガバナンス機関(学群長会議、学群運営委員会、大学評議会など)での議論・承認
- 学則改定やカリキュラム編成会議を経て、教育課程を再設計
- 文部科学省への届出・認可申請
- 学生募集要項の改訂・入試制度の変更(2028年度入試情報の公表など)
- 2029年度(2029年4月)から新組織による教育・研究活動を開始
現状では、学内の議論が不十分なまま再編案が“報告”され、さらなる議論の場が制限されているため、学内ガバナンスをどう確保するかが最大の焦点と言えます。学内外からは「再編案の詳細な影響試算(カリキュラム変更による学生負担増減や教員配置シミュレーションなど)を公開し、説明責任を果たせ」という声が高まっています。
また、文部科学省側は全国の大学再編状況を注視し、「大学設置・学校法人審議会」で審査を行いますが、設置審査委員会の意見や助言を踏まえた上で認可するため、最終的に再編が認可されるかどうかは不透明です。仮に再編が見送られた場合、人文・文化学群は従来の3学類を維持しつつ、別の経営改善策が検討されるでしょう。例えば、カリキュラム刷新による学類間連携の強化や、地域連携プログラムの拡充、オンライン教育の導入によるコスト削減などが考えられます。
11. まとめ
筑波大学が計画する「人文学専門学群」への改組は、少子化に伴う大学再編の潮流と、中教審の答申に基づく国の方針を受けた動きです。大学全体の教育・研究リソースを最適化しようという狙いは理解される一方で、学問の自由や教育の質、地域社会への貢献をどう確保するかが大きな課題となっています。
歴史的に日本の人文学系学部は、各専門分野の細分化と学際融合を繰り返しながら発展してきました。その中で、少数精鋭型のゼミや演習授業が人文学教育の根幹を支えてきた面があります。今回の再編案では、この伝統的教育のスタイルが“大規模講義中心”に移行する懸念が強まっており、教員・学生からは「学びの深度が失われる」「多様な研究テーマが埋没する」との反発が出ています。
大学再編は、経済的・制度的には必然であり、他大学でも同様の動きが見られます。ただし、学内ガバナンスを無視した急速な統合は、教職員・学生の信頼を失う危険性があります。今後は、以下の点を踏まえた慎重な対応が求められます。
- 再編案の詳細な影響試算データを公開し、学内外での透明性を確保する
- 学生・教員の意見を収集するための公聴会や説明会を適切に開催する
- 地域連携や産学連携の視点を取り入れ、地域社会への貢献を維持・強化する
- 少人数ゼミやハンズオン型授業など、人文学の特徴的教育スタイルを維持する仕組みを構築する
筑波大学は、国内でも先駆的な学群制を採用し、学際融合教育のモデル校として評価されてきました。今回の再編案が「人文学の真価を高めるもの」として実を結ぶかどうかは、学内外のステークホルダー(教員・学生・地域社会・文科省)が連携し、「教育の質」と「学問の自由」をいかに両立させるかにかかっています。今後の動向を注視するとともに、学内ガバナンスを十分に発揮し、建設的な議論が行われることが期待されます。


コメント:0 件
まだコメントはありません。