女性地方議員53%が嫌がらせ被害
女性地方議員53%が嫌がらせ被害
2025/06/06 (金曜日)
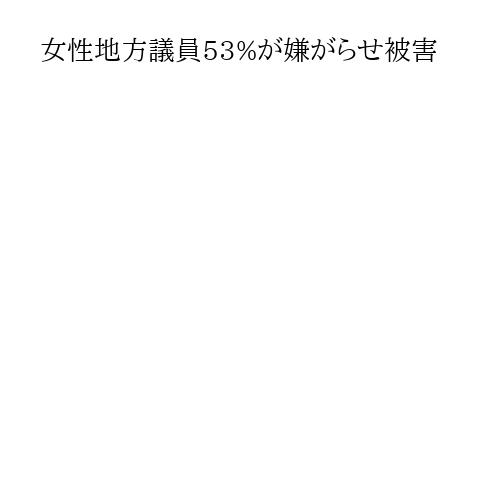
総合ニュース
女性地方議員53%が嫌がらせ被害 男性の4割「見聞きもせず」 内閣府調査
内閣府は6日、「女性の政治参画への障壁等に関する調査研究報告書」を公表した。
地方議会議員への調査で、自身や家族らが嫌がらせを「受けた」と答えた女性は53.8%で、男性(23.6%)の2倍強に上った。嫌がらせを「受けたことも見聞きしたこともない」と回答したのは女性19.5%、男性41.0%だった。
調査は昨年11月から12月にかけて全国の地方議員を対象に実施し、5075人から回答を得た。議員や候補者へのハラスメント防止策を盛り込んだ「政治分野における男女共同参画推進法」改正法の2021年6月の施行後も依然、嫌がらせなどが女性の政治参画の障壁となっている現状が浮き彫りとなった。
嫌がらせの内容は、男女ともに「暴力的な言葉」が最多。「性別による無意識の思い込みから来る侮蔑的な態度や発言」や「身体的な接触や付きまとい」は女性の被害が男性に比べて顕著に多かった。女性議員への嫌がらせ行為者は「他の候補者やその支持者、同僚議員」が65.7%でトップ。「有権者」が64.0%と続いた。
要約
内閣府が2025年6月6日に公表した「女性の政治参画への障壁等に関する調査研究報告書」によると、地方議会議員を対象としたアンケートで、女性議員の53.8%が自身や家族が「嫌がらせを受けた」と回答し、男性の23.6%を大きく上回りました。一方、「嫌がらせを受けたことも見聞きしたこともない」と回答した女性は19.5%、男性は41.0%でした。嫌がらせの内容としては男女とも「暴力的な言葉」が最多で、女性では「性別による無意識の思い込みから来る侮蔑的な態度や発言」「身体的な接触や付きまとい」といった被害が顕著でした。行為者としては「他の候補者やその支持者、同僚議員」が65.7%、「有権者」が64.0%と並びます。2021年6月施行の「政治分野における男女共同参画推進法」改正にもかかわらず、女性へのハラスメントが依然として大きな障壁であることが明らかになりました。
1. 女性の政治参画の歴史的背景
日本における女性の選挙権は1945年に初めて認められ、1946年4月には約39%の女性が衆議院議員選挙に投票しました。1950年代から高度経済成長期にかけて国政・地方政治の場に女性議員が少しずつ増えていきましたが、総じて男性議員に比べて数は少なく、「婦人参政権」の実現当初の熱気は徐々に薄れていきました。
1970年代に入ると国際的な女性の地位向上の動きや国内の男女雇用均等法(1986年施行)などを背景に、女性議員が少しずつ増加します。しかし1990年代以降も女性議員の割合は一桁台にとどまり、ジェンダーギャップ指数でも日本は先進国の中で最低水準に位置していました。2000年代に入り、地方議会でのクオータ制導入や、政治分野における男女共同参画推進法(2003年制定)の成立などによって、女性候補者支援や啓発が強化されました。それでも地方議会に占める女性割合は2024年時点で16%前後にとどまり、欧米諸国と比較すると依然として低い状況が続いています。
2. 嫌がらせ被害の実態と内容
今回の調査では、男女別に「嫌がらせを受けたことがあるか」「見聞きしたことがあるか」を問うたところ、女性は53.8%が「受けた」と回答し、男性(23.6%)の約2.3倍にこの割合が達しました。さらに「受けたことも見聞きしたこともない」と答えたのは女性19.5%に対し男性41.0%という結果でした。
嫌がらせの具体的な内容としては以下の項目が挙げられています。
- 暴力的な言葉:男女とも最多の回答項目で、議会や街頭演説の場で大声で罵倒されたり、罵詈雑言を投げかけられたりする事例が多い。
- 性別による無意識の思い込みから来る侮蔑的な態度や発言:「女性だから議論能力が低い」「家庭に入るべきだ」といったジェンダー・ステレオタイプに基づく差別的発言が女性に集中している。
- 身体的な接触や付きまとい:演説中や街宣カーから降りる場面で、腕をつかまれたり、後をつけられたりといった身体的嫌がらせが女性の方が顕著。
- 中傷を目的としたデマやSNS上での誹謗・中傷:ネット上で女性議員を標的とした偽情報や侮辱コメントを拡散されるケースも増加しており、精神的ダメージが深刻。
これらの嫌がらせは、男性議員でも受けることはあるものの、女性議員の方が「身体的接触」「性差別的な侮蔑発言」「ネット上の誹謗中傷」など性別に根ざす攻撃をより多く受けている点が浮き彫りになりました。
3. 嫌がらせ行為者とその背景
嫌がらせ行為者として最も多かったのは、「他の候補者やその支持者、同僚議員」(65.7%)で、次いで「有権者」(64.0%)が続きました。この結果は以下のように考えられます。
- 政局的な対立構造の中での攻撃:同じ選挙区内で競合する候補者や支持者が、相手候補の女性議員に対して「失言を拡大解釈してネットに拡散」「選挙演説中に妨害行為を行う」など、政治目的での嫌がらせ行為を行う場合がある。
- 有権者の中に根強く残る性差別的意識:有権者からの嫌がらせは、「女性に政策を決める能力はない」といった偏見に基づき、街宣時に大声で差別的な発言を浴びせたり、SNSで誹謗中傷を行ったりするケースがある。
- 同僚議員からの無意識的な差別:議会の慣習として、女性議員が発言する際に遮られたり、発言後に「大丈夫か?」といった同情的・保護的な態度を示されたりすることで、自尊心を傷つけられる事例も多い。
こうした嫌がらせ行為は、女性が政治の世界に進出しにくい大きな障壁となり、「辞める理由」「立候補をためらう要因」として作用しています。実際、報告書でも「女性候補者の約6割が立候補を断念する要因として、政治活動中の嫌がらせや暴言を挙げている」とのデータが示されています。
4. 法改正と現状の課題
2021年6月に改正施行された「政治分野における男女共同参画推進法」では、ハラスメント防止策を強化し、国政や地方議会でジェンダーに基づく暴言・妨害行為を罰する仕組みが盛り込まれました。主なポイントは以下の通りです。
- ハラスメントの定義拡大:政党活動や選挙運動を含む政治活動での嫌がらせ行為を「ハラスメント」に位置付け、違反行為を行った個人や団体に対し、罰則や指導措置を講じる。
- 相談窓口の整備:各都道府県や市町村に「政治分野におけるハラスメント相談窓口」を設置し、被害を受けた女性議員が気軽に相談できる体制を構築する。
- 研修や啓発活動の強化:選挙管理委員会や自治体が主催する研修で、男性議員や選挙スタッフを対象に「男女共同参画教育」を実施し、無意識バイアスやジェンダー差別をなくす意識改革を促す。
しかし、今回の調査結果からわかるように、法改正だけではハラスメントの実態を十分に是正できていません。主な課題としては以下の点が挙げられます。
- 抑止力の弱さ:ハラスメント行為があっても罰則が実際に適用されるケースが少なく、行為者に対する実効的な制裁が機能していない。
- 相談窓口の利用促進不足:女性議員自身も「相談しても事態が改善しない」という不信感から相談窓口を利用しないケースが多く、被害が見過ごされがちである。
- 男性議員の意識変革が進まない:同僚議員による無意識バイアスに基づく発言や態度が依然として常態化しており、ジェンダー差別を自覚しないまま女性議員を排除するような言動が続いている。
- 有権者教育の欠如:政治活動中の有権者による暴言・妨害行為を抑止するための教育・啓発が地域レベルで十分ではなく、投票行動や政治参加への理解が不十分なままになっている。
5. 過去の女性政治参画支援策と成果・限界
これまでにも、女性政治参画を促進するための取り組みはいくつか行われてきました。
5.1 クオータ制の導入・検討
地方議会や政党レベルで、女性候補者を一定割合確保する「クオータ制度」を導入する動きがありました。たとえば、いくつかの政党では公認候補者のうち女性割合を30%以上とする目標を掲げています。しかし、制度として義務化されていないため「形骸化している」「実効性が薄い」との批判があり、女性当選者数の増加にはつながりきっていません。
5.2 女性候補者支援研修・ネットワーク形成
女性議員や市民団体が主催する研修や政策勉強会が各地で開催され、「立候補の手続き」「政策立案のノウハウ」「メディア対応術」などを学ぶ機会が増えました。また、女性議員同士のネットワークを構築することで、孤立しがちな女性議員に精神的支援を行う活動も進んでいます。しかし、地方部などでは研修参加が困難なケースもあり、地域格差が生じているのが現状です。
5.3 国際的な比較と日本の立ち遅れ
欧米諸国では、ノルウェーやスウェーデンなど北欧諸国がクオータ制を法制化し、議会における女性議員の割合を50%近くに高めています。また、アメリカやイギリスなどでも女性議員のネットワーク強化や資金援助プログラムが充実しており、政治家としてのキャリア形成が支援されています。これに対し、日本は女性議員の割合が国会で10%前後、地方議会で15%前後にとどまっており、国際的に見て立ち後れた状況が続いています。
6. 今後の展望と提言
6.1 ハラスメント対策の強化と実効性向上
女性議員への嫌がらせを早期に発見し、行為者に対する制裁を迅速に行うためには、以下の対策が求められます。
- 専任の相談窓口と緊急対応チームの設置:地方議会ごとに専任のハラスメント相談員を配置し、被害通報から調査・対応まで迅速に行うチームを設置する。
- 匿名通報システムの導入:議員個人のプライバシーを守りながらハラスメントを報告できる匿名通報システムを整備し、被害が顕在化しなくても早期に発見・対処できる仕組みを構築する。
- 行為者へのペナルティ強化:具体的な法的罰則や議会での懲罰規定を明確化し、暴言や身体的嫌がらせを行った行為者に対して罰則を科すことで抑止力を高める。
6.2 教育・啓発活動の充実
有権者や同僚議員に対して、以下の教育・啓発が必要です。
- 有権者向け政治リテラシー教育:中学校・高校などで「政治参加の意義」「選挙活動中のマナー」などを市民教育カリキュラムに組み込み、有権者の理解を深める。
- 同僚議員へのジェンダー研修:議会運営委員会が中心となり、全議員を対象にジェンダー意識改革を図る研修を定期開催し、無意識バイアスを払拭する。
- メディア向けガイドライン作成:新聞社やテレビ局が政治報道において「性別を過度に強調しない」「誹謗中傷を助長しない」などのガイドラインを整備し、取材・報道の段階からハラスメント的表現を排除する。
6.3 女性候補者の支援策拡充
女性が立候補しやすい環境を作るため、以下の支援策を強化すべきです。
- 経済的支援の拡大:女性候補者が選挙運動資金を確保しやすいよう、公的な選挙奨励金や助成金制度を充実し、候補者間の経済格差を是正する。
- 子育て支援の充実:地方議会が育児休業制度を整備し、乳幼児の託児サービスを提供するなど、子育て中の議員が活動を継続しやすい仕組みを導入する。
- ロールモデルの可視化:成功している女性議員や候補者の事例を積極的に紹介し、「女性も政治で活躍できる」というメッセージを社会に広める。
7. まとめ
内閣府の調査から明らかになったとおり、地方議会において女性議員は男性議員と比べて深刻な嫌がらせ被害を受ける傾向が顕著です。2021年の「政治分野における男女共同参画推進法」改正後も、実効性のあるハラスメント対策や相談窓口の整備が不十分であり、女性議員が安心して活動できる環境はまだ整っていません。
歴史的に見ても、女性の政治参画は徐々に進展してきたものの、依然として欧米諸国と比べると低い水準にとどまっています。今後は、ハラスメント対策の強化、教育・啓発活動の充実、女性候補者支援の拡充という三つの柱を軸に、地方自治体や政治家、メディア、教育機関が連携して取り組みを進める必要があります。
消費者としての有権者やメディアも、女性議員に対する差別的発言や誹謗中傷を許さず、建設的な議論を行う意識を持つことが重要です。これらの対策を総合的に推進することで、女性が安心して政治に参画できる環境を整え、ジェンダー平等な社会を実現することが期待されます。


コメント:0 件
まだコメントはありません。