病院で取り違え「親」さがし20年
病院で取り違え「親」さがし20年
2025/06/28 (土曜日)
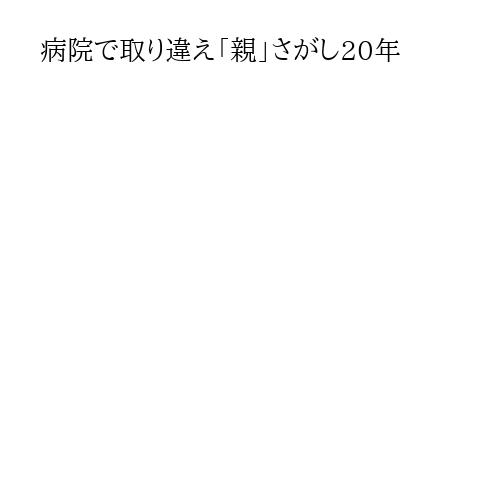
67年前に病院で取り違え“生みの親”捜し続けた男性の20年「真実を知りたい。父母のヒストリーを聞きたい」【news23】
67年前の取り違えから20年──“生みの親”捜し続ける男性が見つめる真実と社会の課題
1958年、東京都立墨田産院で誕生した江蔵智さん(67)は、生後まもなく別の新生児と取り違えられ、実の両親とは別の家庭で育てられた。2004年に始まった賠償請求訴訟で過失を認定され、2005年には都から2000万円の支払いを勝ち取ったが、生みの親が誰か、どう過ごしてきたかを知る機会は得られなかった。江蔵さんは「真実を知りたい。父母のヒストリーを聞きたい」と願い、2021年に“出自を知る権利”を根拠に都に調査を求める第二の訴えを起こした。4月21日、東京地裁は初めて都に対し生みの親捜しへの協力を命じる判決を言い渡した。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
判決の意義と法的論点
地裁判決は「出自に関する情報は個人の重要な歴史的事実であり、憲法13条が保障する人格的生存にかかわる」と評価。さらに、「子どもの権利条約」が保障する出自を知る権利も日本国内で認められていると指摘した。しかし、具体的な国内法は未整備のため、判決はあくまで都に調査実施の法的義務を課す形にとどまった。従来、出生届と戸籍は家族関係を確定する行政手続きであり、ミスが生じた場合の救済規定が不十分だった点を浮き彫りにした。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
取り違え事件の背景と全国の事例
戦後まもないころ、全国の産院や病院では新生児の管理体制が今よりずさんで、誤って取り違えられるケースが複数報告された。出生直後の保育室は人員不足や記録管理の不備が原因とされる。2004年には兵庫県でも同様のケースが発覚し、被害者が生物学的親捜しを求めて訴訟を起こした事例がある。いずれもDNA鑑定技術が普及する前の出来事だったため、判決や救済は限定的だった。
20年にわたる捜索の歩み
江蔵さんは2004年の初訴訟後、戸籍受附帳や診療録の開示を求め続けたが、診療記録は廃棄され、戸籍情報は黒塗りのまま公開が阻まれた。2016年には都に交渉窓口を設置させたが協力は得られず、苦難の捜索が続いた。2004年時点で血液型の不一致に気付くも、助産師の聞き取りや職員の証言では確証に至らず。2016年に区役所から戸籍情報の一部公開を得たことで、初めて取り違えの事実を裏付けられたという。
DNA鑑定と技術的進展
現在はDNA型鑑定技術が高度化し、わずかな毛髪や唾液痕でも親子関係を確定できる。海外では出生取り違え後の無償鑑定支援制度を整備する国もある。しかし日本ではDNA検査は任意・有料であり、公的補助が乏しい。判決後、江蔵さんは都から調査が進むまで自費でのDNA検査を準備すると明かしている。
行政記録管理の課題
医療記録の保存期間は法律で最長10年程度と定められ、今回のような事案では証拠が残らない。2023年公布の医療法改正では「電子化記録の長期保存」を義務付けたが、旧データの再構築は困難だ。裁判所は今回、分娩助産契約を根拠に都に録の探索義務を認めたが、全国の自治体や医療機関のガイドライン整備が急務となっている。
倫理・プライバシーの調整
生みの親が高齢化・他界している可能性や、成年した被養育者のプライバシー保護も論点だ。調査が遅れると、実の母や父の記憶を聞き取る機会を失いかねない。判決は「親子の情報は私的情報に当たるが、その開示には公益性が上回る」と判断したが、個人情報保護法とのバランス調整も求められる。
社会的インパクトと今後の展望
今回の判決は、出生取り違え事案で行政に調査を命じた初例として大きな意義を持つ。法整備が追いつかない分野で司法判断が先行する形となり、今後は「出自を知る権利」を具体化する法制度創設が課題だ。厚生労働省は2025年度内にガイドラインを策定し、取違い防止策や遺失記録の保管延長を検討すると表明している。
まとめ
67年前の産院での取り違えから20年以上にわたり、生みの親捜しを続ける江蔵智さんの姿は、被害者の苦悩と「出自を知る権利」の重要性を強く示す。東京地裁判決は都に調査義務を課し、法制度の空白を司法判断で埋めた画期的なものだ。しかし、医療記録の廃棄、家族登録制度の限界、プライバシー保護と公益の調整など、解決すべき課題は多い。今後は、出生記録の電子保存期間延長や公的DNA検査支援制度、出自を知る権利を明文化する立法措置が求められる。江蔵さんの願い──「母の思い、私の願いをかなえてほしい」──を実現するため、行政・医療機関・立法府が連携し、同様の苦しみを抱える当事者を救済する仕組み作りを急ぐ必要がある。


コメント:0 件
まだコメントはありません。