リンゴ病患者が過去最多 妊婦注意
リンゴ病患者が過去最多 妊婦注意
2025/07/01 (火曜日)
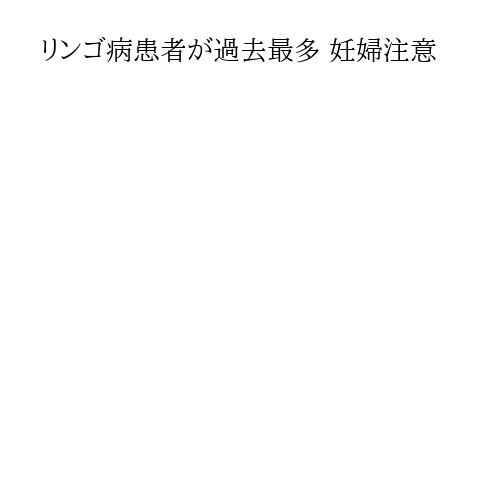
国立健康危機管理研究機構は1日、全国の定点医療機関から6月16~22日に報告された伝染性紅斑(リンゴ病)の患者数(速報値)が5943人で、1機関当たり2.53人だったと発表した。感染症法に基づく集計
伝染性紅斑(リンゴ病)流行報告とその背景・歴史・対応策
国立健康危機管理研究機構は2025年7月1日、全国の定点医療機関から6月16~22日に報告された伝染性紅斑(通称リンゴ病)の患者数が5,943人、1機関あたり2.53人だったと速報値を公表した。小児を中心に春から初夏にかけて流行するこの疾患は、パルボウイルスB19による飛沫・接触感染症であり、定点報告が流行把握の要となっている。
1. 伝染性紅斑とは
病原体と感染経路
伝染性紅斑の病原体はパルボウイルスB19。潜伏期間は4~14日程度で、主に飛沫感染のほか、唾液や接触を介して感染する。患者が発疹期に入る前後にウイルス排出が最も多く、発疹出現後は免疫によって排泄が急減する。
主な症状
- 顔全体に赤いチーク様紅斑(“リンゴ病”の由来)
- その後、四肢にレース状の発疹が拡大
- 微熱、頭痛、関節痛、リンパ節腫脹などの全身症状を伴う場合も
2. 流行状況と季節性
伝染性紅斑は年によって流行規模が異なるが、日本では4~6月に患者数のピークを迎えることが多い。特に学童期(5~10歳)の子どもに高い発症率を示し、幼稚園・小学校での集団感染が報告されやすい。最新の6月16~22日速報では、前週(6月9~15日)の1機関当たり2.10人から増加傾向にある。
3. 過去の大規模流行と歴史
過去30年で大規模流行となった例を振り返ると:
- 1996年:全国的に1機関あたり4人超の猛威(WHO報告)
- 2006年:学童集団感染が各地で発生、8000人超の報告
- 2015年:全国定点で再び大流行、病院外来受診者が急増
これらの流行期はいずれも冬から春にかけて感染者が蓄積され、翌年の春に一気に拡大する特徴がある。学校保健法による出席停止期間は発疹出現から5日または解熱後2日間であり、流行抑制の一助となっている。
4. 診断・治療・予防
診断方法
- 臨床所見:典型的な“両頬チーク紅斑”とレース状発疹
- 血清学的検査:パルボB19抗体(IgM陽性で急性期診断)
- ウイルスDNA検出:重症例や妊婦例でPCR検査が行われる
治療の基本
特効薬はなく、対症療法が中心。解熱鎮痛剤や関節痛緩和薬を用い、多くは数週間で回復する。ただし、免疫不全者や重症貧血を伴う患者は輸血や免疫グロブリン投与が必要となる。
予防策
- 手洗い・咳エチケットの徹底
- 学童施設での発疹例発生時の速やかな出席停止
- 妊婦は特に注意:胎児水腫や流産リスクがあるため、発疹期の接触を避ける
5. 公衆衛生対策と報告制度
伝染性紅斑は感染症法に基づく5類感染症に指定され、全数把握は不要だが、定点医療機関による週報告で流行状況を把握する。保健所は流行警報の発出や医療機関・学校への注意喚起を行い、さらに地域内での集団感染が疑われる場合は調査・対策を実施する。
6. 海外の流行動向との比較
米国CDCや欧州CDCの報告によると、北半球では春季に流行し、報告ピークは4~5月。症状や重症化リスクは日本と同様で、特に欧州では妊婦管理ガイドラインが充実している点が特徴的だ。
まとめ
2025年6月16~22日の定点報告で伝染性紅斑患者数が過去数年と比較して増加傾向にあるのは、春季から初夏にかけての流行期に入ったことを示すシグナルである。主に学童期の小児を中心に集団感染が発生しやすい疾患であるため、学校・家庭・医療機関が連携し、早期発見・出席停止・手洗い・咳エチケットなどの基本的対策を徹底することが重要だ。妊婦や免疫不全者への適切な情報提供と保護も不可欠であり、引き続き定点報告による監視と地域での感染対策強化が求められる。


コメント:0 件
まだコメントはありません。