悪質ひきこもり支援で被害 実態は
悪質ひきこもり支援で被害 実態は
2025/06/08 (日曜日)
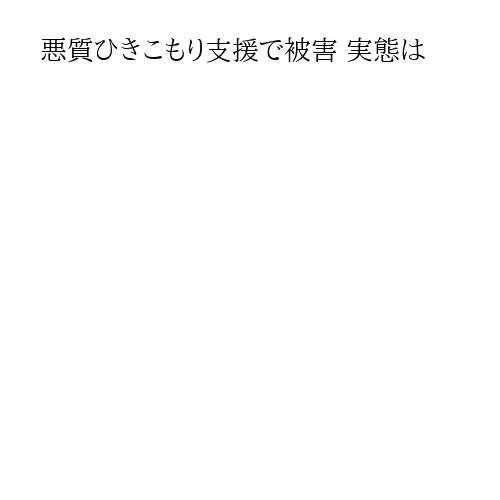
総合ニュース
引きこもりの自立支援をうたう“引き出し屋”強引に連れ出し施設に閉じ込める悪質業者も 人権侵害を受けた当事者と悩む母親の葛藤
はじめに
「引きこもり」の若者が社会復帰を目指す中で、近年「引き出し屋」と呼ばれる民間業者が自立支援をうたって注目を浴びています。しかし、一部には本人の意思を無視して強引に自宅から連れ出し、施設に監禁同然の環境に置く悪質業者も存在し、人権侵害が深刻化しています。本稿では、引きこもり支援の歴史と制度、引き出し屋の成立背景と手法、被害事例や法的課題、当事者と家族の葛藤、そして今後求められる支援のあり方について解説します。
1. 引きこもり支援の歴史と現状
1.1 「ひきこもり」という概念の誕生
1980~90年代、学校や職場を長期間欠席・欠勤し、自宅からほとんど外出しない若者を「ひきこもり」と位置づける研究が始まりました。厚生労働省は2003年に初めて「社会生活を6か月以上送れていない状態」と定義し、全国に約70万人の当事者がいると推計しました。
1.2 政府・自治体の支援体制
自治体は相談窓口や訪問支援、就労訓練などの支援を設けていますが、相談者のプライバシー確保や本人の意欲を引き出す手法の確立が課題です。また公的支援の対象年齢が40代前後に限られ、支援の断絶に悩む家族も多いのが実情です。
2. 「引き出し屋」の登場と問題点
2.1 民間業者のビジネスモデル
「引き出し屋」は、数十万円から百数十万円と高額な料金を徴収し、引きこもり当事者を自宅から外へ連れ出すサービスを提供すると謳います。本人が自力で外出困難なケースに「専門のスタッフが説得・同行する」として、短期集中型の外出プログラムを実施します。
2.2 強引な手法と人権侵害
中には契約書に「誓約違反時には追加金を請求」「外出後は返金不可」など過酷なペナルティ条項を盛り込み、本人の意思とは無関係にスタッフが物理的に連れ出す例があります。施設では外出禁止や監視カメラ、個室の施錠などが行われ、実質的に自由を奪う事例も報告されています。
3. 被害事例と家族の葛藤
実際に、17歳の高校中退者が母親の同意で引き出し屋に預けられ、そのまま数か月間施設に軟禁状態となり、体調を崩したケースがあります。家族は「本人のため」と依頼したものの、帰宅後の心身不調やトラウマに苦しむ息子の姿を見て深い後悔と自責の念を抱えています。また、行政や支援団体への相談にも踏み切れず、孤立する母親の悩みは複雑化しています。
4. 法的規制と課題
現行法では「民間契約」による引きこもり支援は原則自由とされ、監禁や暴行がなければ警察介入は難しい状況です。「人身保護請求」などで無理やり連れ出された場合の救済手段はあるものの、家族や当事者が具体的行動に移すハードルは高いままです。また、消費者契約法による「不当条項」の無効も、裁判所の判断や弁護士依頼が必要で、時間と費用がかかります。
5. 今後求められる支援のあり方
- 相談窓口の拡充:匿名相談や家族同席型の面談、オンライン相談を増やし、心理的ハードルを下げる。
- 多機関連携チーム:保健師・精神科医・臨床心理士・福祉職で構成する包括的支援チームを常設し、本人の意思を尊重した支援計画を策定。
- 当事者参加型プログラム:カウンセリングやピアサポート、自助グループへの参加促進で自己肯定感や自律性を育む。
- 家族支援の強化:当事者の家族に対する教育プログラムや心理的ケアを充実させ、過度なプレッシャーを緩和。
- 悪質業者の規制:消費者庁による監視強化や地方自治体条例で無許可業者の取り締まりを実施し、違反者への罰則を厳格化。
まとめ
引きこもり支援を掲げる「引き出し屋」の一部で発生している強引な連れ出しや監禁は、社会問題として放置できません。本人の意思や人権を尊重しつつ、適切な制度設計と公的支援の強化が急務です。当事者と家族が安心して手を取り合い、自律的な社会参加を実現するために、行政・専門職・市民が連携して支援の環境整備を進める必要があります。


コメント:0 件
まだコメントはありません。