出生前診断異常なし 子がダウン症
出生前診断異常なし 子がダウン症
2025/06/08 (日曜日)
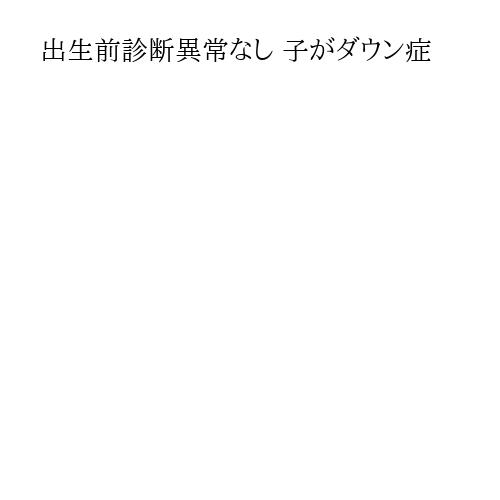
出生前診断で「異常なし」、生まれた子はダウン症 30代夫婦が病院に起こした訴訟の行方
訴訟の経緯と概要
30代の夫婦は妊娠中に病院で行った出生前診断(超音波検査および血清マーカー検査)で「異常なし」と告げられたにもかかわらず、出産後に生まれた子どもがダウン症(21トリソミー)と判明しました。両親は診断結果が誤っていたとして、検査を実施・診断した医療機関に対し数千万円の損害賠償を求める訴訟を起こしています。
出生前診断の種類と仕組み
- 超音波検査(エコー)
胎児の形態や首のむくみ(NT値)などから染色体異常のリスクを示唆しますが、あくまでスクリーニング(ふるい分け)検査です。 - 母体血清マーカー検査
母体血中の化学物質濃度を測り、21番染色体・18番染色体トリソミーなどのリスクを統計的に算出します。検出率は約70~80%、偽陰性や偽陽性のリスクがあります。 - 非侵襲的遺伝子検査(NIPT)
母体血中に遊離する胎児由来DNAを解析し、異常染色体の有無を90%以上の精度でスクリーニングしますが、確定診断ではなく陽性時は羊水検査などの確定検査が必要です。 - 侵襲的検査(羊水検査・絨毛検査)
羊水や絨毛を採取して染色体を直接解析する「確定診断」。流産リスク(約0.1~0.5%)を伴います。
検査精度と偽陰性の可能性
出生前診断は「異常なし」を保証するものではありません。超音波検査や母体血清マーカーは検出率が80%前後、NIPTでもfalse negative(偽陰性:異常があっても検出できない)が約1~2%存在します。特に血清マーカー単独や超音波所見のみでは、胎児の表現型や採血時期によって検査感度が落ちることが知られています。
日本における出生前診断の歴史
- 1984年頃:母体血清マーカー検査導入。トリプルテストなど基本的スクリーニング開始。
- 1990年代:超音波検査によるNT測定が普及し、リスク評価が高度化。
- 2013年:NIPTが一部の医療機関で臨床導入。高リスク妊娠に限定された運用。
- 2016年:日本産科婦人科学会のガイドラインでNIPT保険適用の議論開始。
- 2024年:NIPT実施施設の登録制や遺伝カウンセリング義務化が制度化。
医療側の説明義務とインフォームド・コンセント
医師は出生前診断を行う前に、検査の性質、精度、偽陰性・偽陽性の可能性、および確定診断の必要性とリスクについて十分に説明し、同意(インフォームド・コンセント)を得る義務があります。説明不足や誤解を招く言い回しがあった場合、医学的過誤や説明義務違反が問われることになります。
これまでの裁判例と判例動向
- 2001年:超音波検査で異常なしとされたが出生後に先天性心疾患が判明した事例で、説明義務違反を認定し、医師に賠償命令。
- 2010年:NIPT未導入時代の母体血清マーカー検査で偽陰性となった事例で、検査精度や説明内容が争点となり、一部で医療側の善管注意義務違反を認めた判決あり。
- 近年:NIPTの導入に伴い「スクリーニング検査であることの説明が不十分」として賠償を認める傾向が強まっている。
原告側の主張と求める賠償内容
原告夫婦は、「検査結果を過度に信用して確定検査を受けなかったのは病院の説明不足が原因」と主張。出生後の医療費や育児・教育費、精神的苦痛に対する慰謝料など、数千万円の損害賠償を求めています。また、遺伝カウンセリングや再発防止策の法的義務化も併せて請求しています。
被告(医療機関)側の抗弁
医療機関側は、「スクリーニング検査は確定診断ではない旨を説明し、同意を得た」と主張。検査結果を鵜呑みにして確定検査を受けなかったのは両親の判断であり、検査精度の限界や偽陰性の可能性を説明しているため、過失はないと反論しています。
倫理的・社会的課題
- 検査の限界と期待のギャップ:高度化する検査技術と、受診者の期待値がかみ合わず、説明不足がトラブルを招く。
- 障害者差別の懸念:出生前診断が普及することで、障害者へのネガティブな偏見が助長される可能性。
- カウンセリング体制の必要性:検査前後に専門の遺伝カウンセラーが介在し、心理的支援を含めた包括的ケアが求められる。
今後の展望とガイドライン改訂
日本医師会や日本産科婦人科学会は現在、出生前診断の実施施設要件強化や説明義務の明確化に向けたガイドライン改訂を検討中です。検査精度や限界をより具体的に伝える資料作成、遺伝カウンセラーの配置義務化、受診者が自らのリスク許容度を判断できるツール開発などが議論されています。
まとめ
出生前診断は現代医療の重要なツールですが、その結果を過信して確定診断を怠ると重大なトラブルを招きます。医療側は検査の性質と限界を十分に説明し、受診者は説明を理解した上で自己判断と確定検査の有無を選択する責任があります。今回の訴訟は、インフォームド・コンセントのあり方や検査技術の社会的受容について、再検討を迫る契機となるでしょう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。