立憲 内閣不信任案見送りで調整
立憲 内閣不信任案見送りで調整
2025/06/10 (火曜日)
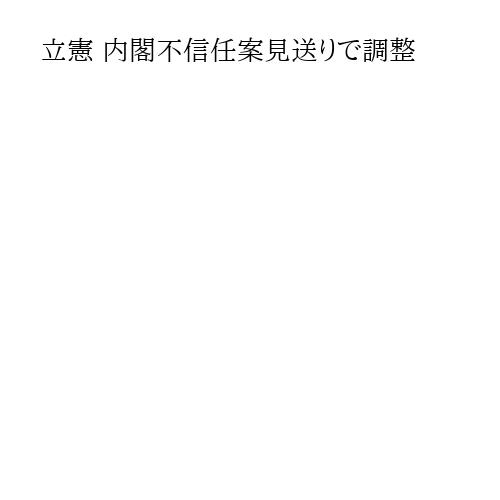
総合ニュース
立憲民主党の野田佳彦代表は9日、今国会での石破茂内閣への不信任決議案提出を見送る調整に入った。石破首相が15日からカナダで開かれる主要7カ国首脳会議(G7サミット)の前と後に、野党が求めた米国との関
はじめに
2025年6月9日、立憲民主党の野田佳彦代表は、今国会での石破茂内閣への不信任決議案提出を見送る方向で調整に入ったと発表しました。本来、野党は首相に対し米国との安全保障条約や経済連携強化を求める議論を深めるため、不信任決議をチャンスとする構えでしたが、来週カナダで開催される主要7カ国首脳会議(G7サミット)の前後に政局混乱を避ける配慮から、提出時期を見合わせる判断を下しています。
1.不信任決議案とは何か?
日本の国会における不信任決議案は、衆議院が内閣に対して示す「信任しない」という意思表示です。可決されれば内閣は総辞職か衆議院を解散しなければならず、政権基盤を揺るがす強い政治手段となります。憲政史上、1948年の芦田内閣や2009年の麻生内閣などが不信任決議案を可決・提出された例がありますが、実際の解散・退陣に至ったケースは限られています。
2.過去の主要事例
・1948年 芦田均内閣:衆議院不信任可決を受け退陣
・1993年 細川護熙内閣:自民党分裂による連立政権の成立
・2009年 麻生太郎内閣:不信任案提出による解散総選挙で自民党大敗
これらの事例では、不信任案が提出された直後に解散・総選挙へとつながり、日本の政局に大きな転換をもたらしました。
3.石破内閣の課題と野党の攻勢点
石破内閣は発足当初から少子高齢化対策、経済再生、安全保障のバランスに挑んでいます。特に米国との防衛協力強化を巡り、野党は在日米軍基地の負担や自衛隊の役割拡大に慎重な立場を取ってきました。また、経済連携協定(EPA/TISA)の交渉過程で、農林業者保護や中小企業支援を不十分と批判。こうした政策論点を追及するために不信任案を武器にする構図があったのです。
4.G7サミットと政局への影響
6月15日からのG7サミットは、ウクライナ支援やインド太平洋戦略、気候変動対策などを協議する国際会議です。世界的な注目を集める中、与野党が国内で激しく対立すれば、首相の外交交渉力にも影響を及ぼす恐れがあります。野党側は「国内政局を棚上げして米国との関係強化を議論すべき」との主張を踏まえ、あえてサミット前後の混乱を避けるタイミング調整を優先しました。
5.野田代表の判断と党内事情
野田代表は党内基盤の安定を重視し、「支持率低迷の中で不信任案提出が逆効果になりかねない」と判断しました。立憲民主党は来年の参議院選挙を睨み、野党共闘の継続や地域票の維持を最優先。相次ぐ党内離反や中道層の離反を防ぐため、強硬な政局手段を控え、協議期間を確保する方針です。
6.不信任決議見送りの意義とリスク
提出見送りは、野党が国内外の大問題に集中するための戦術といえますが、一方で「政権監視を放棄した」との批判も免れません。支持基盤の高齢層や保守層からは「野党としての役割を果たしていない」との声が上がり、野党内諸派の不満もくすぶっています。党としては、提出時期を再検討する条件と合わせ、今後の政策協議の成果を示せるかが問われます。
7.今後の展望
野党はサミット後の6月下旬~7月に、駐日米国大使との会談状況や協力強化策の具体化を受け、不信任案提出を再検討するとみられます。与党側は対案として防衛費増額や外交文書の全面公開を掲げ、政局をにらんだ綱引きが続くでしょう。参議院選挙を控え、与野党の駆け引きは一層激化し、国民の判断材料として「政策論争」の質が問われます。
まとめ
立憲民主党が石破内閣への不信任決議案提出を見送った決断は、国内政局と外務の狭間での苦渋の選択です。G7サミットを控えた外交と、参院選を見据えた党勢維持の両面で、適切なタイミングと戦略的提言が今後のカギとなります。政権批判と政策提案のバランスをどう取るか、野党の真価が問われる局面と言えるでしょう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。