日大重量挙部元監督 詐欺疑い逮捕
日大重量挙部元監督 詐欺疑い逮捕
2025/06/10 (火曜日)
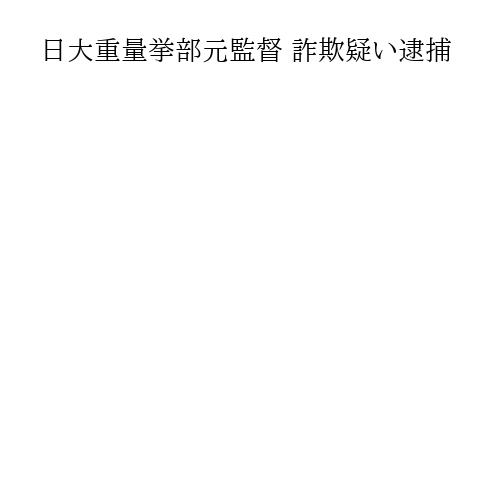
【速報】“名門”日本大学重量挙部の元監督逮捕 入学金など不要な特待生4人の保護者に「入学金必要」などうその案内 現金205万円詐取か 遊興費などに充てたか 警視庁
はじめに
2025年6月9日夕方、警視庁は“名門”として知られる日本大学重量挙部の元監督(65歳)が、保護者への虚偽案内により現金約205万円を詐取した疑いで逮捕されたと発表しました。被害にあったのは重量挙部に特待生として入学した4名の保護者で、「入学金や授業料は不要」と説明したにもかかわらず、元監督名義の口座へ入学金名目で振り込ませていたというものです。本稿では、事件の経緯と内容を整理するとともに、大学スポーツにおけるガバナンスの現状や選手育成体制の課題、スポーツ界で散発する詐欺事件の類型と法的課題、再発防止に向けた取り組みなどを詳しく解説します。
1.事件の概要
警視庁の調べによると、逮捕された元監督は2023年4月から2024年3月までの間、重量挙部に入部した高校卒業生4名を「全額大学負担の特待生」として保護者に紹介。入学金や授業料がかからないと説明しつつ、実際には「設備維持費」や「遠征費用」「ユニフォーム代」と称して計205万円を私的に受領しました。受領後は高級レストランでの接待や私的な飲食費、遊興費などに充てていたとされています。
元監督は今年5月中旬、被害保護者の通報を受けて詐欺容疑で事情聴取され、その後逮捕に至りました。取調べに対し「特待制度の誤解を招いただけで詐欺の意図はなかった」と供述していますが、警察は文書や振込記録、口座履歴を押さえ、計画的・組織的に私的流用したと判断しています。
2.日本大学重量挙部の歴史と実績
日本大学重量挙部は、1950年代に創部以来、日本学生重量挙選手権で多数の優勝実績を誇る強豪チームです。オリンピックや世界選手権の代表選手も輩出し、多くのトップアスリートを育成してきました。伝統的に「部費や遠征費は大学が全額補助する」として、経済的に恵まれない選手の支援を行ってきた背景があり、今回の事件はその信頼を大きく損ねるものとなりました。
特待生制度は部活動強化策の一環として導入され、学業と競技を両立する奨学金・経済支援として高く評価されていました。保護者にとっては入学後の費用負担がほぼゼロという説明が前提であったため、元監督の案内を信じて金銭を振り込んだケースが多く見られました。
3.詐欺の法的枠組みと摘発経緯
日本の刑法第246条には「人を欺いて財物を交付させる行為」が詐欺罪として規定されており、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。今回のケースでは、被害者に「入学金不要」という虚偽の説明を行い、実際には私的な目的のために金銭を取得している点が詐欺罪の成立要件を満たします。
警視庁は先月、被害保護者からの相談を受け、不正受給の疑いがあると判断して捜査を開始。元監督の口座残高や振込記録を押さえ、部費・大学負担の分と私的取り込み分を線引きし、該当部分205万円を詐取と認定して逮捕に踏み切りました。
4.大学スポーツにおけるガバナンス課題
大学スポーツは「教育活動の一環」として公益的に位置づけられる一方で、部活動の管理・運営は教職員やOB・OGが担い、独自の予算管理が行われるケースが多いです。特に強豪校では遠征費や用具購入費、コーチ招聘費用など多額の資金が動くため、大学本体のガバナンスから逸脱しがちです。
法制度としては、2019年のスポーツ基本法改正により「スポーツ活動の透明性確保」が求められていますが、実施主体となる大学には罰則規定がないため、自浄作用に頼る側面が強いのが現実です。今回の事件は、部活動運営における会計と報告体制の強化が必要であることを改めて浮き彫りにしました。
5.他競技・他大学の類似不正事例との比較
過去には大学駅伝部の遠征費横領事件、柔道部のスポンサー料金着服事件、合気道部の掛け金詐取事件など、部活動をめぐる不正が散発しています。いずれも部内の「一人権限」体制や外部監査の不在が犯行を助長しており、全国の大学で監査体制強化やガバナンス改革が急務となっています。
海外では米国NCAAが学生アスリートの奨学金や補助金の適正管理を厳格に監査し、不正が発覚すると除名や制裁を行う体制を構築しています。日本でも、大学スポーツ連盟による独立した監査機構や第三者委員会の導入が検討課題です。
6.保護者・選手の心理と被害実態
被害にあった保護者は「子どもの進学と競技継続を最優先にした結果、監督の言葉を盲信してしまった」と語っています。学生選手自身も「経済的負担を心配せずに競技力向上に集中できる」と信じていたため、入学後に重い負担を抱え込む可能性がありました。金銭トラブルは家庭崩壊や選手の競技離脱を招くリスクが高く、大学は学生と保護者への心理的ケア支援も課題となります。
7.再発防止策と大学の対応
日本大学は、今回の逮捕を受けて以下の再発防止策を表明しました。
1) 部活動会計の定期外部監査導入
2) 部費・補助金使用履歴のウェブ公開
3) 運営責任者の複数設置と権限分散化
4) 保護者説明会での資金管理・ガバナンス講習
5) 大学スポーツガバナンス推進室の設置
これらの措置を迅速に実行し、学生と保護者が安心して部活動に専念できる環境整備が急がれます。
8.スポーツ界全体への教訓と提言
部活動をめぐる不正は、大学スポーツの信頼を根底から揺るがす社会問題です。再発防止には
・全国大学スポーツ連盟による統一ガイドライン整備
・独立監査機構の設置義務化
・部活動指導者向け倫理・ガバナンス研修
・保護者と選手への情報開示ルール明確化
が必要です。さらに、大学スポーツを支えるOB・OGの寄附やスポンサーシップの適正管理も重要なポイントとなります。
まとめ
日本大学重量挙部元監督の逮捕事件は、スポーツ指導者のモラルと組織ガバナンスの課題を改めて浮き彫りにしました。部活動運営の透明性と会計監査体制を強化し、保護者・選手が安心して競技に打ち込める環境を構築するため、大学界全体での制度改革と社会的監視が求められます。スポーツを育む教育機関の責務として、公正で健全な部活動運営の実現が急務です。


コメント:0 件
まだコメントはありません。