警察官自殺 1.3億円の賠償命令
警察官自殺 1.3億円の賠償命令
2025/06/10 (火曜日)
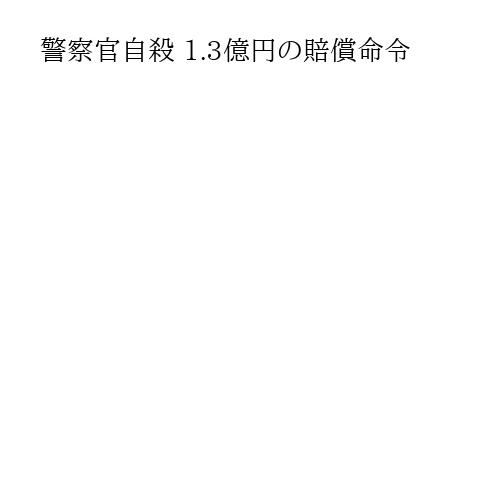
総合ニュース
上司からのパワハラで警察官自殺 県に1億3500万円の損害賠償を命じる判決 長崎地裁
はじめに
2025年6月10日、長崎地裁は上司からのパワーハラスメントを苦に自殺した元警察官遺族が県を相手取って提起した損害賠償請求訴訟において、県に約1億3500万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。この判決は公務員の職場におけるハラスメント問題の重大性と、行政機関の安全配慮義務を改めて示すものとして注目されます。
1.事件の経緯
原告の元警察官は、数年間にわたり直属の上司から継続的な暴言や過重な業務強要を受け、精神的に追い込まれた末に自ら命を絶ちました。遺族は「適切な相談窓口や上司の管理を怠った県警の組織的責任がある」として、慰謝料や逸失利益の賠償を求める訴えを2019年に提起しました。
裁判では、上司の暴言の録音記録や同僚の証言、業務量の異常性を示すシフト表、精神科受診記録が証拠として提出され、県側は「指導の範囲内だった」「自殺の直接要因は特定できない」と主張しました。
2.判決のポイント
- 県警には部下の安全配慮義務とハラスメント防止の義務があることを認定
- 上司の言動が職務の範囲を逸脱し、遺族の精神的苦痛を直接誘発したと判断
- 自殺との因果関係を「相当因果関係」として肯定—行政訴訟での労災認定基準に準拠
- 慰謝料および生計補償などで総額1億3500万円の賠償命令
3.公務員の安全配慮義務と法的背景
民法第5条(公序良俗)や第709条(不法行為責任)に加え、公務員法や国家賠償法により、公務員は上司・組織において部下の生命・身体の安全を確保する義務が明記されています。裁判例でも、職務指導が過度で精神障害や自殺を誘発した場合、国家賠償法上の瑕疵ある公権力行使と認められるケースが増えています。
4.類似事例との比較
- 2016年・大阪府警事件:警察官の自殺をめぐり、遺族が府に賠償請求。業務過重とパワハラを受け、5000万円の和解成立。
- 2018年・奈良県庁事件:公務員が上司の暴言により休職後自殺。県が賠償責任を認め、約8000万円を遺族に支払う。
これらの先例と比べ、長崎地裁判決は金額規模が最大級であり、組織的責任に踏み込んだ判断が特徴です。
5.職場ハラスメントの実態と対策
内閣府の調査によると、公務部門でのパワハラ訴訟はここ5年で約1.8倍に増加。上司の指導風土や相談窓口の形骸化が指摘され、再発防止策が急務です。
- ハラスメント防止研修の義務化と部下向け相談窓口の充実
- 第三者機関による匿名通報システムの導入
- 上司評価に「部下のメンタルヘルス管理」指標を追加
- 定期的なストレスチェックとフォローアップ面談の実施
6.遺族支援と社会的意義
公務員の自殺は単なる個人事件にとどまらず、公共サービスの信頼性にも影響します。遺族が真相を知る権利と精神的ケアの提供、公金を用いた責任ある補償は、再発防止と行政改革の実践として重要です。
まとめ
長崎地裁による1億3500万円の賠償命令は、公務員組織におけるハラスメントの深刻さを改めて示しました。行政機関は部下の心身の安全を最優先に、教育・監督・相談体制を抜本的に見直し、働きやすい職場環境整備を急ぐ必要があります。今回の判例がハラスメント対策の転機となることが期待されます。


コメント:0 件
まだコメントはありません。