柏崎原発に燃料装てん 異例の手順
柏崎原発に燃料装てん 異例の手順
2025/06/11 (水曜日)
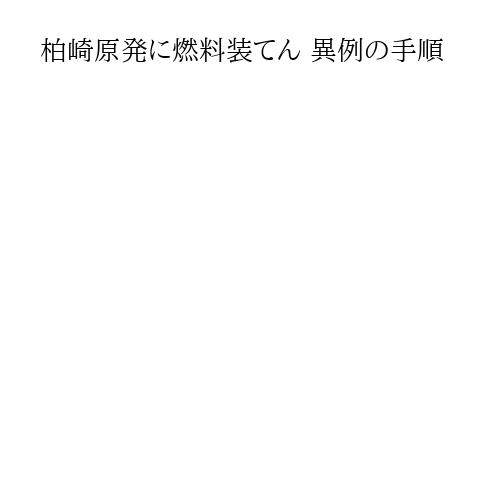
柏崎刈羽原発6号機、東京電力はまたも地元同意を得る前に燃料装てん…異例の手順に再稼動へのプレッシャーとの推測も
柏崎刈羽原発6号機の概要と作業開始
2025年6月10日、東京電力は新潟県にある柏崎刈羽原子力発電所の6号機に対し、原子炉圧力容器の蓋を開け、使用済み燃料プールから核燃料を原子炉内へ移す「燃料装てん」作業を開始しました。この作業は、再稼働に向けた最終段階の試験・検査を行うための重要なステップと位置づけられていますが、通常は地元自治体の再稼働同意を得た後に行われるのが通例です。今回、同意を待たずに装てんを進めた点は全国的に見ても異例で、手順の順序が注目されています。
(出典:新潟日報デジタルプラス)
地元同意を待たない異例の手順
福島第一原発事故以降、全国で再稼働した原発は8ヵ所14基にのぼりますが、核燃料の装てんと地元同意の順序を明文化した規定はありません。とはいえ、ほとんどの電力会社は地元や周辺自治体の同意を得た後で装てんを開始しており、地元理解を得ることを前提に進めるのが慣例とされてきました。柏崎刈羽原発6号機では、地元での同意が得られていない段階で装てんを始めたため、再稼働を巡る手順の在り方が改めて問われる事態となっています。
(出典:新潟日報デジタルプラス)
歴史的経緯:6号機・7号機の類似事例
柏崎刈羽原発では、過去にも同様の手順が踏まれています。2002年のトラブル隠し発覚後や、2007年中越沖地震後の再稼働に向けた装てん作業、さらには昨年4月に行われた7号機への燃料装てんでも、地元同意前に作業が進められていました。東電は装てんを「機器健全性の確認に不可欠」と説明し、装てん後の原子炉内検査で初めて確認できる項目が多数あるため順序が前後しても安全性への影響は少ないと主張しています。
(出典:新潟日報デジタルプラス)
交付金制度と金額減額リスク
装てんの時期は、立地自治体に支払われる「電源立地地域対策交付金」に直接影響します。改定前は再稼働前の装てん日を起点に「みなし稼働率」を算定し、停止中でも一定の交付金を支給していました。改定後は、使用可能とされた日から9ヶ月を過ぎても稼働しない場合、交付金の大幅減額が規定され、6号機で装てんを行った後9ヶ月以内に地元同意を得て再稼働しないと、約7億円規模の減収リスクが浮上します。新潟県や柏崎市など関係自治体は、再稼働の遅れによる財政への影響を懸念しています。
(出典:新潟日報デジタルプラス)
電力需給と再稼働本命の入れ替え
東京電力ホールディングスは当初、7号機を再稼働の最優先候補として準備を進めてきました。しかしテロ対策施設の完成遅延などで7号機の再稼働時期が不透明となったため、6号機への方針転換を迫られています。6号機は朝日新聞によれば、約2週間で872体の燃料装てんを完了させたのち、各種機器点検を経て技術的にはいつでも運転可能な状態にあるとされ、本命機への期待が高まっています。
(出典:朝日新聞)
他電力会社との比較
他社の原発では、関西電力や中部電力などいずれも地元同意を先行させた上で燃料装てんを行う慣行があります。地元理解を重視し「同意先行」を明示的・暗黙的に順守することで、周辺住民や行政との信頼関係を維持してきました。柏崎刈羽6号機での逆順序は、特段の政治的・経済的プレッシャーが背景にあるとの指摘もあります。
(出典:新潟日報デジタルプラス)
地元自治体・住民の反応
柏崎市議会や刈羽村議会では、同意手続きの在り方に疑問の声が相次いでいます。「手続きを軽視しているのでは」「安全より財政優先との誤解を招く」といった批判があり、住民説明会への要請や第三者机上検証の実施を求める動きが出ています。一方で電力安定供給の観点から「早期再稼働を」との意見も根強く、賛否が割れています。
(出典:新潟日報デジタルプラス)
再稼働へのプレッシャーと今後の課題
交付金制度の見直しは政府主導で進められ、電力需給の逼迫や地球温暖化対策による脱炭素の観点から原発再稼働への圧力が強まっています。ただ、地元同意を後回しにすることが住民信頼を損ない、長期的な合意形成を難しくする恐れもあります。安全性と民主的手続きを両立させるために、東電は透明性の高い情報開示と丁寧な住民対話を一層強化する必要があります。
(出典:新潟日報デジタルプラス)


コメント:0 件
まだコメントはありません。