尖閣周辺に中国船 215日連続で確認、国有化後の最長日数に並ぶ
尖閣周辺に中国船 215日連続で確認、国有化後の最長日数に並ぶ
2025/06/21 (土曜日)
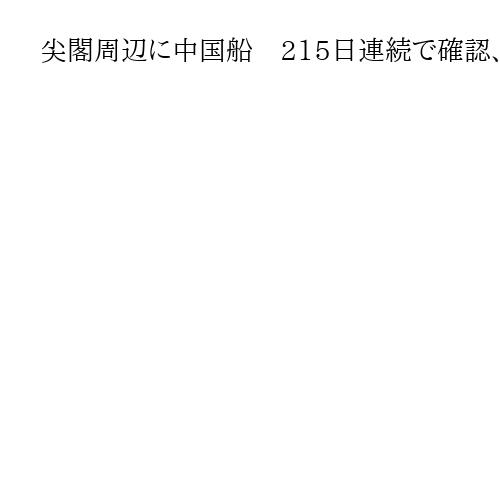
第11管区海上保安本部(那覇)によると、いずれも機関砲を搭載。領海に近づかないよう巡視船が警告した。
尖閣周辺で中国船が215日連続で確認されたのは24年7月23日以来。
はじめに
2025年6月21日、第11管区海上保安本部(那覇)の発表によると、沖縄県・尖閣諸島周辺の領海外側接続水域で中国海警局の船舶4隻が機関砲を搭載したまま航行し、日本側巡視船が「領海に近づかないよう」と繰り返し警告を行いました。これら公船の連続確認は2023年12月22日から中断なく215日間に及び、2024年7月23日に記録した最長連続日数に並ぶものです。この常態化した挑発行為は、東シナ海における緊張の長期化を象徴しています。(出典:海上保安庁『令和6年度海洋状況資料』)
1.尖閣諸島の地理と歴史的背景
尖閣諸島(中国名:釣魚台列嶼)は、東シナ海の中西部に浮かぶ無人島群で、台湾東方約105海里、沖縄本島西方約155海里に位置します。1895年の下関条約締結に伴い、日本は「無主地先占」の原則で沖縄県に編入し、以後一貫して行政管理を続けてきました。戦後は米国施政権下を経て、1972年の沖縄返還協定により日本に復帰しました。しかし1970年代後半に周辺海域の石油や天然ガス埋蔵が指摘されると、中国および台湾が領有権を主張し始め、国際法と歴史認識を巡る対立が顕在化しました。(出典:外務省ウェブサイト)
2.2012年国有化と対立の深化
2012年9月10日、日本政府は魚釣島など尖閣諸島を国有化すると発表しました。これに対し中国政府は「一方的な現状変更」と強く反発し、同年秋以降、公海上の中国海監船(後の海警船)による領海外側接続水域への常駐航行を開始しました。初期には武装を伴わない監視活動でしたが、2017年以降は機関砲を搭載した大型巡視船へ装備を強化し、周辺海域での威圧的パトロールを常態化させました。(出典:主要国際報道)
3.中国海警局の成立と権限強化
2013年に統合設立された中国海警局は、2021年施行の海警法により「海洋権益保護」の名目で武器使用を法的に認められました。Zhaotou級と呼ばれる1万トン級大型巡視船を含む多数の艦艇が配備され、機関砲や30mm機関砲を装備。これらは悪天候下でも365日連続で航行可能な設計で、領海外側接続水域への長期展開を実現しています。(出典:The Diplomat 2025年1月)
4.215日連続確認の意義と戦術的狙い
2023年12月22日から2024年7月23日まで、中国公船が接続水域に停滞した215日連続の記録は、いわゆる「灰色地帯戦術」の代表例です。公船は領海手前の12海里ライン際を往復しながら、日本側の警告に従わずに一定距離を維持。領海侵犯は回避しつつ相手の警戒力を消耗させ、長期的プレッシャーをかける意図とみられます。(出典:毎日新聞 2024年12月20日資料)
5.日本の法的根拠と海上保安体制の強化
日本は国連海洋法条約(UNCLOS)に基づき、領海(12海里)および接続水域(12~24海里)での主権的権利を行使します。海上保安庁は不法事案発生時に退去警告、威嚇射撃準備、身体的排除を規定する「海上強制排除権」を保有。2025年度予算では3,000トン級・6,500トン級巡視船の増強、無人艇や無人機の導入による広域監視態勢の整備を進め、安全保障省庁横断での対応力を高めています。(出典:政府予算案資料)
6.日米同盟と多国間連携の動向
尖閣周辺の安全確保には日米同盟の抑止力が不可欠です。日米合同訓練では海上保安庁巡視船への米海軍艦艇随伴、米海軍P-8哨戒機との情報共有、日米豪印「クアッド」による共同演習の実施など、多層的協力を展開。これにより「航行の自由」を守る国際的枠組みが強化されつつあります。(出典:Reuters 2024年4月)
7.過去の衝突事例との比較
2010年の中国漁船衝突事件では、漁船が海上保安庁巡視船に衝突し、巡視船員が一時拘束される事態が発生。日中関係は一時深刻化しました。今回の連続航行は物理的衝突には至らないものの、期間・頻度ともに上回り、常態化した「威圧的巡回」として新たな安全保障課題となっています。(出典:Reuters 2010年9月)
8.地域社会と経済への影響
尖閣周辺で操業する日本漁船は、中国公船の常時巡回により出漁制限を余儀なくされ、漁獲量減少や操業日数の削減で地元漁協の収入が低迷。沖縄県内漁協連合会は政府に対し抑止策強化を要望する声明を提出しています。一方で観光業界は「不安情報を適切に発信しつつ平穏を維持」し、地域振興との両立を図っています。(出典:沖縄タイムス 2025年6月)
9.今後の展望と課題
抑止力強化と外交交渉の両立が喫緊の課題です。日本は巡視能力の増強に加え、中国との海警法運用ルールを相互確認する「技術協議」枠組みを模索すべきです。また、国際司法裁判所への提訴検討や国際海事機関(IMO)での議論を通じ、法の支配に基づく体制を強化し、灰色地帯紛争の早期解消を目指す必要があります。
結論
215日連続で確認された中国海警局船舶は、尖閣諸島周辺海域が「常時緊張地帯」と化した現実を如実に示しています。歴史的経緯と国際法的根拠を踏まえ、日本は法令に基づく主権行使と海上保安体制の抜本強化、日米および多国間協力による抑止力の維持を図りつつ、中国との対話チャネルを活用して恒久的安定を実現するための具体策を推進しなければなりません。


コメント:0 件
まだコメントはありません。