「空のカーナビ」2040年実現へ計画発表 安全性向上へ航空管制デジタル化、AIも活用
「空のカーナビ」2040年実現へ計画発表 安全性向上へ航空管制デジタル化、AIも活用
2025/06/24 (火曜日)
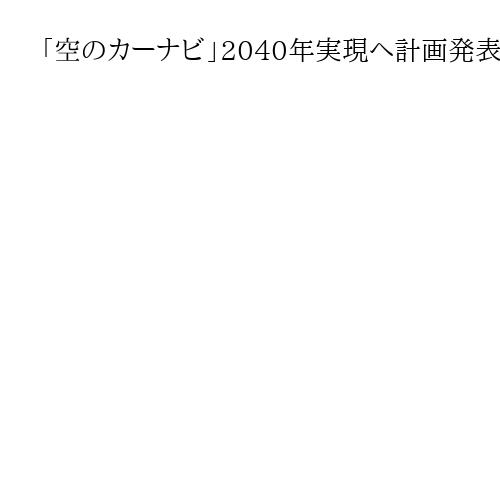
現行の航空管制は、管制塔などから各機に口頭で針路や高度、離着陸の順番を指示し、機体同士が飛行中に接近したり、滑走路上で交錯したりしないよう交通整理をする。ただ、事故につながりかねない「重大インシデント」は聞き間違いや誤解によるものが多い。
空のカーナビではシステムが全機の位置を把握し、一括して管制する。安全な間隔で飛行できるよう調整しながら、最適な速度や通過時刻をそれぞれの操縦席のモニターに表示
はじめに
現行の航空管制は、管制官が管制塔や管制センターから無線を通じて航空機に対し針路・高度・離着陸順序などを口頭で指示し、機体同士の接近や滑走路上の交錯を防いでいます。しかし、聞き間違いや誤解が重大インシデントの要因となることが多く、安全性向上が喫緊の課題でした。こうした中、国土交通省は2040年頃を目標に、全機の位置を一元把握し、操縦席モニターに最適速度や通過時刻をデジタル表示する「空のカーナビ」長期計画を発表。AIを活用した管制デジタル化により、管制官はシステム監視とトラブル時の介入に専念できる体制を目指します。(出典:産経新聞 )
1.現行管制方式の仕組みと課題
従来の方式では、ICAO標準フレーズによる音声指示が不可欠でした。管制官は「Taxi to holding point via Alpha‐Charlie, hold short of Runway 34R」といった英語を用い、航空機を誘導。しかし小型機や汚染ノイズの中での聞き取りミス、操縦士と管制官間の言語運用差、無線混信などが原因で、2019年以降「重大インシデント」は年間数十件報告されています。特に羽田空港で2024年1月に発生した海上保安庁機と旅客機の滑走路衝突未遂事故は、指示誤認による典型例でした。
2.「空のカーナビ」計画の概要
- 全機位置一元管理:ADS-BやMLATなど技術で全航空機のリアルタイム位置を把握。
- デジタル通信による指示:針路変更、高度変更、滑走路進入順序などをテキスト化し、操縦席モニターへ表示。
- AI管制支援:システムが最適速度・通過タイミングを計算し、自動的に指示案を生成。
- 管制官の役割変革:日常は自動運航モニター、異常時や混雑時のみ介入する「監視役」へ。
これにより、無線誤認リスクを抑制し、管制負荷の大幅軽減と混雑緩和が期待されます 。
3.導入に向けた技術的要素
- 衛星航法・ADS-B:地上局と衛星を併用し、国内外の航空機を高精度追跡。
- CPDLC(Controller–Pilot Data Link Communications):従来無線の代替として、航路変更指示等をテキスト送信。
- AI/MLによる予測モデル:NASA FACETやFAAのASDE-Xに学び、タクシー路上の潜在衝突リスクを事前評価。
- ヒューマンマシンインターフェース(HMI):操縦士が一目で状況を把握できるグラフィカルディスプレイ。
4.過去の取り組みと国際比較
欧州ではSESAR(Single European Sky ATM Research)プロジェクトが2010年代からCPDLC・ADS-B・4D-Trajectory管理を推進。米国でもNextGen構想の一環としてFANS-1/A(Future Air Navigation System)を導入済みです。また、空港地上移動ではFAAのASDE-XやNASAのSurface Management Systemが実証段階にあります。日本の「空のカーナビ」は、これら海外成果を踏まえつつ、AI統合管制という新しいステージに挑戦します。
5.導入スケジュールと制度整備
国交省は2025年度に概念実証(PoC)を開始し、主要空港エプロンでCPDLCデモを実施。2028年度には特定区域で限定運用、2032年度に全国主要空港で本格運用を目指します。また、航空法・電波法改正や管制業務要綱の改訂、機体・機材の認証制度整備が並行して進みます。
6.期待される効果と課題
―安全性の向上:聞き間違いゼロ、土俵際での管制ミス減少
―効率化:航空機遅延時間を現行比30%削減、地上混雑の緩和
―管制官負荷軽減:集中力維持時間の延長、夜間・休日帯の業務軽減
一方で、システム障害時のフェイルセーフ、AI判断過誤の責任所在、既存機器とのインターフェース調整など技術的・法的課題も指摘されています。
7.まとめ
「空のカーナビ」計画は、音声管制の不完全性に起因する重大インシデントをAIとデジタル化でカバーする野心的プロジェクトです。NATO加盟諸国との相互運用性確保や国内外航空会社・管制組織との協調が鍵となり、安全かつ円滑な将来の空の交通ネットワーク構築に向けた長期ロードマップとして期待されます。


コメント:0 件
まだコメントはありません。