選択的夫婦別姓 なぜ30年近く停滞
選択的夫婦別姓 なぜ30年近く停滞
2025/06/07 (土曜日)
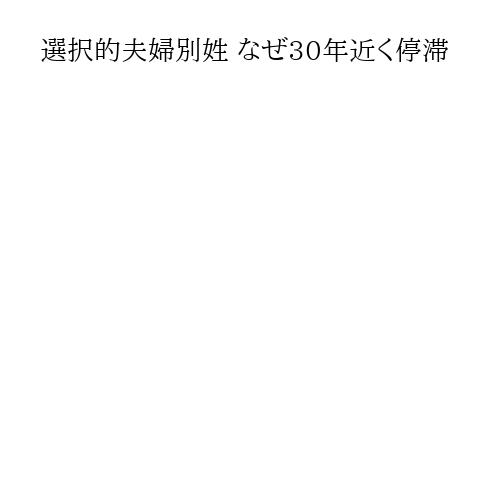
国内ニュース
58万人以上が「別姓婚待ち」の推計も…なぜ選択的夫婦別姓は30年近く停滞? 専門家が解説
はじめに
2025年6月、28年ぶりに「選択的夫婦別姓」導入をめざす法案が衆議院法務委員会で実質審議入りしました。自民党が法案提出を見送り、立憲民主党・国民民主党・日本維新の会の野党3党がそれぞれ異なる法案を提出したものの一本化できず、成立の見通しは立っていません。本稿では、選択的夫婦別姓制度の内容や現行制度の課題、これまでの立法過程、今国会の審議状況、各党案の相違点、世論動向、海外の制度比較、憲法判断・裁判例、そして今後の展望について詳しく解説します。
選択的夫婦別姓制度とは
選択的夫婦別姓制度は、結婚時に「婚姻後も各自が旧姓を維持する」か「夫婦いずれかの姓を共有する」かを自由に選べる仕組みです。現行の民法750条および戸籍法74条1号では、婚姻届に夫または妻の氏を記載しなければ受理されず、夫婦同氏を強制されています。この制度を「選択的」に変更し、同姓・別姓いずれでも婚姻可能とするのが導入の趣旨です。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
現行制度の問題点
寺原真希子弁護士は、現行法の不合理性を「氏と婚姻、いずれも生命や人格に深く関わる価値を二者択一させる点」に指摘します。具体的には以下の3点があげられます。
- 氏名権の侵害:婚姻に伴い片方(多くは女性)が必ず改姓を強いられ、アイデンティティや職歴への影響が生じる。
- 婚姻の自由の侵害:別姓を希望するカップルは事実婚を選択せざるを得ず、法的保護(相続権や配偶者控除など)を受けられないケースがある。
- 多様な家族形態への対応不足:子どもの姓や将来の家族形態を含め、多様性を認める柔軟性に欠ける。
事実婚を選ぶ人のうち約58万人以上が「別姓婚」を待ち望んでいるとの調査もあり、現行制度は婚姻の自由を制限しているとの指摘があります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
立法過程と歴史的経緯
選択的夫婦別姓の導入議論は1996年に法制審議会が答申を出したのが最初で、その後2001年の世論調査で賛成が反対を上回り、2009年の政権交代時にも法制化の機会がありました。しかし、いずれのタイミングでも保守派議員の反対や女性議員の少なさ、選挙リスクを懸念した政治判断により先送りされてきました。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
2015年には最高裁判所大法廷が「同姓強制は合憲」と判断し、形式的な性別不平等は認めないとの結論を示しました。これにより司法ルートでの制度変更は望めず、立法による改正が唯一の手段とされます。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
今国会の審議状況
2025年5月30日、衆議院法務委員会に立憲民主党・国民民主党・日本維新の会の3案が一括審議入りし、6月4日から質疑が始まりました。28年ぶりの審議再開に野党側は「十分な議論を尽くし、世論を喚起することが重要」と主張しましたが、自民党は採決を見送り、成立には至っていません。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
各党の法案内容と相違点
- 立憲民主党案:婚姻届に「同姓」か「別姓」いずれかを明示し、いずれの姓でも婚姻可能とする。婚姻時に子の姓は両者で協議して決定。
- 国民民主党案:選択的別姓を認めるが、戸籍の筆頭者(世帯主)を決定し、子は世帯主の姓を付する方式。
- 日本維新の会案:民法750条は維持しつつ、旧姓を通称として戸籍に併記できるようにし、実質的に別姓利用を認める。
野党3党が案を一本化できず、子どもの姓の扱いや戸籍制度の在り方で相違が大きいことが課題となっています。:contentReference[oaicite:5]{index=5}
世論動向と実態
内閣府の世論調査では、選択的夫婦別姓に賛成する割合は2010年代以降50%前後で推移し、慎重派を上回る状況が続いています。また、事実婚カップルの約半数が別姓を理由に婚姻を躊躇しているとのデータもあり、実際に婚姻届を出さない「結婚希望層」の存在が明らかとなっています。:contentReference[oaicite:6]{index=6}
海外の制度比較
世界的には「別姓・同姓どちらも可」の国が多く、スウェーデン・アメリカ・イギリス・フランス(慣習的)などでは婚姻後の姓選択が自由です。一方、日本・インドでは同姓義務が法律で規定されている希少な国となっています。韓国や中国、ベトナム、スペインなどでも別姓が一般的で、日本の制度が特殊であることがうかがえます。:contentReference[oaicite:7]{index=7}
憲法判断と裁判例
2015年の最高裁大法廷判決(平成27年12月15日)は、民法750条の同姓強制が憲法14条(法の下の平等)に反しないと判断しました。裁判所は「夫婦同氏原則は社会に定着し、合理的制度として認められる」とし、立法政策判断の範囲としました。このため、司法による合憲性判断は改正を求める動きを後押しせず、立法措置に委ねられています。:contentReference[oaicite:8]{index=8}
今後の展望と論点
- 法案一本化:野党間で子どもの姓や戸籍制度をどう整合させるか、早急に合意形成が必要です。
- 世論形成:国民理解を深めるため、審議の十分な公開と情報提供が求められます。
- 制度移行:戸籍システムの改修コストや行政手続きの簡素化、専門職(戸籍職員・戸籍法務担当者)の研修体制整備が課題です。
- ジェンダー平等:姓の問題を通じて性別役割分業意識からの脱却や多様な家族形態の承認が期待されます。
まとめ
選択的夫婦別姓制度は、氏名権や婚姻の自由、多様な家族形態への対応という観点から立法改正が求められてきました。1996年以降、数度の機会がありながら実現を見送られた背景には、政治的制約や制度設計の課題があります。2025年の国会審議を機に、法案の一本化と十分な論点整理、制度移行の具体的検討が進めば、制度改正への道筋が見えてくるでしょう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。