南海トラフ死者8割減目標に 政府
南海トラフ死者8割減目標に 政府
2025/06/10 (火曜日)
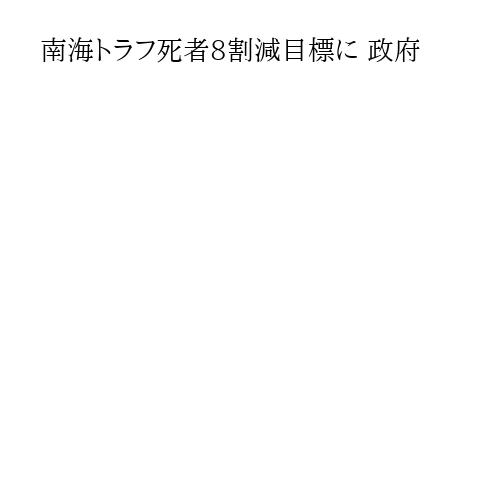
国内ニュース
政府は、3月に発表した南海トラフ巨大地震の被害想定で最大29万8千人とした死者数に関し、今後10年間でおおむね8割減とする目標を設定する方針を固めた。政府、与党関係者が10日明らかにした。全壊焼失建
はじめに
政府は2025年3月に公表した「南海トラフ巨大地震」被害想定で、最大で約29万8千人にのぼる死者数を、今後10年間で約8割削減する目標を設定する方針を固めました。政府・与党関係者によれば、住宅の耐震化や避難体制整備、地域の減災力強化などを一体的に進めることで実現を図るといいます。過去の大地震教訓を踏まえつつ、全国的な防災対策の加速が求められます。
1.南海トラフ巨大地震の被害想定
南海トラフ沿いではマグニチュード9級の地震が90年以内に70%の確率で発生するとされ、津波最大高さは高知県四万十で30メートル以上、静岡県浜松で10メートル以上と試算されます。想定死者数は最悪約30万人、全壊家屋は約90万棟、経済被害額は150兆円超に達するとされ、単一の巨大地震リスクとしては未曾有の規模です。
2.8割減目標の意義
8割減とは、約29万8000人のうち約24万人の死者を防ぐことを意味します。これは、阪神・淡路大震災(約6400人)比で40倍の規模を、現行の対策で縮小しようという挑戦的な目標です。政府は、被災想定を前提にした住民向け避難啓発とインフラ整備を強化し、「ゼロ被害」へ向けたビジョンを示す狙いがあります。
3.過去の地震対策の歩み
1995年の阪神・淡路大震災を契機に、住宅耐震化促進法や建築基準法改正、緊急地震速報の制度化が進みました。2004年には中越地震を経て耐震診断・改修支援が拡充され、2011年東日本大震災では津波避難タワーや高台集団移転などの大規模防災インフラが整備されました。これらの要素技術を南海トラフ対策に結集し、地域特性に応じた減災プランを策定します。
4.国内の防災・減災施策
- 耐震改修補助金:住宅や公共施設の耐震化にかかる費用を最大2分の1補助。
- 津波避難タワー整備:漁村や沿岸集落に高さ10~15mの避難施設を設置。
- 避難訓練・啓発:小中学校や自治会で年2回以上の津波避難訓練を義務化。
- 緊急地震速報強化:基地局数と通知速度を改善し、最大10秒前の警報を実現。
5.建築基準の強化と耐震化
2020年改正建築基準法では、新築住宅の耐震等級3(消防署・警察署並み)の取得促進が図られ、制震・免震構造の導入支援が始まりました。既存不適格建築の解消に向け、木造住宅を中心とした木耐協の改修リフォームガイドラインも改訂され、木造住宅半壊リスクの低減を目指します。
6.地域防災力強化と避難計画
各市町村は「地域防災計画」を5年ごとに見直し、災害特性に応じた避難シナリオを策定。要援護者リストの整備や「災害協定」締結により、福祉・医療機関との連携を強化します。また、シェアオフィスや学校体育館を活用した「多目的避難所」の運営モデルも実証実験が進められています。
7.国際的比較
地震多発国のニュージーランドでは、2010年クライストチャーチ地震後に「ビルディングコード改革」を実施し、耐震設計基準を引き上げました。米国カリフォルニア州は「緊急対応プラン」策定により、ガソリン供給や通信網の優先復旧が義務化されています。日本も国際教訓を踏まえ、早期対応能力を高めるべくJ-Alertの多言語化や衛星通信の活用を検討中です。
8.今後の課題と展望
- 予算確保:毎年度1兆円規模の防災予算を安定的に確保する財政措置
- 人的資源:防災士や土木技術者、地域コーディネーターの育成と配置
- データ活用:IoTセンサーやドローンを活用したリアルタイム被害把握システム
- 教育強化:小中高校での「減災教育」を必修化し、次世代防災リーダーを育成
- 民間連携:保険・金融機関との連動による「災害リスクプール」商品の普及
まとめ
政府が掲げる「南海トラフ巨大地震死者数8割減」目標は挑戦的ですが、過去の教訓と最新技術を結集し、耐震化・避難体制・インフラ整備を加速させることで実現可能です。国・自治体・民間・市民が一体となり、命を守る行動と意識改革を推進し、被害最小化を図る取り組みを強化しましょう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。