米問題で注目 農水族とJAの関係
米問題で注目 農水族とJAの関係
2025/06/11 (水曜日)
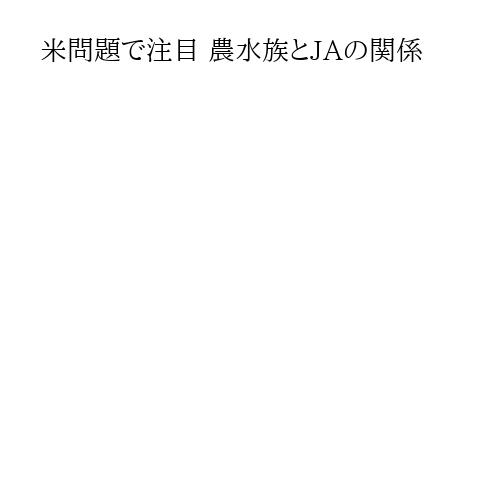
“コメ問題”で小泉大臣とJAの関係は悪化?西田亮介氏「今までの対立に一層、拍車を」 “農政トライアングル”を元農水省官僚が解説
コメ問題を巡る与党・JA間の緊張
2025年6月、小泉進次郎農林水産大臣が政府備蓄米20万トンを随意契約方式で小売業者に直接売り渡す施策を発表したことを契機に、自民党農水派議員とJA(農業協同組合)との関係が一段と悪化しています。JA側からは「官邸主導の急進的施策が現場実態を無視している」との不満が噴出し、小泉大臣との対立構図が鮮明化しました。
JAの役割と組織構造
JAは1947年に創設され、農家の購買・販売・融資を一体化して効率化する役割を担ってきました。全国のJAは中央会を通じて連携し、農林水産省と密接な関係を築いてきた「農政トライアングル」の一角を形成しています。JAは市場安定のための価格支持事業や融資事業、営農指導を行い、農家票を背景に自民党内の農水派議員と強固な利益共同体を形成してきました。
「農政トライアングル」とは何か
「農政トライアングル」は、農家(生産者)、JA(流通・販売・金融)、農林水産省(政策立案・施策実施)の三者が相互補完的に結合し、コメ政策や農政全般を支えてきた仕組みを指します。元官僚は「国会議員の多くが農水派であり、JAは農水省と連携して政策に影響力を行使してきた」と解説しています。
備蓄米放出問題の争点
政府の備蓄米放出は、需給ひっ迫時の緊急対応が目的でしたが、小泉大臣は即効性を重視して「随意契約での小売直販」を主導。一方でJAは「備蓄米は政策在庫としてまずJA経由で安定供給すべき」と反発し、「政府がJAを軽視している」と批判しました。
歴史的な対立構造の再来
1999年のコメ卸自由化論議ではJAと農水省首脳が対立し、JAは全国農協中央会を通じて政府に抗議し、自由化を後退させました。今回の放出問題も、同じくJAの既得権益と省庁主導の市場改革が衝突する構図が繰り返されています。
専門家の指摘──「拍車をかける」理由
政治学者は「従来から農水省とJAの間には駆け引きがあったが、小泉大臣の強硬手法はそれを露呈させた。JAにとっては『自分たちの味方』が政府内で孤立しているように映り、対立に一層拍車をかけている」と分析しています。
他国の備蓄政策との比較
米国では食糧備蓄は緊急援助用として管理され、小売店への直接放出は行われません。EUも緊急時の共同調達にとどまり、小売直販モデルは日本独自の手法と言えます。
今後の展望と課題
政府とJAの溝を埋めるためには、①JAの販売・融資機能を活用しながら小売直販を併存させる制度設計、②農家への十分な情報共有と説明責任、③需給予測の精度向上による先行的な備蓄放出判断、などが必要です。また、JA内部のガバナンス強化と農林水産省官僚の省庁横断的連携も重要です。
まとめ
小泉大臣の備蓄米直販策は迅速な価格安定化を実現しつつ、JAとの既存の利益連合に亀裂を入れる異例の手法でした。今後は「農政トライアングル」の機能不全を回避し、政府・JA・農家が協調できる新たな枠組みを構築することが、安定したコメ供給と政策信頼の維持につながる最大の課題となります。


コメント:0 件
まだコメントはありません。