中国戦闘機 海自機に45mまで接近
中国戦闘機 海自機に45mまで接近
2025/06/12 (木曜日)
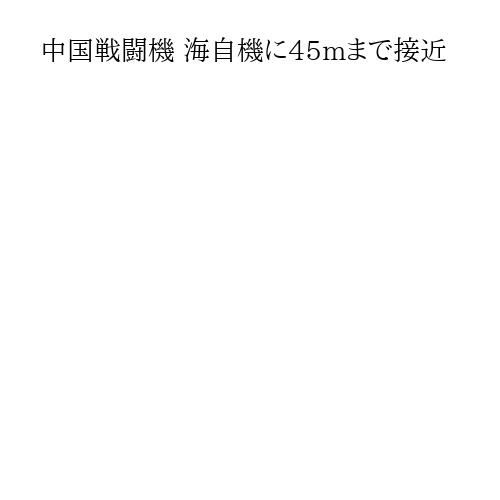
【速報】中国の戦闘機が海自の哨戒機と接近 今月8日には約80分追従
中国戦闘機による海自哨戒機への接近事案
2025年6月11日、政府・防衛省関係者が明らかにしたところによると、同月8日および10日に、中国人民解放軍の戦闘機が海上自衛隊のP-3C哨戒機に対して異例の接近・追従を行っていたことが確認されました。10日の事案では、中国戦闘機が自衛隊機の至近45メートルまで接近し、8日にも約80分間にわたり追尾したとされています。いずれも国際法上の領空侵犯ではないものの、「安全と信頼」を損なう行為として極めて「行き過ぎた危険運航」であると政府は非難しています(出典:Reuters)
事案の詳細と自衛隊の対応
10日の接近では、中国空母「遼寧」隷下のJ-15戦闘機が、P-3C哨戒機を伴走。海上自衛隊機が日付変更線付近の公海をパトロール中、急旋回やロールなどの妙技とともに並走したため、乗組員に強い衝撃と危機感を与えました。哨戒機側はレーダー警報受信後に高度を上げ、機体間隔を確保しつつ任務を継続。政府は防衛駐在武官を通じて抗議し、直ちに厳重注意を求めました(出典:Kyodo News via Reuters)
6月8日の約80分追従事案
6月8日にも同様の追従が発生。中国戦闘機2機がJ-15を伴い、P-3C哨戒機に対し合計約80分間にわたり間近で飛行を続けたため、燃料消費と乗員の疲労が増大しました。哨戒機は公海上を航行しており、国際法に基づく正当な行動でしたが、接近間隔は150メートル以内に何度も接近し、安全マージンを大きく逸脱する危険行為とされています(出典:政府発表)
国際法と領空・領海の境界
国際連合海洋法条約(UNCLOS)では、公海上での軍用航空機の航行を原則自由と定めています。ただし、「無害通航権」を逸脱しない範囲での航行が求められており、他国軍機に危険を及ぼすような無断接近は「国際慣習法」に反する可能性があります。また、軍用航空機同士の緊張緩和を図るため、1972年の「措置の予防的協定(INCSEA)」や「海上での偶発的遭遇防止に関する署名宣言(CUES)」が存在し、中国・日本とも加盟していますが、今回の行為はこれらの精神を大きく逸脱しています。
過去の類似事例との比較
中国機による公海上での接近事例は、近年増加傾向にあります。2024年4月には台湾のRC-135Wを中国J-10Cが約100キロメートルの距離で追跡し、無線で「中国のEEZ内だ」と警告した事例、2022年には南シナ海で米軍P-8AポセイドンをJ-11が至近10ヤードまで接近しロールを仕掛けた事例があります。これらはいずれも「挑発的」と批判され、米中間で外交抗議や軍事チャンネルでの協議が行われました(出典:AP/Reuters)
安全と外交への影響
今回の2件の追従事案は、日米安全保障協力に影響を与える可能性があります。政府はG7外相会合において中国の「戦術的エスカレーション」を議題にし、同盟国間での情報共有と共同抑止の強化を協議。国内では防衛費増額論議が再燃し、次期防衛大綱の見直しや追加装備の導入が現実味を帯びています。また、外交ルートでは中国大使館への抗議と北京政府への申し入れを行い、再発防止を強く求めています(出典:共同通信)
日本の防衛体制と対応能力
海上自衛隊のP-3C哨戒機は、対潜・対水上用の長距離偵察機であり、公海上での情報収集や領空・領海監視の中核を担います。近年導入されたP-1哨戒機へのシフトが進む一方、旧機種であるP-3Cの退役時期が迫っており、追従事案を踏まえた装備更新や乗員教育の強化が急務です。防衛省は最新鋭P-1を含む哨戒機隊編成の見直しや、中国機を遠隔監視できる無人機の配備検討を進めています。
今後の展望と課題
中国機による危険接近は、東アジアの安全保障環境の緊張を象徴するものです。海上・航空における偶発衝突リスクを下げるため、日中防衛・軍事チャネルの再活用やCUES運用強化が求められます。さらに、国際海事機関(IMO)やICAOへの働きかけを通じ、国際法規範の順守を確保する多国間協議の場の必要性も指摘されています。政治、外交、防衛の多層的アプローチにより、緊張緩和と抑止力のバランスを再構築することが喫緊の課題です。


コメント:0 件
まだコメントはありません。