神奈川新聞、参政党の見解「事実の誤りあり看過できない」 会見排除問題で抗議声明
神奈川新聞、参政党の見解「事実の誤りあり看過できない」 会見排除問題で抗議声明
2025/07/25 (金曜日)
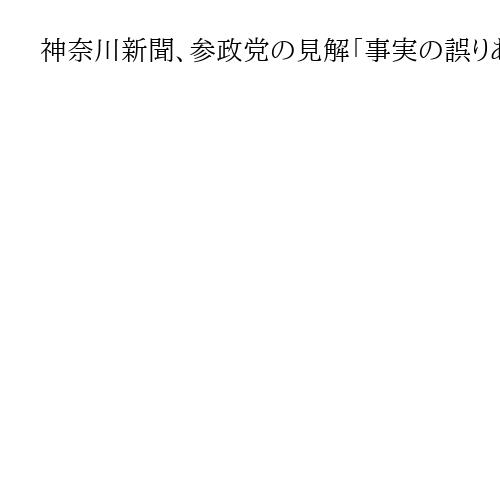
声明では、会見出席を拒む理由として、22日の会見時には「事前登録がない」点を挙げていたのに、24日の党見解では「混乱が生じるおそれがあると判断」した点を虚偽説明だと問題視した。
当該記者が参院選の街頭演説で、参政への妨害行為に関与していたとの指摘には「外国人差別につながる、事実と異なる候補者の主張に対する取材の一環」だとして、誹謗中傷や妨害ではないと説明した。
参政が、会見映像のインターネット
神奈川新聞と参政党の対立:記者会見排除問題の背景と影響
2025年7月25日、産経ニュースは「神奈川新聞、参政党の見解『事実の誤りあり看過できない』 会見排除問題で抗議声明」と題する記事を掲載した。この記事は、参政党が記者会見から神奈川新聞の記者を排除した問題に対し、神奈川新聞が「事実の誤りがある」と抗議声明を発表したことを報じている。参政党は、記者が過去に街頭演説を妨害したと主張し、会見への出席を拒否したが、神奈川新聞はこれを報道の自由への侵害として批判。以下、この問題の背景、歴史的文脈、類似事例、そして今後の影響について詳しく解説する。
[](https://www.sankei.com/article/20250725-KOF5ZIDW2FIUXL7UQOT7U5AHUI/)会見排除問題の経緯
問題の発端は、2025年7月の参議院選挙期間中に、参政党が神奈川新聞の記者を記者会見から排除したことにある。参政党は当初、出席制限の理由を「事前申請がなかった」としていたが、後に公式サイトで「記者が街頭演説の妨害行為に関与したため、混乱を避けるために入場を拒否した」と説明を変更。 これに対し、神奈川新聞は7月25日、参政党の見解に「事実の誤りがあり、看過できない」とする声明を発表。「メディアを選別し、異論を封じる行為は報道の自由を脅かす」と強く抗議した。
この対立は、参政党の急速な支持拡大と、その主張に対するメディアの報道姿勢が衝突した結果だ。X上では、「神奈川新聞の記者が参政党を批判する記事を書きすぎたから排除された」との意見や、「参政党の対応は報道への圧力」と批判する声が混在している。新聞労連も同日、「市民の知る権利を損ねる行為」と参政党を非難する特別決議を出し、事態の深刻さを強調した。
[](https://www.sankei.com/article/20250725-KOF5ZIDW2FIUXL7UQOT7U5AHUI/)歴史的背景:参政党の台頭とメディアとの関係
参政党は、2020年に設立された新興政党で、「日本人ファースト」を掲げ、外国人政策や伝統文化の保護を重視する立場で知られる。2022年の参議院選挙で初の議席を獲得し、2025年の参院選ではさらに支持を広げ、50代を中心に支持を集めたとされる。 その主張は、外国人による不動産購入制限や反グローバリズムを訴えるもので、一部で「排外主義」と批判される一方、経済安全保障や国家主権を重視する層から支持を得ている。
[](https://www.sankei.com/politics/)参政党とメディアの関係は、設立当初から緊張をはらんできた。党の主張が物議を醸す中、一部のメディアは参政党を批判的に報道。特に神奈川新聞は、参政党候補の言動を検証する記事を積極的に掲載し、党側はこれを「偏向報道」とみなしてきた。X上では、「神奈川新聞は参政党を攻撃しすぎ」との声や、「メディアは公平であるべき」との意見が飛び交い、メディアと政党の対立が注目を集めている。この背景には、日本のメディア環境の変化や、SNSを通じた直接発信の増加がある。政党が記者会見で特定のメディアを排除する行為は、従来の報道機関の影響力を相対化する動きともいえる。
類似事例:報道の自由と政治的圧力
記者会見でのメディア排除は、日本国内外で過去にも議論を呼んだ事例がある。2019年、希望の党が記者会見で特定のフリージャーナリストを排除した際、「報道の自由の侵害」と批判された。また、海外では、2017年にトランプ米大統領(当時)がCNNやニューヨーク・タイムズをホワイトハウスの記者会見から締め出したケースが知られる。これに対し、米国のメディア団体は「民主主義の基盤を揺るがす」と抗議し、訴訟に発展した。日本では、記者クラブ制度が報道のアクセス制限として問題視されてきたが、特定の記者の排除は異例であり、参政党の対応は新たな論争を巻き起こしている。
国内では、2023年にれいわ新選組が一部メディアの質問を制限した事例もあった。X上では、「参政党の排除はれいわのケースと似ているが、理由が明確でない分、問題が大きい」との指摘がある。一方、参政党支持者は、「批判的な報道ばかりするメディアを排除するのは当然」と擁護する声も見られる。これらの事例は、報道の自由と政治的意図の間で緊張が高まっていることを示している。
社会的影響:報道の自由と市民の知る権利
参政党の記者排除は、報道の自由や市民の知る権利に対する重大な挑戦と受け止められている。神奈川新聞の声明では、参政党の対応が「批判的な質問を封じる意図」と指摘され、民主主義の根幹である情報公開の原則が脅かされると警告している。 新聞労連も、「公党による報道への圧力は許されない」と強調し、再発防止を求めた。 X上では、「メディアも偏向があるから、参政党の対応は理解できる」との意見がある一方、「報道を制限するのは危険な前例」との懸念も強い。
[](https://www.sankei.com/article/20250725-KOF5ZIDW2FIUXL7UQOT7U5AHUI/)この問題は、メディアの信頼性にも波及している。日本のメディアは、記者クラブ制度や大手メディアの同質性から、偏向報道との批判を受けてきた。参政党のような新興政党は、SNSを活用して直接発信することで、従来のメディアを回避する戦略を取っている。X上では、「メディアが政党を攻撃するなら、排除されても仕方ない」との声もあり、メディアと政党の力関係の変化を反映している。一方で、記者排除が常態化すれば、情報の透明性が損なわれ、市民が多様な視点にアクセスする機会が減る恐れがある。
政治的文脈:参政党と2025年参院選
2025年の参院選は、参政党の支持拡大とともに、外国人政策や国家主権をめぐる議論が注目された。産経ニュースによると、参政党は外国人による不動産購入制限を訴え、経済安全保障や日本の伝統文化保護を強調。 これに対し、立憲民主党や全国知事会は「多文化共生」を掲げ、参政党の主張を「排外主義」と批判した。 参政党の記者排除問題は、こうした政治的対立が背景にある。X上では、「参政党は日本の利益を守る」と支持する声と、「外国人差別を助長する」と批判する声が交錯し、議論が二極化している。
[](https://www.sankei.com/article/20250725-I2J6DYPLDZCJHGRK7H7ZXP4FAE/)[](https://www.sankei.com/article/20250725-I2J6DYPLDZCJHGRK7H7ZXP4FAE/)参政党支持者の一部は、SNSで「メディアの偏向報道が問題の本質」と主張。ある著名人のインスタグラム投稿では、参政党への投票は「個人の自由な選択であり、民主主義の根幹」と述べ、批判に反論した。この発言は、参政党の支持層が選挙結果を民主的なプロセスとして受け入れる姿勢を示しつつ、メディアへの不信感を反映している。
[](https://www.sankei.com/article/20250725-KOF5ZIDW2FIUXL7UQOT7U5AHUI/)今後の展望:報道と政治の関係再構築
参政党の記者排除問題は、報道と政治の関係に新たな課題を投げかける。メディア側は、客観性や公平性を保ちつつ、政党の主張を検証する役割が求められる。一方、政党は、批判的な報道を排除するのではなく、対話を通じて説明責任を果たす必要がある。X上では、「メディアも自己反省すべき」との意見や、「参政党はもっと透明性を高めるべき」との声があり、双方に改善の余地があることが指摘されている。
今後、類似の対立が再発する可能性は高い。特に、SNSの普及により、政党が直接発信できる環境が整う中、従来のメディアの役割が問われている。政府や業界団体は、報道の自由を保護しつつ、メディアの信頼性向上に向けたガイドライン策定を検討する必要がある。また、市民の知る権利を守るため、記者会見の公開性やアクセスの透明性を高める仕組みが求められる。
[](https://www.sankei.com/article/20250725-KOF5ZIDW2FIUXL7UQOT7U5AHUI/)結論:報道の自由と民主主義の試練
参政党による神奈川新聞の記者排除は、報道の自由と民主主義の緊張関係を浮き彫りにした。参政党の台頭やメディアへの不信感は、SNS時代における情報発信の変化を反映する。類似事例から、記者排除が情報の透明性を損なうリスクは明らかだ。メディアと政党は、対立を超え、市民の知る権利を優先する対話が必要である。報道の公平性と政治の透明性が確保されなければ、民主主義の基盤が揺らぐ。今後の議論と制度改革が、この問題の解決の鍵となる。
[](https://www.sankei.com/article/20250725-KOF5ZIDW2FIUXL7UQOT7U5AHUI/)

コメント:0 件
まだコメントはありません。