尖閣諸島周辺に中国海警局船4隻 209日連続航行確認 海保巡視船が警告
尖閣諸島周辺に中国海警局船4隻 209日連続航行確認 海保巡視船が警告
2025/06/15 (日曜日)
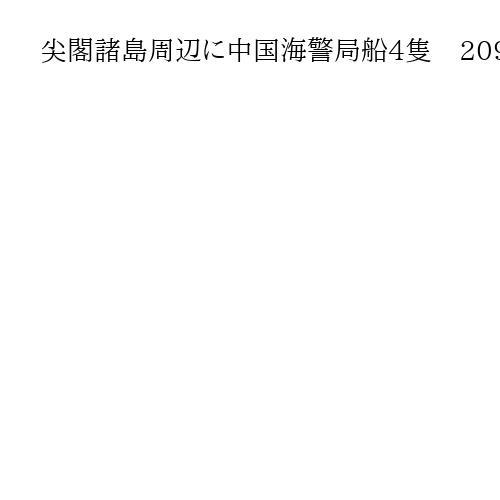
第11管区海上保安本部(那覇)によると、いずれも機関砲を搭載。領海に近づかないよう巡視船が警告した。
はじめに
2025年6月14日、第11管区海上保安本部(那覇)は、尖閣諸島周辺の接続水域で中国海警局所属の艦船4隻が航行しているのを確認したと発表しました。確認された4隻はすべて、甲板に37ミリ級とみられる機関砲を搭載しており、日本の領海に近づかないよう巡視船が無線警告を行い、監視・警戒を強化しています。今回の航行は208日連続で、長期にわたるプレゼンスの維持が懸念されています。
1.航行が確認された中国海警局艦船
- 海警2204
- 海警2301
- 海警2501
- 海警2305
これら4隻はいずれも、日本政府が「公船」と認定する中国海警局の船舶です。過去には小型の航行船が多かったものの、近年は最新鋭の装備を備える大型艦船も導入されています。
2.機関砲搭載の背景と意味
機関砲は対小型ボートや接近する船舶に威嚇射撃を行うための装備で、通常は「公務執行用武器」として位置づけられます。中国海警局の艦船にこうした武装を搭載することは、領海侵犯の意図を示す威圧的な行動とみなされ、沿岸国にとっては深刻な安全保障上の懸念材料です。
3.尖閣諸島を巡る法的・外交的論点
尖閣諸島(中国名:釣魚島)の周辺海域は日本の領海・排他的経済水域(EEZ)とされていますが、中国は「公海上での航行の自由」を主張し、法的解釈をめぐる対立が続いています。武装公船の航行は、国際法に基づく「無害通航権」の逸脱行為として、国際社会における批判対象となります。
4.日本側の対応と巡視強化
第11管区海上保安本部は、1500トン級PL型巡視船やヘリ搭載PLH型巡視船を集中的に配備し、航空機による早期探知、レーダーシステムの連携など、複数の監視手段を統合して警戒を強化。領海接続水域での警告を超えて、領海侵入の兆候があれば即時退去を命令する態勢を敷いています。
5.連続航行日数の長期化が示すもの
尖閣周辺での中国公船の確認は、当初1日から数日にとどまっていたものが、2025年6月時点で208日連続に及んでいます。こうした長期航行は、沿岸警備能力の見極めや偵察活動の一環と見られ、日本の領海警備力や即応態勢を試す「グレーゾーン事態」として重要視されています。
6.地域住民・漁業者への影響
漁業操業海域に近接したパトロールは、日中双方の漁船に不安をもたらします。漁業者は「漁場が狭められた」「警告があると安全操業に支障が出る」と懸念を示し、地元自治体も漁村の暮らしへの影響を注視しています。
7.日米安保と多国間協力の重要性
日本は日米地位協定に基づく米軍基地を沖縄に多数抱えていますが、海上保安は法執行組織であり、軍事組織とは位置づけが異なります。そのため、海洋安全保障や海上監視については、米国沿岸警備隊や豪州・東南アジア諸国との連携強化が求められています。
8.過去の事例との比較
2010年代末から中国公船の武装航行は見られましたが、機関砲搭載艦船の常時航行が確認されるのは異例です。2012年の尖閣国有化を契機に緊張が高まりましたが、この数年で中国海警局の装備近代化と運用常態化が急速に進んでいることが鮮明になっています。
9.国際法の視点から見る抑止と対話
海洋法条約(UNCLOS)では、領海・EEZ内の法執行権限を沿岸国に認めています。したがって、武装公船は「治安維持活動」として排除できる一方、過度の衝突回避と慎重な対応が求められます。同時に、中国との外交対話を通じ、ルールに基づいた海域管理の仕組み構築が急務です。
10.今後の展望と課題
日本は巡視船の増強に加え、無人航空機(UAV)による監視や衛星画像解析などハイテク監視手段の導入を進めています。また、地元漁業者への支援、海上法執行人員の訓練充実、日中間のホットライン設置など、多角的な抑止・対話策を組み合わせる必要があります。
まとめ
第11管区海上保安本部による中国海警局艦船4隻の機関砲搭載航行確認は、尖閣諸島周辺を巡る長期的な「グレーゾーン事態」の深刻化を示しています。日本は法執行組織としての海上保安能力を一層強化するとともに、米国や近隣諸国との連携や外交努力を通じ、公海・領海のルールに基づく安定的な海洋秩序を維持することが求められます。


コメント:0 件
まだコメントはありません。