台湾有事で米軍部隊がミサイルを撃つ時、自衛隊は撃てるか? 米海兵隊大尉「将来の戦闘」
台湾有事で米軍部隊がミサイルを撃つ時、自衛隊は撃てるか? 米海兵隊大尉「将来の戦闘」
2025/06/17 (火曜日)
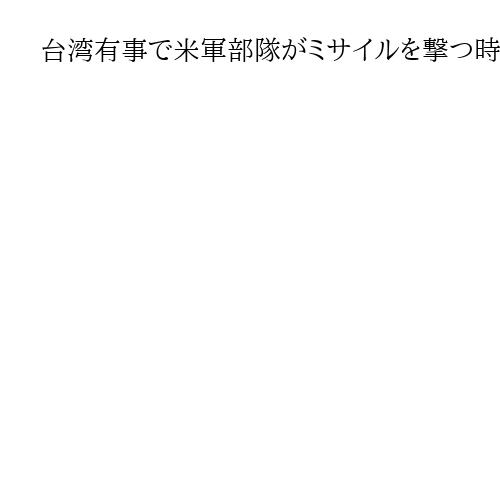
台湾有事が起きれば、米海兵隊は小規模部隊が分散展開し、中国軍を発見・追尾し、地対艦ミサイルなどで中国軍を攻撃する-。海兵隊は新たな作戦コンセプト「遠征前方基地作戦(EABO)」の下に装備調達や自衛隊を含む友軍との訓練を進めている。分散展開した小規模部隊は具体的にどのような判断を迫られるのか。海兵隊大尉が昨年発表した架空の物語で改めて浮き彫りになったのは、海兵隊は自衛隊とは異なる基準で行動することを
はじめに:台湾有事に備える米海兵隊の「遠征前方基地作戦(EABO)」と小規模部隊の判断
台湾有事が発生した場合、米海兵隊は分散展開した小規模部隊を用いて、中国軍の艦艇や航空機を発見・追尾し、地対艦ミサイルなどで攻撃する「遠征前方基地作戦(Expeditionary Advanced Base Operations:EABO)」を遂行します。本稿では、EABOの全体像と歴史的背景、日米共同訓練での実証、分散展開部隊が直面する具体的判断、そして日米自衛隊との連携や架空の物語が示す行動基準の違いなどを総合的に解説します。
EABOの概要
EABOは、敵の接近阻止・領域拒否(Anti-Access/Area-Denial)に対し、脅威圏内に小規模前進基地(EAB)を確保・運用し、制海・制空支援やミサイル攻撃、補給拠点として機能させる海兵隊の新たな作戦コンセプトです。前進基地には、対艦・対空ミサイルやレーダー、前方航空給油地点(FARP)などを設置し、敵兵器の射程外部から「インサイド部隊」と「アウトサイド部隊」による二重態勢で運用します:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
歴史的背景:戦力デザイン2030とLOCEとの連携
米海兵隊は2016年に発表した「海兵隊作戦コンセプト(2016 MOC)」で、EABOを制海支援や前哨機能、前方兵站ハブとしての強化課題に掲げました。さらに、2020年に公表された「戦力デザイン2030(Force Design 2030)」では、中国を「主たる基準となる脅威(pacing threat)」と位置づけ、EABOおよび分散型海上作戦(Distributed Maritime Operations:DMO)との相互補完を図ることで、より分散かつ機動的な部隊運用を志向しています:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
分散展開部隊が直面する具体的判断
分散展開した小規模部隊は、島しょ部や離島に短期間で上陸し、センサー設置やミサイル配置、地形選定を行う際に「兵器交戦圏(WEZ)内での持久力確保」「敵偵察や襲撃リスクとミッションクリティカル装備の優先度」「補給線遮断時の自律的補給手段」「民間者・友軍勢力との識別基準」など、瞬時に多面的な判断を迫られます。特に、敵の長距離精密兵器射程内での活動となるため、秒単位の意思決定と無人機や無線傍受による情報収集能力が生死を分ける要因となります。
日米共同訓練での実証
米海兵隊は2023年3月、沖縄県うるま市で陸上自衛隊と共同訓練を実施しました。第3海兵機動展開部隊と陸自第5普通科連隊が、島しょ部への分散上陸や地対艦ミサイル運用、MV-22オスプレイによる迅速展開を試行し、EABOの想定能力を検証しました:contentReference[oaicite:2]{index=2}。また、久米島訓練ではレーダー設営や電子戦機材運用を含む全地対艦能力を実証し、夜間・悪天候下での「インサイド部隊」の持久的任務遂行を成功させています:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
架空の物語が浮き彫りにした行動基準の違い
昨年、海兵隊大尉が発表した架空のストーリーでは、分散部隊が中国沿岸監視に成功した一方で、民間漁船との識別ミスや友軍支援要請のタイミングを逸し、仲間を危機に追い込む場面が描かれました。この物語は「自衛隊とは異なり、海兵隊は攻撃・待機・退避の三段階判断を現場指揮官に一任する」運用基準を示唆し、米海兵隊が持つ即断即決の戦術思想を象徴しています。
今後の課題と展望
EABOは米海兵隊単独ではなく、海軍や空軍、宇宙軍、さらには友軍である自衛隊との多層的連携が不可欠です。今後は、情報共有・火力統合・兵站ネットワークのシームレス化を進めることで、琉球・南西諸島から台湾海峡に至る「第1列島線」での統合防衛体制を構築する必要があります。また、無人プラットフォームや人工知能を活用した自律分散運用の研究開発も加速中です。
結論
「遠征前方基地作戦(EABO)」は、台湾有事や南西諸島防衛の新たな鍵を握る作戦コンセプトです。分散展開する小規模部隊は、自らの判断で攻撃・防御・退避を瞬時に決断しなければならず、そのための訓練と装備・情報基盤の強化が急務となります。日米両軍の連携を深化させることで、EABOの実効性を高め、有事における抑止力と対応能力を飛躍的に向上させることが期待されます。


コメント:0 件
まだコメントはありません。