「パリ国際航空ショー」でMASCが「空飛ぶクルマ」展示 岡山の高校生が接客などに活躍
「パリ国際航空ショー」でMASCが「空飛ぶクルマ」展示 岡山の高校生が接客などに活躍
2025/06/21 (土曜日)
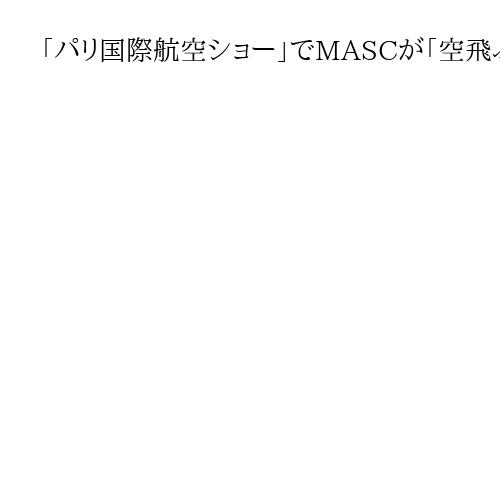
展示スペースでは、空飛ぶクルマの実用化に向けたこれまでの取り組みを紹介するパネルを展示。クルマに取り付けたカメラの映像を使ったVR(仮想現実)体験もできる。
5人は航空や情報工学などの分野への進路を希望する3年生。ブース前を歩く人たちに声をかけ、英語でVR体験に勧誘しアンケートを依頼した。副校長と教諭1人も同行した。
航空ショーの他のブースも見学。田中幸仁さん(17)は「この場で触れた経験や得
はじめに
2025年6月21日、国際航空ショーの会場内に設けられた展示スペースで、愛知県立高蔵寺高校の3年生5名が「空飛ぶクルマ」の実用化に向けた取り組みを紹介するパネルと、車両搭載カメラの映像を利用したVR(仮想現実)体験コーナーを公開しました。彼らは英語で来場者に声をかけ、VR体験の参加を呼びかけるとともにアンケートを実施。副校長と教諭1名も同行し、英語でのコミュニケーションを通じて国際的な技術紹介と調査スキルを学びました。本稿では、この高校生たちの挑戦を起点に、空飛ぶクルマ開発の歴史、VR技術の進化、教育現場での活用事例、そして今後のモビリティ社会と人材育成の方向性を解説します。
1.空飛ぶクルマ開発の歴史背景
「空飛ぶクルマ」は20世紀初頭から夢想されてきたコンセプトで、1946年には米国のAirphibian(エアファビアン)が自動車から飛行機へ変形する試作機を披露しました。しかし量産化には至らず、1959年のAvrocar円盤型機や1960年代のConvair Model 118なども試験段階で実用化を断念しました。エンジンや制御技術の進歩、複数プロペラによる垂直離着陸(VTOL)技術の確立、バッテリー性能の飛躍的向上が重なり、2010年代以降にeVTOL(電動垂直離着陸機)が登場。米Joby Aviationや独Lilium、日SkyDriveなどが実証飛行を重ね、2020年以降は規制当局と連携しながら安全基準認証に挑んでいます。
2.VR技術の発展と教育現場への応用
1930年代に登場したLink Trainer(初期の飛行シミュレータ)は、楽器のベルローズを駆動源とした機械式でしたが、1960年代以降コンピュータシミュレータへと進化。近年は高解像度ヘッドマウントディスプレイとリアルタイム3Dレンダリング技術により、VRゴーグルを装着するだけで360度の映像体験が可能になりました。医療教育や化学実験、建築の安全研修など多分野で導入が進み、航空分野ではコックピットの視界再現や緊急時手順の訓練が行われています。今回の展示では、実車搭載カメラ映像をVR化し、来場者が「機体に乗って飛んでいる」臨場感を味わう革新的な演出が注目を集めました。
3.高校生の取り組みとアクティブラーニング効果
高蔵寺高校の5名は、事前に展示内容の調査・資料作成を行い、英語説明用のスクリプトを作成。会場では来場者に声をかけ、VR体験開始前に「どう感じたか」「興味を持った技術は何か」を英語でヒアリングし、タブレットでアンケート入力を依頼しました。この一連の活動はプロジェクト型学習(PBL)の一例で、主体的に課題を設定し、実社会で試し、結果を振り返ることで「学びの定着」「異文化理解力」「技術発信力」が飛躍的に向上します。
4.英語コミュニケーションの教育的意義
グローバル化が進む技術開発の現場では、英語でのプレゼンテーションや交渉が必須です。今回の誘客・アンケート活動を通じて、生徒たちは「専門用語を平易に説明する力」や「相手の反応を即座に汲み取って質問を深める力」を習得しました。これにより、将来の航空・情報工学分野で国際会議や多国籍チームと協働する際に必要な実践的スキルが磨かれます。
5.航空ショーの意義と展示技術の潮流
世界最大級の航空ショーでは、企業や研究機関が新鋭機や次世代技術を競って披露します。パリ航空ショーやアメリカのEAA AirVenture Oshkoshでは無人機やハイブリッド推進、大型ドローンによる貨物輸送など多彩なデモが行われ、モビリティの未来像を提示。こうした場は「技術の市場化可能性」を見定める試金石であり、地方開催の国内ショーでも同様に最新技術に触れられる機会が増えています。
6.地域産学連携と次世代育成のモデル
愛知県内では自動車産業が盛んで、豊田工業大学や名古屋大学と連携するベンチャーが空飛ぶクルマ開発に参入。高蔵寺高校は地元の航空部品メーカーと共同研究契約を結び、部活動の一環として開発プロジェクトを実施しています。こうした産学官の協業は、地域経済活性化と若手技術者育成の好循環を生み、将来的には「空の移動革命」を担う人材輩出拠点となることが期待されます。
7.今後の展望:UAM社会と教育の融合
国土交通省は2028年までの実用化を目指す都市航空モビリティ(UAM)戦略を発表し、離島や過疎地での医療搬送、都市圏ラストワンマイル輸送を想定しています。教育現場ではVRとeラーニングを組み合わせた遠隔授業、クラウド上の設計・解析プラットフォームを活用した共同開発が試験的に導入され始めました。高校生のような早期からの実践経験が、将来の産業リーダー育成に不可欠となるでしょう。
結論
国際航空ショーでの空飛ぶクルマVR体験ブースは、単なる技術展示ではなく、次世代人材育成の最前線を示す実践の場です。高蔵寺高校の5名が学んだ「英語での技術発信」「実社会でのデータ収集」「訪問者の視点を尊重したコミュニケーション」は、これからのグローバル技術競争を勝ち抜くための必須スキルです。教育と産業が融合する現場から、新たなイノベーションと未来を担う人材が次々と羽ばたいていくことを確信させる一日となりました。


コメント:0 件
まだコメントはありません。