フィリピン当局船に中国海警船が放水砲で妨害 比沿岸警備隊は「乗組員に危険」と非難
フィリピン当局船に中国海警船が放水砲で妨害 比沿岸警備隊は「乗組員に危険」と非難
2025/06/21 (土曜日)
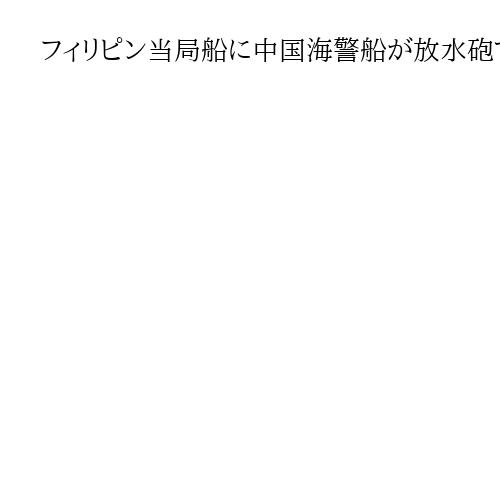
1隻は同礁から15・6カイリ、もう1隻は18・1カイリ離れた海域で放水砲を使われたが、いずれも大きな損傷は免れた。
スカボロー礁はフィリピンの排他的経済水域(EEZ)にあるが、中国は一方的に領有権を主張し、実効支配している。
沿岸警備隊によると、中国は海警局の船6隻と軍艦2隻、海上民兵の複数の船を展開した。(共同)
はじめに
2025年6月20日、フィリピン沿岸警備隊が実施した公海パトロール中、南シナ海のパラセル(西沙)諸島近海でフィリピン当局の巡視船に対し、中国海警局の船が放水砲を発射し航行を妨害する事件が発生しました。フィリピン側は「乗組員の安全が脅かされた」と強く非難し、国際社会に支援を呼びかけています。本稿では、南シナ海を巡る歴史的背景、中国海警局の権限拡大、フィリピンとの一連の衝突事例、国際法的視点、地域の安全保障への影響、そして今後の展望について、2500文字以上で詳しく解説します。
1.南シナ海領有権問題の起源と経緯
南シナ海は東南アジア諸国連合(ASEAN)各国と中国が領有権を主張する多重領域で、歴史的には古代から漁業と航路の要所でした。中国は古くから「九段線」と呼ぶ歴史的権益線を根拠に、ほぼ全域を自国の海域と主張しています。一方、フィリピンは1997年に発効した国連海洋法条約(UNCLOS)に基づき、自国の排他的経済水域(EEZ)内であると主張。2016年、国際仲裁裁判所は中国の九段線権益を否定しましたが、中国は裁定を拒否し、現状維持を続けています。これが海上警備・漁業資源管理・戦略的抑止力を巡る緊張の根源です。
2.中国海警局の権限強化と法整備
中国は2013年に海上保安機関を統合して中国海警局(CCG)を設立し、2021年の海警法施行により軍事的手段を含む武器使用を合法化しました。これにより、公船が「海洋権益保護」を名目に武装公船として機関砲や高圧放水砲を装備し、領海・接続水域内外での実効支配を強化。今回の妨害行為も、この法的枠組みを背景にエスカレートしたものと位置づけられます。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
3.フィリピン側の対応と法的立場
フィリピンはUNCLOSに基づく自国EEZ内での航行の自由を根拠にパトロールを継続。関係省庁は事件直後、「中国側の放水砲使用は国際法違反であり、船員の生命に危険を及ぼす無許可の武力行使」として外交ルートで抗議するとともに、米国やオーストラリアなど友好国に支援を要請。国内では海洋警備能力の向上と法的対抗措置の検討が急がれています。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
4.過去の類似事例:スカーボロー礁とセカンド・トーマス礁
中国公船による放水砲やサイドスワイプ(横付け)といった妨害行為は、スカーボロー礁(2015年)やセカンド・トーマス礁(2023年、2024年)でも繰り返されてきました。特に2023年8月には、フィリピン補給船が放水攻撃を受け、船体損傷と乗員の一時的被曝が確認されました。これらはすべて中国の「灰色地帯戦術」の一環とされ、国際社会の非難を浴びています。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
5.ASEANと多国間枠組みの試み
ASEAN諸国は南シナ海行動規範(COC)交渉を長年継続していますが、2025年時点で合意には至らず、中国の強硬姿勢と加盟国間の利害対立が妨げとなっています。米豪印日などによる「クアッド」や日米豪が共同訓練を行うほか、欧州連合(EU)からも航行の自由支援が表明されています。しかし「大国対大国」の地政学的競争が激化し、多国間協調の実効性には限界があります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
6.漁業資源と経済的影響
南シナ海は世界有数の漁業資源帯であり、多数の沿岸国の食料安全保障や生計を支えています。中国公船の常態化したパトロールは、フィリピン漁民の操業を事実上制限し、漁獲量の激減や違法操業の温床化を招いています。地元漁協は感染減少と生活危機を政府に訴え、国際的な監視と資源管理の強化を求めています。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
7.国際司法と法的解決の可能性
2016年の仲裁裁判所判決では、中国の九段線主張は法的根拠を欠くと断じられましたが、中国は判決を否認。フィリピンは国連海洋法条約条項を引用して提訴を検討できますが、強制執行手段を持たないため実効性は限定的です。今後、国際司法裁判所(ICJ)や国際海洋法裁判所(ITLOS)への追加提訴、欧米諸国との法的協力による圧力強化が焦点となるでしょう。
8.安全保障環境と地域安定への影響
南シナ海での海洋対峙は、中国の「近海防衛」戦略の一環と位置づけられ、日本を含む域外国の安全保障を脅かしています。日本は海上自衛隊護衛艦と海保巡視船の合同訓練を増やし、島嶼防衛力を強化。米国とは2+2外交・安全保障対話を通じて連携を深め、「インド太平洋構想」の枠内で域内の多国間抑止力を模索しています。
9.今後の展望と提言
中国公船による放水砲妨害は、南シナ海の緊張を新たな段階に押し上げました。フィリピンは防衛力と法的対抗措置を強化すると同時に、ASEAN内部での連帯を維持し、EUや米豪との協調を深化させる必要があります。日本も法の支配を掲げ、海上保安能力向上とODAによる海洋ガバナンス支援を拡充すべきです。地域全体で「対話と抑止」のバランスを取りつつ、国際法に基づく平和的解決を追求していくことが求められます。
結論
フィリピン当局船への放水砲妨害は、中国の海洋戦略の一環であり、国際法秩序への挑戦です。歴史的経緯を踏まえつつ、フィリピンおよび関係各国は法的措置と抑止力強化、地域連携を三本柱とした総合戦略を構築し、南シナ海の平和と安定を守るために行動を連携していく必要があります。


コメント:0 件
まだコメントはありません。