尖閣周辺に機関砲搭載の中国海警局船4隻、217日連続確認 海保巡視船が警告
尖閣周辺に機関砲搭載の中国海警局船4隻、217日連続確認 海保巡視船が警告
2025/06/23 (月曜日)
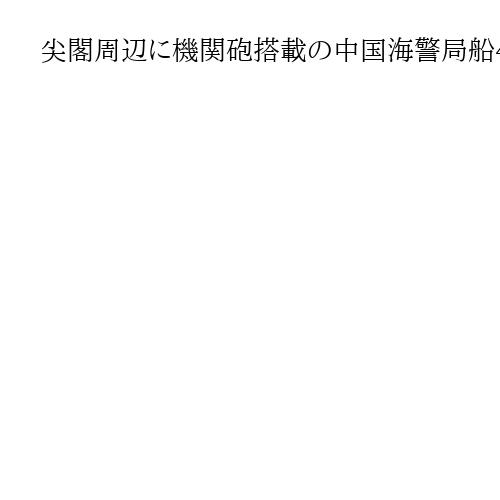
第11管区海上保安本部(那覇)によると、いずれも機関砲を搭載。領海に近づかないよう巡視船が警告した。
尖閣周辺で機関砲搭載の中国船が接近
2025年6月23日、第11管区海上保安本部(那覇)は、尖閣諸島周辺の接続水域内で中国公船数隻が機関砲を搭載して航行しているのを確認し、領海侵入を防ぐため巡視船が警告射撃も辞さない姿勢で警告したと発表しました(出典:産経新聞2025年6月23日)。この事態は中国公船が機関砲を露出させたまま日本の排他的経済水域(EEZ)や接続水域に長期的に常駐し、周辺海域の実効支配を強める動きの一環とみられます。
機関砲搭載公船の実態と機動力
中国公船(海警局所属船艇)はPL(巡視船)やPS(警備救難艇)などの大型船艇に30mm機関砲や37mm機関砲を装備し、日本の巡視船よりも強力な火力を誇ります。これら船艇は最大速力20~25ノットで航行可能で、接続水域内での活動において日本側巡視船を圧倒するケースが増えています。那覇海保が警告を行っても、公船側は航行を続ける事例が相次いでおり、海上保安庁の緊張が高まっています。
接続水域と領海警備の法的枠組み
国連海洋法条約(UNCLOS)に基づき、日本の排他的経済水域は基線から200海里以内、接続水域は領海基線から24海里以内と規定されます。接続水域では「法の順守を確保する権利」が沿岸国に認められ、違法操業や密輸防止のため巡視活動が許されます。しかし、中国は接続水域まで公船を進入させることで「実効的支配」をアピールし、領海侵入時には機関砲をちらつかせる戦術を用いています。
尖閣諸島を巡る歴史的背景
尖閣諸島(日本名・魚釣島、久場島など)は1895年に日本政府の所管となりましたが、1971年の日中国交正常化交渉以降、中国政府が領有権を主張。1978年に日本が国有化すると、定期的に中国公船が接続水域や領海外側の接続水域へ侵入し、抗議活動を繰り返すようになりました。2008年以降、機関砲を搭載した大型公船による「常駐化」が顕著になり、海保の巡視体制見直しと装備強化が迫られています。
過去の類似事例との比較
2025年5月にも、中国公船4隻が同海域を航行し、那覇海保巡視船が警告射撃を行った事例があります(出典:琉球新報2025年5月5日)。同様の対峙は2012年の初機関砲搭載公船確認以降、年々頻度を増し、2025年3月時点で連続200日以上にわたり中国船が確認されました。かつては竹島周辺や南シナ海でも同様の「灰色地帯作戦」が展開されており、中国の海洋進出戦略の一環と位置づけられます。
第11管区海上保安本部の装備強化と対応
那覇海保はPLH型巡視船「りゅうきゅう」やPLH35「朝月」など大型巡視船を配備し、巡視船艇数を増強。加えて耐波堤高のヘリ搭載型巡視船やドローン監視システム、AIS(船舶自動識別装置)連携によるリアルタイム把握体制を強化しています。沿岸に設置する監視レーダー網も拡充され、電子戦にも対応できる交信・通信暗号化装置が導入されています。
中国側の戦術と海洋進出戦略
中国は「法の順守を確保する権利」を盾に接続水域での活動を正当化し、実際には漁業取締や海底資源調査、さらに軍事演習を行っています。機関砲搭載公船の常駐は、海上での威圧を通じて東シナ海と南シナ海での領有権主張を一体化させる戦術です。沿岸部での砂州造成や埋め立てによる人工島建設にも同様の目的があり、国際法解釈の争点となっています。
国際的な反応と地域安全保障
米国は2021年に台湾海峡での中国公船活動を「挑発行為」と非難し、海軍艦艇の通過を継続。一方、東南アジア諸国連合(ASEAN)も2016年の仲裁裁判所判決を支持しない中国に対し懸念を示しました。日本と米国は日米安保条約に基づき共同パトロールを実施し、また豪州やインドを巻き込む「クアッド(日米豪印戦略対話)」での海洋安全保障協力を強化しています。
国内法整備と法執行の強化
日本政府は2022年に海洋安全保障法を施行し、外国船舶の海上デモ阻止条項を設けました。また、公船に対する当該法の適用可否を巡る議論を踏まえ、警察・海保・海自の連携強化や、沿岸警備隊の設置構想も浮上しています。自衛隊艦艇の警備協力や警備部隊配備法案の審議も進み、海域防衛力の法的裏付けを拡充する流れが顕在化しています。
展望:抑止力強化と外交努力の両立
機関砲搭載の中国公船による威圧的航行は、日本の実効支配を脅かす重大事態です。抑止力強化として海保装備の充実、自衛隊との法整備による抑止力連携が急務ですが、一方で中国との外交対話窓口も維持し、地域協力枠組みでの対立緩和策を講じる必要があります。海洋法秩序の遵守と多国間の平和的解決を目指し、日本は国内法制と国際協力の両輪で課題に対応していくことが求められます。


コメント:0 件
まだコメントはありません。