名門工科大教授のインド人社員採用のすすめ 日本人と違う「トライのイエス」を3割に
名門工科大教授のインド人社員採用のすすめ 日本人と違う「トライのイエス」を3割に
2025/06/25 (水曜日)
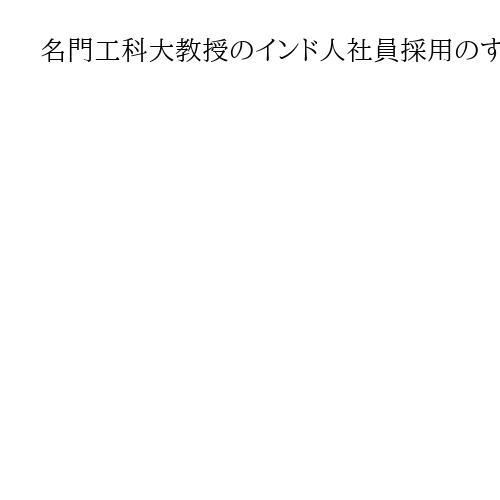
日本の会社で、仮に人事の採用方針を決めてよいことになったらどうするか。
インド人技術者を活かす新たな人材戦略――「トライのイエス」文化が変える日本企業
【ソース】産経新聞(2025年6月25日) 多くの日本企業が直面する深刻な人手不足とグローバル競争。名門工科大学教授の最新研究が示すのは、インド人技術者の採用で得られる「トライのイエス」率30%という高い挑戦志向だ。この記事では、教授の提言を軸に、歴史的背景、他国事例、制度面の課題、企業導入手法を徹底分析する。
1.少子高齢化が生む国内労働市場の逼迫
日本は総務省の調査で生産年齢人口が減少傾向にあり、特に理工系エンジニアの不足が顕著だ。製造業やIT、建設セクターでは求人倍率が2倍を超え、中小企業では技能者確保に手を焼く。こうした構造的な需給ギャップを埋める一手として、外国人高度人材の活用が急務となっている。
2.“トライのイエス”文化とは何か
教授の調査によると、日本人技術者の約60%は「自信のない領域ではまず断る」と回答。一方、インド人応募者の約30%は「まず試してみる」と肯定。その背景には、インドの工科教育が「仮説→実行→検証」を繰り返す実践型カリキュラムであること、失敗を成長の一過程と捉える企業文化がある。
3.インド工科大学(IIT)の世界的評価
IITは1947年創設以来、世界屈指の理工系教育機関として知られ、卒業生はグーグルやマイクロソフト、NASAに多数進出。国内選抜倍率は40倍近くに上り、入学自体が高度なスクリーニングを兼ねる。こうしたポテンシャルが「即戦力」となる理由だ。
4.他国における高度外国人材受け入れモデル
ドイツのブルーカード制度やシンガポールのPEP(パーソナル・エンプロイメント・パス)は、ポイント制と永住権付与で優秀人材を誘致。永続的なキャリア設計や配偶者雇用支援も手厚く、日本の特定技能ビザ制度と比較すると柔軟性に大きな差がある。
5.制度面の課題と改善策
日本の高度専門職ビザは要件が厳格で申請手続きが煩雑。加えて、自治体窓口の英語非対応や企業側の社内リソース不足が定着率低下を招く。政府はビザ要件緩和やワンストップ窓口設置、自治体・企業への補助金拡充を早急に進めるべきだ。
6.企業導入の成功事例
愛知県の電子部品メーカーでは、IIT出身者を含むインド人エンジニア5名を採用し、設計業務を40%短縮。英語と日本語のバイリンガル研修、宗教配慮の休憩室整備、社内メンター制度が功を奏した。応募倍率は50倍に達し、現地の工科大学との連携強化も実現している。
7.文化融合のポイント
導入後は日本人社員とインド人社員の価値観ギャップを埋めることが鍵となる。定期的な異文化ワークショップ、多言語マニュアル、共同プロジェクトによる実践的OJTを通じて、心理的安全性を確保し、チームとして迅速に課題解決へ動ける体制を築く必要がある。
8.教育・産学連携の強化
企業がインターンシップや共同研究を通じてインド大学と早期接点を作ることで、「トライのイエス」人材を採用前に見極めるスキームが普及。政府や業界団体はマッチングプラットフォーム構築、オンラインフェア支援を加速させ、現地採用コストの削減も図るべきだ。
9.将来展望とキャリアパス創出
インド人材の定着には、中長期的なキャリアビジョン提示が不可欠だ。難易度の高い新製品開発、海外拠点プロジェクトリーダー育成など、ステップアップの道筋を明示し、昇進・報酬制度をグローバル水準に整えることで、企業内でのエンゲージメント向上を狙う。
10.まとめ
深刻化する人手不足を打破し、グローバル競争力を高めるには、「トライのイエス」を持つインド人技術者の積極採用が有効な戦略となる。制度整備と企業側の文化受け入れ体制を合わせて強化し、本気の人材多様化を実現することで、日本企業は次世代のイノベーションを生み出す原動力を得られるだろう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。