中国が日比連携をけん制、海自艦のマニラ寄港に反発「日本は南シナ海の当事国ではない」
中国が日比連携をけん制、海自艦のマニラ寄港に反発「日本は南シナ海の当事国ではない」
2025/06/27 (金曜日)
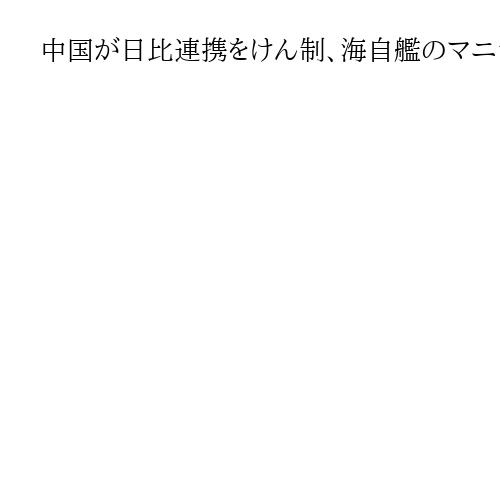
張氏は「日本は南シナ海問題の当事国ではない。主権侵害や挑発行為をあおるべきではない」と強調した。(共同)
はじめに
2025年6月22日、海上自衛隊の護衛艦2隻がフィリピン・マニラの港に寄港し、比海軍から歓迎を受けました。この訪問は日比両国の防衛協力強化の一環ですが、中国はこれに強く反発し、「日本は南シナ海の当事国ではない」とけん制する声明を発表しました。中国側は「日本が南シナ海問題に介入する権利はない」と主張し、地域の平和と安定を損なう恐れがあると警告しました。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
南シナ海をめぐる長年の緊張
南シナ海をめぐる領有権紛争は、1947年に中華民国政府が示した「九段線」や、1895年の清朝末期にさかのぼる歴史的経緯があります。九段線はフィリピン、ベトナム、マレーシア、ブルネイ、台湾など複数国のEEZ(排他的経済水域)と重複しており、資源権や航行の自由をめぐる対立を招いてきました。1982年の国連海洋法条約(UNCLOS)採択以降、各国は国際法に基づく解決を求めつつも、実効支配や海洋パトロールを強化し、緊張が高まっています。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
2016年の仲裁裁判と国際法的権威
2013年、フィリピンは中国を相手どって南シナ海に関する仲裁手続きを開始し、2016年7月12日に北京の「九段線」に法的根拠はないとの裁定を受けました。この裁定は「中国の歴史的権利主張はUNCLOSの下で認められない」と結論づけ、中国の有人・無人島嶼に対する海域設定が違法であると断じました。しかし、中国はこの裁定を全面的に拒否し、以降も人工島造成やミサイル配備を含む実効支配を続けています。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
中国の実効支配強化
中国はパラセル諸島やスプラトリー諸島で大規模な埋め立て・造成を実施し、滑走路やレーダー塔、ミサイルシステムを配備しました。これにより、南シナ海全域における空域識別圏(ADIZ)の設定や海洋パトロールの頻度が大幅に増加し、近隣国との衝突リスクが高まっています。また、2015年以降、中国人民解放軍空軍が南シナ海で定期的な巡航を開始し、軍事的緊張は一層深刻化しました。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
日比防衛協力の深化
2025年2月、マニラで行われた中谷元防衛相とギルベルト・テオドロ比国防相会談では、合同訓練や寄港、情報共有などを含む防衛協力の強化で合意しました。また、日比間の「相互アクセス協定(RAA)」は2024年7月に署名され、2025年6月6日には日本の国会で承認され、両国艦艇や部隊の相互上陸・訓練が可能となりました。これにより、日比両国は中国の海洋進出に対抗し、インド太平洋地域の平和と安定を確保する体制を整えています。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
インド太平洋戦略と多国間演習
米国・フィリピンは2025年6月初旬に南シナ海で7回目となる合同海洋演習を実施し、相互運用性の向上を図りました。日本も参加し、日米比3か国による連携は一段と深化しています。中国側はこれを「地域の安定を損なう行為」と非難し、日本に対して「現実に即した行動」を求めていますが、日米比3か国は引き続き「法の支配」と「航行の自由」の擁護を掲げ、共同演習や定例会合を通じて抑止力を維持しています。:contentReference[oaicite:5]{index=5}
今後の展望
南シナ海情勢は2025年以降も中国の海洋進出、中国海警局や人民解放軍の活動、フィリピンやベトナムとの摩擦、そして日米同盟・多国間協力の動向によって左右されます。中国の「九段線」主張と国際法的裁定のギャップ、実効支配強化への対抗策、RAAやGSOMIAなど防衛協力枠組みの運用状況を注視するとともに、ASEAN諸国や国連を含む多角的対話の推進が求められています。:contentReference[oaicite:6]{index=6}


コメント:0 件
まだコメントはありません。