ペルー最高峰で遭難の寺田紗規さん、病院へ搬送 一緒に登山の医師は死亡確認
ペルー最高峰で遭難の寺田紗規さん、病院へ搬送 一緒に登山の医師は死亡確認
2025/06/27 (金曜日)
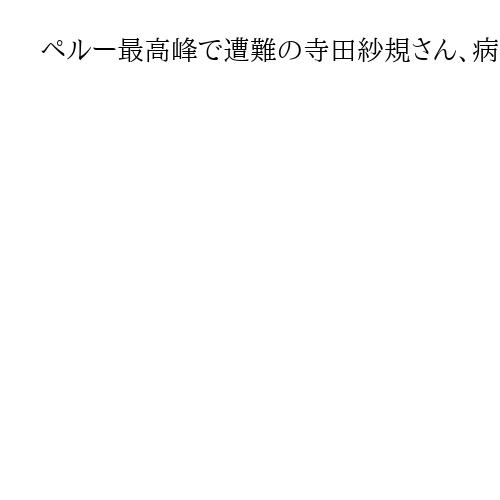
対策本部などによると、寺田さんは救助隊と下山を進め、26日に標高約4000メートル付近にある避難小屋に到着した後、ヘリコプターで病院に搬送された。
寺田さんと一緒に登山中だった医師で登山家の稲田千秋さん(40)=山梨県北杜市=は25日に発見された際、意識がなく、その後に山中で死亡が確認された。
ペルーメディアによると、ワスカラン山は南米で最も登るのが難しい山の一つ。高山病のリスクが高く、山頂付
ワスカラン山遭難、寺田紗規さん救助・稲田千秋さん死亡確認──高所遭難の背景と救助活動の現場
2025年6月26日、ペルー最高峰ワスカラン山(標高6,768m)を登山中だった医師・登山家の稲田千秋さん(40)と寺田紗規さん(35)が遭難した件で、寺田さんは同日、標高約4,000m地点の避難小屋へ下山後にヘリで病院へ搬送された。一方、稲田さんは25日に救助隊に発見された際すでに意識を失い、その後山中で死亡が確認された。
ワスカラン山の地理的・歴史的概要
ワスカラン山はペルー・アンカシュ州ユンガイ県に位置し、コルディエラ・ブランカ山脈の主峰として知られる。標高6,768mの南峰は国内最高峰で、世界的にも赤道付近の熱帯圏で最も高い山として評価される。中新世から鮮新世にかけて隆起し、氷河侵食によって鋭い稜線と多数の氷河を形成した。
登山ルートと難易度
一般的な登攀は西側のムショ集落からスタートし、ビバークキャンプを経て「ラ・ガルガンタ」と呼ばれるコルへ至る。片道5~7日を要するルートで、技術グレードはやや容易~中程度の困難とされるが、高度順応や天候変化、雪崩・クレバスのリスクは顕著であり、南米でも難易度の高い山として知られる。
1970年大雪崩災害の教訓
1970年5月31日の大地震に伴う山体崩壊では、北峰側から大量の岩塊と氷雪が谷を襲い、ユンガイとランラヒルカの集落を壊滅。この災害で約20,000人が死亡し、以降の避難計画や早期警報システムは世界の高地災害対策でモデルとされた。
遭難当日の状況と救助活動
稲田さんと寺田さんは6月24日深夜、頂上直下で稲田さんが高山病と低体温症の疑いで行動不能に。SOSを発信した後、24日夕から救助体制が発動。標高差約1,000mを徒歩で降下しながら、緊急医療処置を行いつつ、25日午後に両名を発見。稲田さんは意識不明のまま死亡が確認され、寺田さんは翌26日にヘリで搬送された。
高山病と低体温症のリスク
標高5,500m以上では酸素濃度が半減し、高山病や高所肺浮腫のリスクが急増。夜間の気温は氷点下20℃を下回ることもあり、防寒装備と適切なシェルターがない場合、低体温症が致命的となり得る。
日本とペルーの救助体制連携
日本からの医療アドバイザーやオペレーターが現地ガイドや民間レスキュー隊と連携し、衛星通信用機器を介した指示を実施。徒歩アプローチとヘリ搬送を組み合わせた複合的な救助方式が採用され、国際的な協力体制が評価されている。
登山家ネットワークと支援団体の役割
稲田さん所属の山岳救急教育団体は、SOS受信から搬送後の医療連携までを支える体制を提供。日本の登山家コミュニティでも安全教育や装備標準の普及が進んでおり、高所挑戦の安全性向上に寄与している。
遭難事故の統計と教訓
アンデス地域では年間数百件の遭難事故が報告され、その死亡率は約10%。高所では天候急変と高山病の合併が主因とされており、過密日程や装備不備もリスク要因となる。国内外の事例から、十分な順応日程と救助計画の周到な準備が不可欠とされる。
気候変動がもたらす新たなリスク
アンデス氷河の融解が進み、クレバスや雪崩の危険度が増加。登攀ルートの安全性は変動しており、デジタル地形解析やリアルタイム気象データを活用した支援システムの導入が求められている。
まとめと今後の課題
今回の遭難救助は、高地救助の複雑さと国際協力の重要性を浮き彫りにした。登山者には適切な順応日程と最新装備の携行、複数の救助計画策定が求められる。関係機関は救助訓練や情報共有を強化し、登山安全のさらなる向上を目指す必要がある。


コメント:0 件
まだコメントはありません。