中国、日本水産物の輸入再開を発表 23年8月の処理水放出以降初めて 10都県は対象外
中国、日本水産物の輸入再開を発表 23年8月の処理水放出以降初めて 10都県は対象外
2025/06/30 (月曜日)
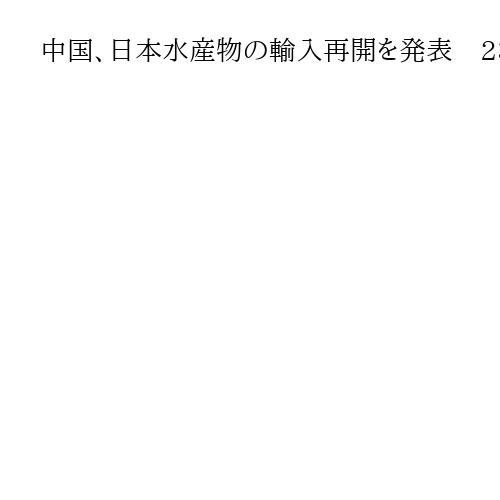
10都県は宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、長野。
日本政府は5月、日本産水産物の対中輸出再開に向けた手続きを開始することで中国側と合意したと発表。中国側が日本の輸出事業者を登録する必要があり、輸出再開まで少なくとも数カ月程度はかかるとみられていた。
輸出停止前の22年の水産物輸出額は、中国が871億円で国・地域別の相手国で最大だった。ホタテやナマコが主力品で、北海道などの
対中水産物輸出再開へ──日本政府と中国側が手続き合意、10都県に拠点集中
2025年5月、日本政府は中国側と協議し、日本産水産物の対中輸出再開に向けた手続きを開始することで合意したと発表した。中国は登録制を採用し、輸出事業者の審査・承認完了後に再開となるため、数カ月の準備期間が見込まれている。
輸出停止の経緯と背景
2010年代後半、中国国内で日本由来の放射性物質検出報道が相次ぎ、日本産食品全般に対する輸入規制が強化。2023年初頭には政府間協議が中断され、水産物輸出は事実上停止状態となった。ホタテ、ナマコ、昆布など北海道産が主力で、停止前の2022年度には対中輸出額871億円でトップだった。
10都県の役割と産地分布
- 北海道・青森・宮城・福島:ホタテ養殖の中核地域
- 茨城・千葉・神奈川:マダイ、アジ、サバの漁獲基地
- 新潟・長野:高級川魚(イワナ、ヤマメ)や淡水魚
- 埼玉・東京・栃木・群馬:加工業と物流拠点として登録業者が集中
これら10都県からの出荷が再開後の中心を担い、特に北日本のホタテは高品質ブランドとして再評価される見込みだ。
登録手続きの流れと課題
- 日本側:輸出事業者の衛生管理・放射能検査体制報告書の提出
- 中国側:現地検疫当局による工場査察、書類審査
- 承認後:輸出リストへの正式登録、輸出開始許可証の発行
主な課題は書類審査に要する時間と、中国側検査員の来日スケジュール調整。また、輸出規模を確保するため、事業者間の共同輸送・合同検査の仕組み整備が急務である。
国際競争力と市場展望
中国市場ではロシア産やベトナム産水産物がシェアを拡大中だが、日本産は品質・安全性の高さで優位性を持つ。ホタテ価格はキログラムあたり平均600円程度と高値安定傾向で、再開後は中国沿岸部の高級レストランやEC販路でプレミアム展開が期待される。
国内産業への影響と対策
輸出停止が続いた間、国内向け価格が下落し、生産者の収益を圧迫。再開後は出荷調整や価格安定策が必要となる。農水省は「輸出再開枠組み会議」を7月に開催し、輸出拡大支援策や共同物流の助成を議論する予定だ。
まとめ
日本産水産物の対中輸出再開は、東アジアの食文化における日本ブランドの復権を意味する。一方で、登録手続きの時間的制約、共同輸送・検査体制の整備、国内価格安定策など多くの課題がある。政府と事業者は連携し、品質保証・効率的物流・市場開拓を推進する必要がある。再開後は、ホタテをはじめとする高級水産物が中国市場で高い評価を取り戻し、東北・北海道の漁業振興や地域経済活性化に寄与することが期待される。


コメント:0 件
まだコメントはありません。