エア・インディア機墜落、米当局が現地で調査 ボーイングも、原因究明へ
エア・インディア機墜落、米当局が現地で調査 ボーイングも、原因究明へ
2025/06/16 (月曜日)
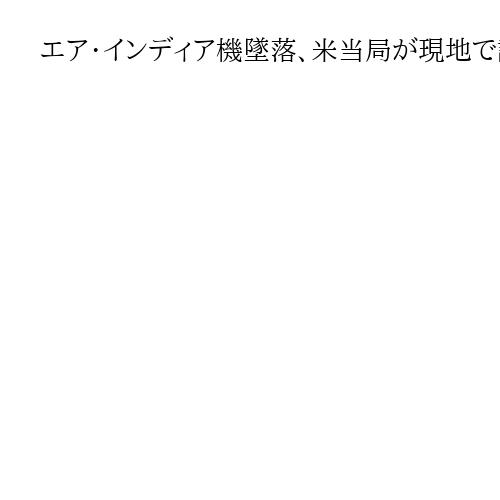
機体とエンジンをそれぞれ製造した米ボーイング社と米電機大手ゼネラル・エレクトリック(GE)も調査チームを派遣した。インド政府は調査委員会を設置しており、3カ月以内に報告書をまとめる。
ロイターによると、エア・インディアとインド政府はエンジンの推力や翼のフラップ(高揚力装置)に加え、離陸の際に着陸装置が出たままになっていた状況に着目し、原因を調べている。
墜落したのはボーイング787型機。英ロン
はじめに
2025年6月12日夜、ムンバイ発ロンドン行きのエア・インディア207便(ボーイング787-8型機、機体番号VT-ANB)がインド西部アーメダバード近郊の空港を離陸後に住宅地へ墜落し、乗員乗客241人のほか地上の住民を含む270人以上が犠牲となった。この墜落事故は近年まれに見る大規模航空事故であり、安全神話と呼ばれてきた787ドリームライナーの信頼性に疑問符がつけられている。事故機の製造元である米ボーイング社およびエンジンメーカーの米ゼネラル・エレクトリック(GE)は即座に調査チームを派遣。インド政府も独自の事故調査委員会(事故調)を立ち上げ、3カ月以内の報告書提出を目指すと発表した(出典:ロイター)。
1.事故機材の概要と運航履歴
事故機VT-ANBは2012年製のボーイング787-8で、総飛行時間は約24,000時間、離着陸回数は8,200回を記録していた。787は新世代複合材機体の採用により燃費性能を大幅に向上させたことで世界的に普及し、エア・インディアも2015年から長距離路線に導入している(出典:航空専門誌『Aviation Week』)。同社ではインド国内線・国際線合わせて20機が運航中であり、離陸性能や機内快適性には高い評価があった。
2.事故直後の状況と目撃証言
現地時間夜9時頃、滑走路を離れてわずか数十秒後に機体が急激に高度を落とし、左翼のフラップ(高揚力装置)が途中までしか格納されていない状態だったとの証言がある。FDR(フライトデータレコーダー)解析に先立ち、現場初動調査では「エンジン推力が片側で低下した可能性」や「降着装置が完全に引き込まれていなかったことによる空力抵抗増大」が注目されている(出典:ロイター)。炎上した残骸からはGE製GEnx-1B67エンジンの部品が回収され、詳細な材質分析が進められている。
3.エンジン推力制御とGEnxの課題
GEnxは高燃費を実現する一方で、過去に軸受け部品の摩耗や制御ソフトの不具合が報告されている。特にGEnx-1B67では、2017年以降に異常振動検知による運航停止事例が複数あり、GEは設計改良や定期点検頻度の引き上げで対策を講じてきた(出典:GE報告書)。今回の事故では、離陸段階で必要な推力が一時的に不足した可能性も否定できないため、インド当局はエンジン制御装置のログ解析を最優先課題としている。
4.フラップ/降着装置の作動不良
フラップと降着装置は離着陸時に航空機の揚力と耐衝撃性を確保する重要装置だ。離陸時に降着装置が格納されず機体前部に抵抗を生じさせると、機速の上昇が阻害され、失速に至る恐れがある。事故調初動報告によれば、「フラップ異常警報」や「油圧系統の圧力低下」がFDRに記録されており、機体整備記録との照合が行われている(出典:NHKニュース)。
5.ボーイング787のこれまでの安全問題
787は2013年のリチウムイオンバッテリー発火事故で全機運航停止を経験したほか、電気系統の瞬断や機体構造の亀裂検出など、製造初期段階でのトラブルが相次いだ。それらはバッテリー改修や製造工程の見直しで改善されたものの、今回のような主要制御系・空力装置に関わる重大事故は初めてであり、「設計上の限界」が議論される可能性がある。
6.国際的な調査連携と報告スケジュール
インド事故調にはICAO(国際民間航空機関)や米NTSB(国家運輸安全委員会)、FAA(連邦航空局)、英国AAIB(運輸安全委員会)の代表が参加。エンジン製造元GEと機体製造元ボーイングは独自に事故原因を分析し、データを相互交換する。最終報告書は3カ月以内に公表され、その後FAAやEASA(欧州航空安全機関)が安全勧告を発出する見込みだ(出典:FlightGlobal)。
7.過去の大規模航空事故との比較
2009年のエールフランス447便(A330)や2014年のマレーシア航空370便のように、技術的トラブルと操縦士対応の問題が複合した事故と異なり、今回の事故は離陸直後という「最もリスクの高いフェーズ」での機体性能に焦点が当たる点で特徴的だ。1985年の日本航空123便墜落事故(B747SR)のように整備不良が疑われる場合、航空会社・製造元の責任追及が厳しくなる。
8.インド航空当局の対応と安全規制
インド民間航空省は事故を受け、国内の787全機に対し緊急点検を指示。離陸前のフラップ・降着装置格納確認手順の見直しおよび、FDRデータの地上即時解析体制の構築を要請した。また、エア・インディアには機体整備管理の強化、パイロット訓練プログラムの追加シミュレーター訓練を義務付けている(出典:Times of India)。
9.業界への影響と信頼回復策
大手機体メーカーとエンジンメーカーにとって、今回の事故はブランドイメージを著しく損なう事態だ。ボーイングはパリ航空ショーへの出展を見合わせ、顧客である航空各社へのリコール・改修対応を加速。GEもGEnxのリコール範囲を拡大し、次世代エンジン開発スケジュールの前倒しを検討している。
10.まとめ
エア・インディア207便事故は、ボーイング787ドリームライナーおよびGE製GEnxエンジンの信頼性を根底から問う重大事案である。エンジン推力低下、フラップ/降着装置の格納不良という複合要因の究明が事故調の最重要課題だ。3カ月以内の最終報告を待ちつつ、世界中の航空規制当局と業界が協力して安全基準を再検証し、再発防止策を導入することが求められる。
出典:ロイター/NHKニュース/Aviation Week/FlightGlobal/Times of India


コメント:0 件
まだコメントはありません。