備蓄米追加放出の効果は 問題点も
備蓄米追加放出の効果は 問題点も
2025/06/11 (水曜日)
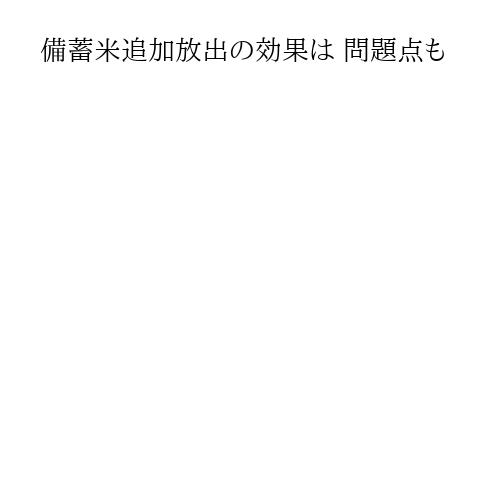
松平尚也宇都宮大学農学部助教、博士(農学・京都大学)、AMネット代表6/11(水) 10:31(写真:つのだよしお/アフロ) 小泉農水大臣は、6月10日、備蓄米20万トンを追加で放出すると表明した。対象となる備蓄米は、2021年産10万トンと20年産10万トンであり、11日から随意契約で小売業者に直接売り渡すとしている。対象はは大手・中小小売、米穀店(精米能力を有数業者)の全てで過去に契約した業者
政府備蓄米追加放出の概要
2025年6月10日、小泉進次郎農林水産大臣は政府備蓄米の追加放出として計20万トンを随意契約方式で小売事業者に売り渡す方針を表明した。対象は2021年産10万トンと2020年産10万トンで、うち2021年産については6月11日午前10時から申し込み受付を開始する。申し込み可能業者には大手チェーンから地域の米穀店まで含まれ、販売期限は2025年8月末までとされた。これにより消費者向け価格の下支えと家計負担の軽減を狙う。
政府備蓄米制度の成立と目的
日本の政府備蓄米制度は1974年の第1次オイルショックを背景に、食糧需給の緊急時対応を目的として創設された。コメ需給がひっ迫した際に市場価格の急騰を抑制し、食料安全保障の観点から一定量を備蓄しておく仕組みで、基本量は年間約30万トン前後で推移している。過去には凶作時の供給安定や価格調整を目的に繰り返し放出が行われてきた。
随意契約方式の特徴と意義
随意契約方式とは、入札によらず行政が個別に業者を指定して契約を締結する手法である。これにより入札準備期間や手続きに要する時間を短縮し、放出開始から店頭販売までのリードタイムを最小化できる。今回、小泉大臣が「スピードを最優先」と強調した背景には、急速な価格上昇への対応と夏場の需要期前に商品を店頭へ並べる必要性があった。
2021年産と2020年産備蓄米の品質と選定理由
2021年産は一部の地域で生産量が想定を上回り、長期低温貯蔵に適した品質の良好な米が選別された。2020年産は当初中小小売向けに放出されたものの一部が行き先を見つけられず残留していたため、合わせて追加放出する運びとなった。どちらも低温長期貯蔵米として風味・品質が保たれており、消費者の評価も高い。
申し込み手続きと業者要件
申し込み受付はオンラインで行われ、申請業者は「精米能力を有すること」「2025年8月末までに販売できる見込みがあること」を証明する書類の提出が求められる。上限数量は設定せず、複数回の再申請も可能な柔軟設計となっている。これにより大手スーパーから個人経営の米店まで幅広い業者が参加しやすい環境が整備された。
市場価格への影響と消費者メリット
備蓄米の追加放出により市場に供給量が一時的に増加し、5kg当たり約2000円前後での販売が見込まれる。これは直近の市場価格(5kgあたり約2400円)から約15~20%の価格低下をもたらす可能性があり、炊飯用米にかかる家計負担の軽減に寄与すると期待される。特に夏場の行楽シーズンや梅雨明け以降の需要増加期を見据えた施策と言える。
過去の放出事例との比較
2024年末に行われた2020年産備蓄米の初放出は公開入札方式が主体で、主に学校給食や法人需要向けに供給された。今回の随意契約方式による小売店直販は全国的にも前例が少なく、迅速な価格対策と“小売主導”の供給構造づくりに新たな意義がある。2009年の凶作時にも随意契約方式を一部で導入したが、小売店への直接販売拡大は初の試みである。
農家・JAへの影響と意見
JA関係者は「政府放出が頻繁化すれば市場価格の安定にはつながるが、生産者の所得確保には逆風となる可能性もある」と指摘する。一方で「過剰在庫が解消されることで需給バランスが整い、新米期に向けた価格形成がスムーズになる」とする声もあり、生産者と行政の微妙な調整が求められる。
消費者行動と販売現場の反応
放出初日から約1時間で30社以上の応募があったと農水省は発表しており、千葉県内の小売店では「通常のコメ販促とは異なり、消費者からの問い合わせが殺到した」と担当者が証言。都内の精米工場では「急ピッチで精米ラインを増設し、納品準備に追われている」といった声も聞かれる。販売現場の関心の高さがうかがえる。
今後のリスク管理と追加放出の可能性
備蓄米販売後の在庫状況を見極め、売れ残りが発生した場合は2020年産の追加放出や七期産の補完放出が検討される。政府は過去の残留リスクを踏まえ、売れ残りリスクを最小化するための在庫・品質管理体制を強化するとしている。また、転売防止のガイドラインを策定し、不正流通を抑制する方針も示した。
比較:海外の戦略備蓄活用事例
米国では戦略備蓄としてバイオ燃料用トウモロコシや大豆を備蓄しないものの、食糧危機時に併用できる農産物備蓄計画を検討中。欧州連合は緊急時に食糧支援を共同調達する「食糧安全備蓄メカニズム」を2023年に採択したが、民間小売への直接放出は例がない。日本の「小売直販型備蓄放出」は国際的にも独自性が高い手法と言える。
結論
政府備蓄米2021年・2020年産計20万トンの随意契約放出は、迅速な需給調整と消費者価格安定化を目的とした異例の施策である。過去の入札主体放出から一歩踏み出し、小売店を通じた直接販売という新たな供給経路を構築した点に注目が集まる。今後の販売動向と在庫管理、農家の所得確保とのバランスをいかに保つかが、持続可能なコメ市場運営のカギとなるだろう。


コメント:0 件
まだコメントはありません。