コメ平均価格 3週連続値下がり
コメ平均価格 3週連続値下がり
2025/06/17 (火曜日)
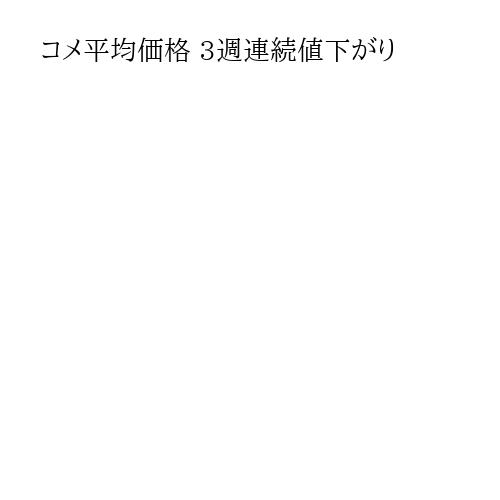
スーパーのコメ平均価格、3週連続値下がり…小泉農相「安心して買える水準にはなっていない」
はじめに:スーパーのコメ平均価格、3週連続値下がり…小泉農相「安心して買える水準にはなっていない」
2025年6月16日、農林水産省は全国のスーパーで6月2日~8日に販売されたコメ5kg袋の平均小売価格が前週比48円安の4,176円となり、3週連続で値下がりしたと発表しました。これにも関わらず、小泉進次郎農相は記者団に対し「国民の皆さんが安心して買える水準にはなっていない」と述べ、市場価格の一層の下落と流通促進策の継続的な実施を強調しました:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
今週の価格推移と内訳
詳細を見ると、銘柄米の平均価格は前週比14円高の4,443円、ブレンド米(備蓄米を混ぜたもの)は前週比64円安の3,834円となりました。全販売量に占めるブレンド米の比率は44%と、備蓄米放出以降で最高を記録。随意契約方式で放出された備蓄米を扱う店舗では、5kgあたり3,096円という低価格帯が定着しつつあります。地域差では最安が長野県の2,790円、最高が滋賀県の4,980円で、多くの地域は3,000円台前半が中心でした:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
備蓄米放出策の背景と政策動向
政府は2025年1月末に備蓄米の運用ルールを見直し、流通不足時にも随意契約で市場放出できるよう制度を改正しました。2025年3月には約15万トンの備蓄米を大手卸業者向けに入札・随意契約で放出し、3月下旬からスーパー等へ順次供給が始まっています。この緊急放出策は、前線的な需給調整ではなく、昨今の高騰を抑えるための価格抑制目的にシフトしており、政府が「1年以内に同量を買い戻す」条件での貸付的運用を行っています:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
価格高騰の構造的要因
コメ価格高騰の背景には、長年の減反政策による作付面積の縮小、農家の高齢化・担い手不足、天候不良による作柄不振など、構造的な供給制約があります。また、一年に一度の刈り取り収穫という特性上、需給の急変に柔軟に対応しづらい点も価格を押し上げる要因です。さらに、国産米の高価格を背景に民間企業による輸入米が急増し、2025年2月だけで523トンを輸入するなど、外食産業などが高関税を負担しても輸入に踏み切る動きが顕著です:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
歴史的な価格動向との比較
小売物価統計調査によると、2025年4月時点のコメ5kg平均価格は4,543円であり、わずか2か月で約367円の下落が見られます。しかし、2020年12月の平均価格(POSデータ)は2,036円と比較的安価で、パンデミック前後で価格はほぼ2倍に上昇したままです。さらに、2015年8月には過去10年で最安の1,799円を記録しており、現状価格はその約2.3倍という高い水準にあります:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
国際的な供給・価格動向との比較
世界市場では、2025年5月のタイ・バンコク港輸出(FOB)価格が431米ドル/トン(約62.44円/kg)となっており、5kg袋換算でおよそ3,122円相当です。日本の国内価格がこれを大きく上回っている背景には、国内生産のコスト高や小規模流通構造の非効率性が指摘されます。一方、輸入米にも341円/kgの高関税が課せられているため、国内市場だけでは十分な価格抑制が難しい状況です:contentReference[oaicite:5]{index=5}。
今後の見通しと課題
2025年産米は増産見込みが高く、主産県では前年実績を上回る生産目標を設定しています。しかし、備蓄米倉庫が東北・北海道に集中し、西日本への輸送が遅れるなど、地域間の流通格差が依然として課題です。政府は海上輸送による大量移送を開始しましたが、消費地までの安定供給体制整備や物流コストの低減策が急務です:contentReference[oaicite:6]{index=6}。
消費者へのアドバイス
- 価格重視なら備蓄米を含むブレンド米を狙う(5kgあたり3,000円台前半が中心)
- 地元産銘柄米との価格差を比較し、セール時期を狙う
- 大量購入時は予約販売や共同購入を利用し、物流コストを抑制
- ネットスーパーやオンライン直販も併用し、価格と品質を天秤にかける
結論
3週連続の値下がりは市場に一時的な安心感をもたらしていますが、依然として消費者が「安心して買える水準」には達していません。長期的には、コメ生産の構造改革、流通効率化、需給調整メカニズムの強化が不可欠です。政府の備蓄米放出策だけでなく、農家所得の確保と消費者負担の均衡を図る包括的政策が求められています。


コメント:0 件
まだコメントはありません。